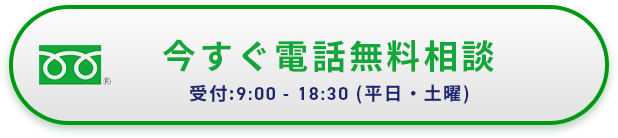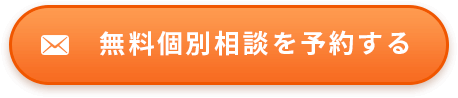法定相続人以外への相続【遺贈】は基礎控除がかかる?計算方法や注意点

監修
中村亨
日本クレアス税理士法人 代表 税理士 公認会計士
相続はだれにとっても避けられないテーマで、特に法定相続人以外への遺贈には独自のルールが多く存在します。
故人の財産総額が基礎控除額に満たない場合、相続で取得した財産・遺贈で取得した財産のどちらにも相続税はかかりません。
つまり、遺贈された人は基礎控除額の計算には含めないものの、控除は適用されるのです。
本記事では、遺贈の種類や相続税の計算方法、そして何より基礎控除がどのように影響するのかをくわしく解説します。
税負担を軽減する方法や遺言書の作成ポイントも含め、法定相続人以外への遺贈を考えている方にとって必読の内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。
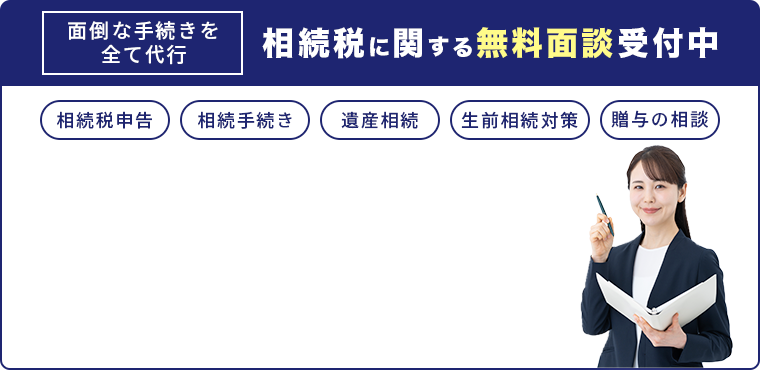
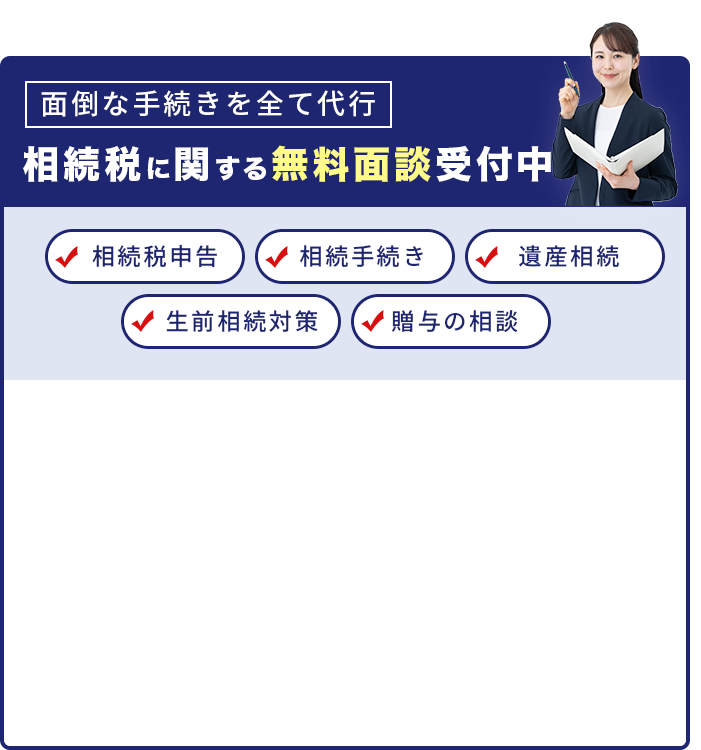
目次
1. 法定相続人以外には遺言によって相続させることができる!

所有する財産を特定の人に譲りたい場合は、遺言書を作成することがおすすめです。
遺言書に財産をあげる人の名前と遺贈するものを書いておけば、法定相続人以外でも財産をもらえます。
これを遺贈といいます。
ここでは、遺贈とは何か、相続税は発生するのかをみていきましょう。
1-1. 遺贈とは?
遺贈とは、遺言書に記載された特定の人が財産を受け継ぐことです。
財産を誰が受け継ぐかを決められるだけでなく、配分方法も財産の所有者が決められます。
遺贈と相続はよく似ていますが、法定相続人への財産の移転とは異なる点があります。
具体的には、相続は法定相続人が財産を引き継ぐプロセスであり、遺贈は遺言書を用いて無償で財産を譲る行為です。
この違いから、遺言書の作成時には法定相続人以外の人に「遺贈する」という言葉を用います。
また、税金の面でも違いがあり、とくに法定相続人以外への遺贈では相続税が2割増しになる場合があるのです。
このような手続きや税金の違いを理解し、遺言書作成時に適切な用語と税務対策をおこなう必要があります。
1-2. 法定相続人以外への相続でも相続税がかかる
法定相続人以外への財産相続で一般的に考えられがちな「法定相続人以外ならば税金がかからない」という認識は誤りです。
実際には、法定相続人以外が遺贈によって財産を受け取る場合には、相続税がかかります。
さらに、配偶者や一親等の親族以外が財産を得る場合、その相続税が2割増しになるので注意しましょう。
ただし、基礎控除額は適用されるため、財産総額によっては相続税がかからない場合もあります。
1-3. 法定相続人以外への相続で基礎控除はある?
基礎控除は一般的に遺産総額から引かれる額ですが、この基礎控除が法定相続人以外にも適用されるかという疑問がしばしば出ます。
結論、法定相続人以外への相続でも基礎控除は適用されます。
ただ、基礎控除の計算式である「3000万円+600万円×法定相続人数」において、法定相続人以外の人は含まれません。
そのため、遺贈によって財産を受け取る人が増えたとしても基礎控除額はそのままです。
死亡保険金や死亡退職金には非課税枠が設けられていますが、この非課税枠は法定相続人以外の人へは適用されません。
なお、非課税枠は「500万円×法定相続人数」と定められています。
これらの点を踏まえ、法定相続人以外への相続に際しては、適用される基礎控除や非課税枠はないことを理解して、税務対策をおこないましょう。
2. 法定相続人以外への相続(遺贈)は2種類
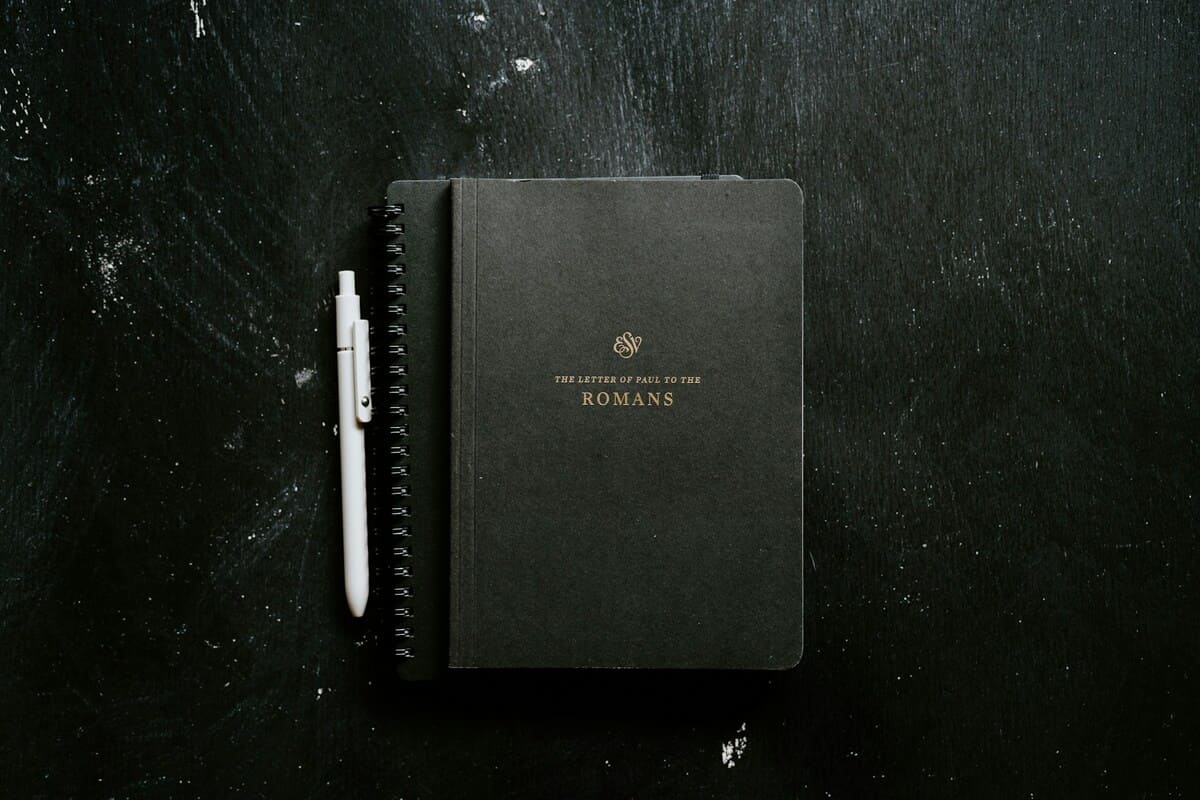
法定相続人以外への相続(遺贈)は2種類あります。
|
<遺贈の種類>
|
それぞれの遺贈はどのような違いがあるのかみていきましょう。
2-1. 特定遺贈
特定遺贈とは、遺言によって特定の財産を特定の人に引き継がせる手法です。
この方法は負債を相続する必要がないため、誰にどの財産を相続させたいのか明確な場合や、負債を受遺者に引き継がせたくない場合にとくに有用です。
特定遺贈を利用する場合には、遺言書に「受け継がせたい財産」と「人物」を明確に指定する必要があります。
特定遺贈にはメリットが多く、とくに法定相続人でない受遺者は遺産分割協議に参加する必要がなく、すぐに遺産を受け取れ負債の相続もありません。
ただし、法定相続人以外が不動産を受け取る場合には、不動産取得税が発生してしまう点に注意が必要です。
なお、指定された財産が無くなった場合、特定遺贈は無効になります。
そして、特定遺贈をおこなう際は遺留分を考慮することが必要。
特定遺贈によって遺留分を侵害してしまうと、相続人の間で遺留分をめぐるトラブルに発展する可能性があるからです。
2-2. 包括遺贈
包括遺贈とは、遺言書で全財産または一定割合の財産を包括的に遺贈する手法です。
包括受遺者は相続人と同等の権利義務を持ち、これによって第三者にも法定相続人と同等の権利や義務を与えられます。
包括遺贈と特定遺贈の主な違いは、包括遺贈が包括的に財産を指定するのに対し、特定遺贈は特定の財産を特定の人に引き継がせる点です。
包括遺贈の場合には、遺贈された割合に応じた負債も相続しなければなりません。
3. 法定相続人以外の相続税・基礎控除の計算

法定相続人以外の相続税・基礎控除の計算はわかりにくく、多くの方が頭を悩ませるところでしょう。
ここでは計算手順をわかりやすく解説します。
3-1. 基礎控除を含めた法定相続人以外の相続税の計算手順
法定相続人以外への相続税の計算手順は独特であり、とくに基礎控除の適用がない点が特徴です。
|
<相続税の計算手順>
|
このような計算手順を理解し、適切に遺贈や相続をおこなうことが重要です。
とくに法定相続人以外への遺贈では相続税が2割増しになるため、遺贈する前に概算しておくといいでしょう。
3-2. 受遺者が法定相続人の場合税負担は軽減される
受遺者が法定相続人である場合、一般的に税負担は軽減されます。
たとえば「小規模宅地等の特例」は、被相続人が居住していた宅地を相続した際、一定の条件を満たせば土地の評価額を80%減額できる制度です。
この特例は、被相続人に配偶者や同居親族がいないこと、さらに遺贈を受けた方が故人と生計を共にしていた親族である場合に適用されます。
また、法定相続人である受遺者に対しては不動産取得税がかかりません。
遺言書を作成する際は、このような税制上の特例をしっかり考慮することが重要です。
3-3. 相続税の申告と納税期限
法定相続人以外への相続(遺贈)であっても、相続税の申告と納税には厳格な期限が設けられています。
被相続人の死亡を知った翌日から10ヶ月以内に、所轄の税務署に相続税の申告と納税が必要です。
ただし、納税に関しては、特別な制度として延納と物納が設定されています。
延納は税金を何年かに分けて納める方式で、物納は財産そのもので税金を納める方法です。
これらを利用する場合、申告期限内に申請と許可が必要です。
特殊な事情がある場合は、申告期限を最大2ヶ月間延長することができるものの、一般的には延長は認められていませんので注意しましょう。
4. 法定相続人以外の人が相続する際の注意点
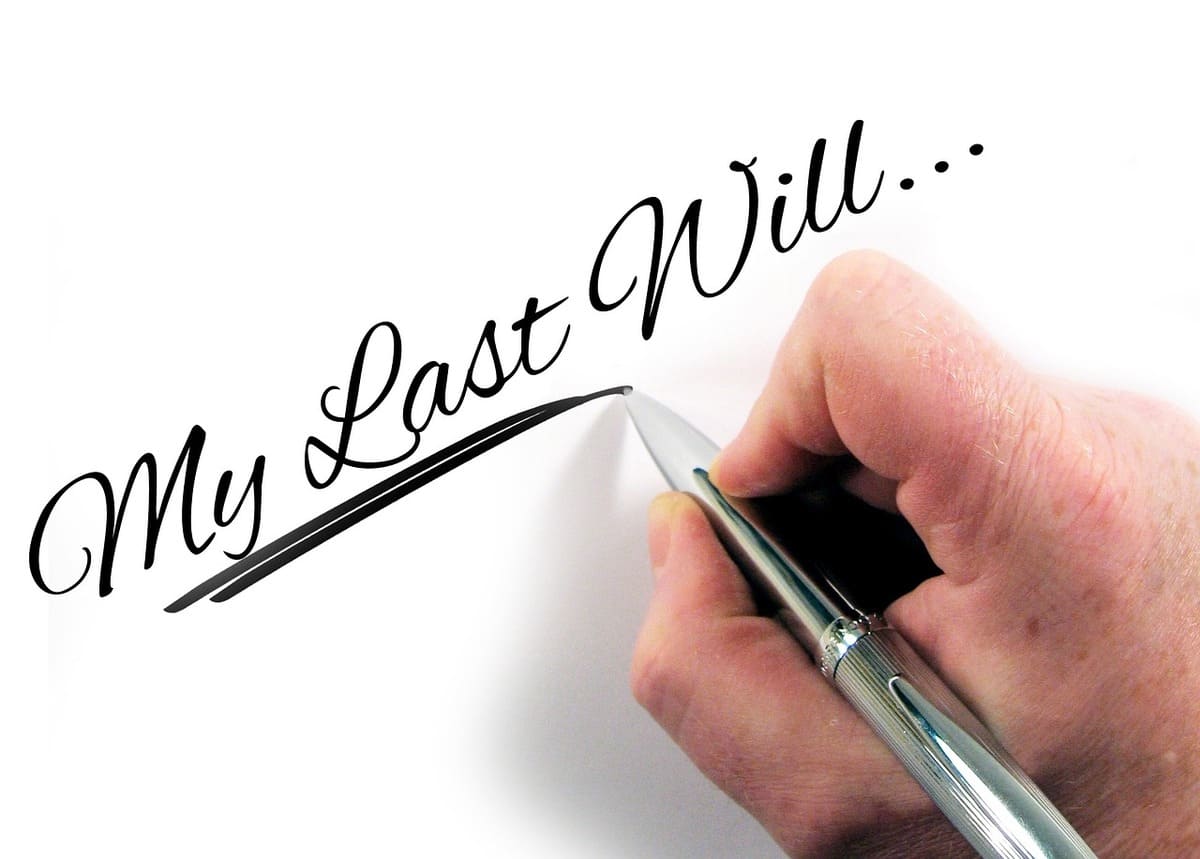
法定相続人以外の人が相続する際の注意点は以下の通りです。
|
<法定相続人以外が相続する際の注意点>
|
相続にはどのような注意点があるのかみていきましょう。
4-1. 遺贈する場合には相続税が2割加算される
遺贈と相続税の関係は独特で、遺贈を通じて財産をもらった場合、贈与税ではなく相続税が適用されます。
とくに注意が必要なのは、被相続人の一親等の血族や配偶者以外が遺贈を受けた場合、その人に課される相続税には2割が加算される点です。
|
<2割加算の対象となる人の例>
|
計算方法も通常の相続とは異なるケースがあり、遺贈で財産を受けた場合にはこの2割加算が適用されることを考慮しなければなりません。
4-2. 小規模宅地等の特例が適用できない場合がある
小規模宅地等の特例は、相続税負担を軽減するための重要な制度です。
遺贈においても利用可能で、遺言によって特定の人に不動産を遺贈する場合、その土地が「小規模宅地」に該当すると一定の税額控除が受けられます。
ただ、特例の適用には要件を満たす必要がありますので注意しましょう。
また、遺贈には特例が適用されますが、生前贈与の場合には適用されません。
生前贈与は特例による税額控除は受けられないことをしっかりと理解して、遺言書の作成や贈与の計画をおこなう必要があります。
4-3. 死亡保険金・死亡退職金の非課税枠がない
死亡保険金や死亡退職金の非課税枠は、相続税額の軽減においてとても重要です。
しかし、この非課税枠は法定相続人以外の人には適用されません。
具体的には、死亡保険金では法定相続人1名につき500万円が非課税で、死亡退職金も「500万円×法定相続人の数」が非課税になります。
法定相続人以外がこれらのお金を受け取る場合、非課税枠は適用されず、全額が課税されるので注意しましょう。
4-4. 遺贈の場合には一部控除が利用できない
特定遺贈を受ける場合、一部の税控除が利用できないケースがあります。
相次相続控除という、前回の相続税から一定の金額を控除できる制度がありますが、この控除は相続人以外が遺贈を受けた場合には適用されません。
さらに、民法では包括受遺者が相続人と同等の権利や義務を持つとされていますが、国税庁の説明によれば、包括受遺者も相次相続控除の適用対象外です。
つまり、包括遺贈でも特定遺贈でも、相続人以外が財産を取得すると相次相続控除は利用できなくなります。
4-5. 不動産取得税・登録免許税がかかる場合がある
遺贈による不動産取得時には税金がかかる場合があるため、注意が必要です。
通常、相続による不動産取得は不動産取得税が免除されますが、遺言で法定相続人以外に不動産を特定遺贈する場合は、不動産取得税が課されます。
また、名義変更に伴う登録免許税も相続と遺贈で異なります。
遺贈は相続税が適用される制度ですが、登録免許税においては贈与の場合と同じく、固定資産税評価額の2%が課税されますので注意しましょう。
4-6. 相続開始前3年間の贈与は相続税の課税対象になる
令和6年1月1日より、相続開始の7年以内にもらった財産価額が相続税に加算されることになりました。
令和6年以前は相続開始の3年以内の生前贈与でしたが、改正後、7年前までに延長されています。
延長された4年間に受け取った財産は、総額100万円が加算対象外となります。
たとえば、相続開始の6年前に200万円を受け取り、2年前に300万円を受け取ったとしましょう。
この場合、6年前に受け取った200万円のうち100万円は加算対象外となるため、200万円-100万円=100万円、100万円+300万円(2年前の生前贈与額)=400万円が相続財産に加算されます。
相続・遺贈のどちらであっても生前贈与の加算が適用されるため、生前に財産を受け取った方はもらった財産価額を計算に含めることが大切です。
4-7. 特定遺贈は債務・葬式費用を控除できない
特定遺贈で土地や建物などをもらった場合は、債務・葬式費用の控除を適用できません。
相続、または包括遺贈であれば財産を持っていた人の債務や葬式費用などを控除することが可能です。
しかし、土地や建物など特定の財産を遺贈によって受け取る場合は控除が適用できないので、納税額が多くなる恐れもあります。
4-8. 納税資金を用意できない可能性がある
突然の遺贈により、納税資金を用意できない可能性があります。
財産所有者の法定相続人であれば、所有者の健康状態にあわせて相続対策を前もって行えるでしょう。
しかし、遺言書によって法定相続人以外の人が財産を受け取るとなると、何の対策もしていないことから、納税資金を用意できない可能性が出てくるのです。
遺言書は、財産所有者が亡くなってから開封されます。
亡くなるまでは誰も内容を知ることができないので、突然の遺贈における納税に対応できないかもしれません。
5. 法定相続人以外に相続させる遺言書作成ポイント
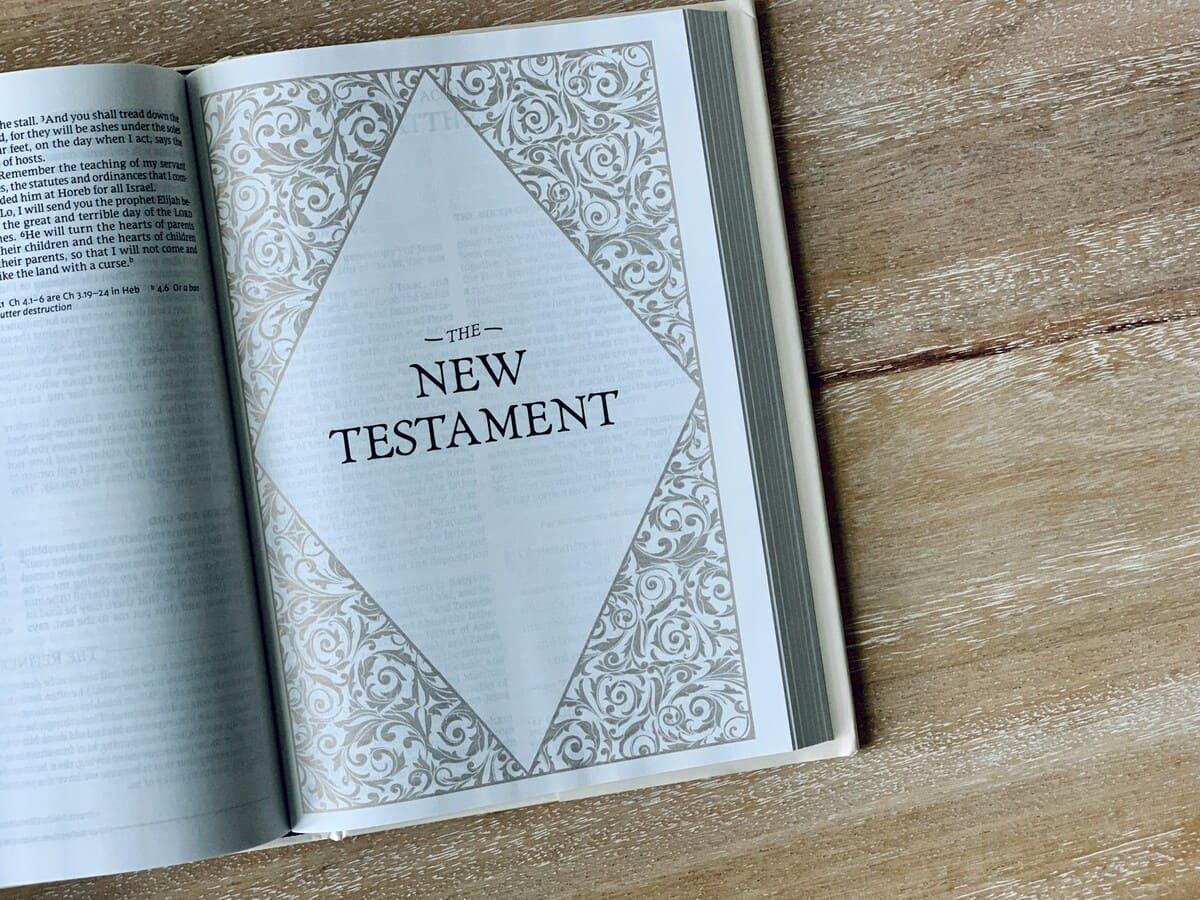
法定相続人以外の人に相続させる遺言書作成のポイントは以下の通りです。
|
<遺言書作成のポイント>
|
それぞれについてくわしく解説します。
5-1. 公正証書遺言で作成する
法定相続人以外に相続する際は、公正証書遺言を作成することがおすすめです。
遺言書の作成では公正証書遺言に多くのメリットがあります。
|
<公正証書遺言のメリット>
|
公正証書遺言は証拠力が高く、遺言の実行確率も上がるため、遺言内容が争われるリスクが低くなるのも特徴です。
さらに、遺言執行者を指定すれば、相続手続きがスムーズに進むでしょう。
付言で遺贈の理由や思いを明示すると、法定相続人も納得しやすくなる可能性があります。
また、元本を公証役場が保管してくれ、検認の必要がないことも大きなメリットです。
5-2. 遺留分の侵害に気を付ける
遺留分を考慮しない遺言は相続トラブルの原因になる可能性が高いので、公平な財産分配をおこなうことが必要です。
遺留分の侵害は、相続人の間でのトラブルを引き起こすリスクがあります。
遺留分とは、相続人が最低限受けるべき遺産の割合で、考慮せずに遺言書を作成すると、相続人が納得せずに紛争に発展する可能性が高いのです。
対策としては、遺言書を作成する際に遺留分をしっかり考慮し、公平な財産分配をおこないましょう。
遺留分が侵害された場合、相続人は「遺留分侵害額請求」をおこなうことでその部分を取り戻せます。
5-3. 遺言執行者を指定する
遺言執行者の指定は、相続手続きを円滑に進めるために重要です。
遺言執行者は遺言者の意志に基づき、遺産分割や遺贈の手続きをおこない、相続手続きを円滑に進めます。
近年の相続法改正によって、遺言執行者の権限がさらに拡大され、単独での登記手続きが可能になっています。
このように遺言執行者は単独でさまざまな手続きをおこなえるため、手続きが効率的に進むのもメリットです。
5-4. 付言で相続トラブルを防止する
付言の利用は、相続トラブルを未然に防ぐ有効な手段です。
付言には、遺言者の意志や気持ちを明示して、相続人の不満やトラブルを未然に防ぐ効果があります。
とくに公正証書遺言によって、特定の誰かに多く財産を遺す場合には、付言を設けることが推奨されています。
5-5. ほかの相続人にも遺贈することを伝える
遺贈をスムーズにおこなうためには、その意志をほかの相続人にも明確に伝えることがトラブル防止につながります。
遺贈することで、相続内容に変化が生じてしまうため、ほかの相続人に伝えていないと遺産分割協議などでトラブルになってしまうのです。
遺贈についてほかの相続人にもしっかりと説明することが、スムーズな相続手続きとトラブル防止につながるでしょう。
6. 特別寄与料制度で相続させることができる場合がある!
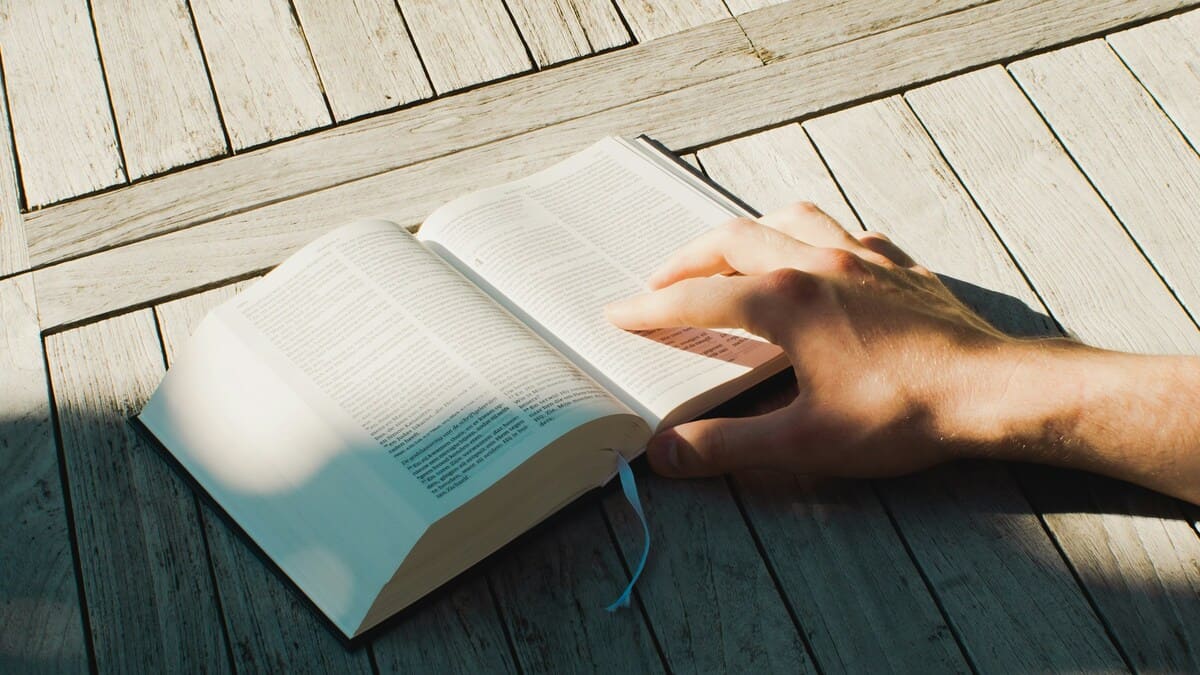
相続の権利を持たない人は、故人が残した遺言書がなければ財産をもらうことができません。
しかし、法定相続人以外の人が無償で故人の身の回りのことをしていた場合は、不公平さを感じるでしょう。
ここでは、法定相続人以外の人が利用できる特別寄与料制度を紹介します。
相続の権利を持っていないけれど、故人の身の回りの世話をしていたという方はぜひ参考にしてください。
6-1. 特別寄与料制度とは?
特別寄与料制度とは、法定相続人以外の人が故人の生前のお世話をしていた場合、相続人に金銭を請求できる制度です。
相続の権利を持たない人は、故人の生前の世話をしていたとしても、財産をもらうことはできません。
しかし、身の回りをしていた人が財産をもらえず、介護をしなかった人が財産をもらえるとなれば不公平になります。
この問題を解決できるのが特別寄与料制度です。
6-2. 特別寄与料制度を利用できる条件
特別寄与料制度を利用するには、条件を満たさなければなりません。
制度を適用する条件は以下のとおりです。
|
3つの条件を満たすことに加え、制度を利用して金銭を請求する人にも要件が定められています。
|
相続の権利を持つ人は財産をもらうことができるため、制度を利用する必要はありません。
相続の権利を持たない親族のみが利用できるので、すべての条件を満たす場合は制度を活用しましょう。
6-3. 金銭の請求先は?
金銭の請求先は、故人の財産を受け取った相続人です。
相続人は、法定相続分に則って、請求された金額を支払わなければなりません。
請求できる金額は、家庭裁判所が決定します。
自身で計算することは難しいため、制度を利用する際は税理士に相談することがおすすめです。
相談し、指示を仰げば、介護や療養看護に見合った金額を請求できます。
7. 法定相続人以外への相続(遺贈)についてよくある質問
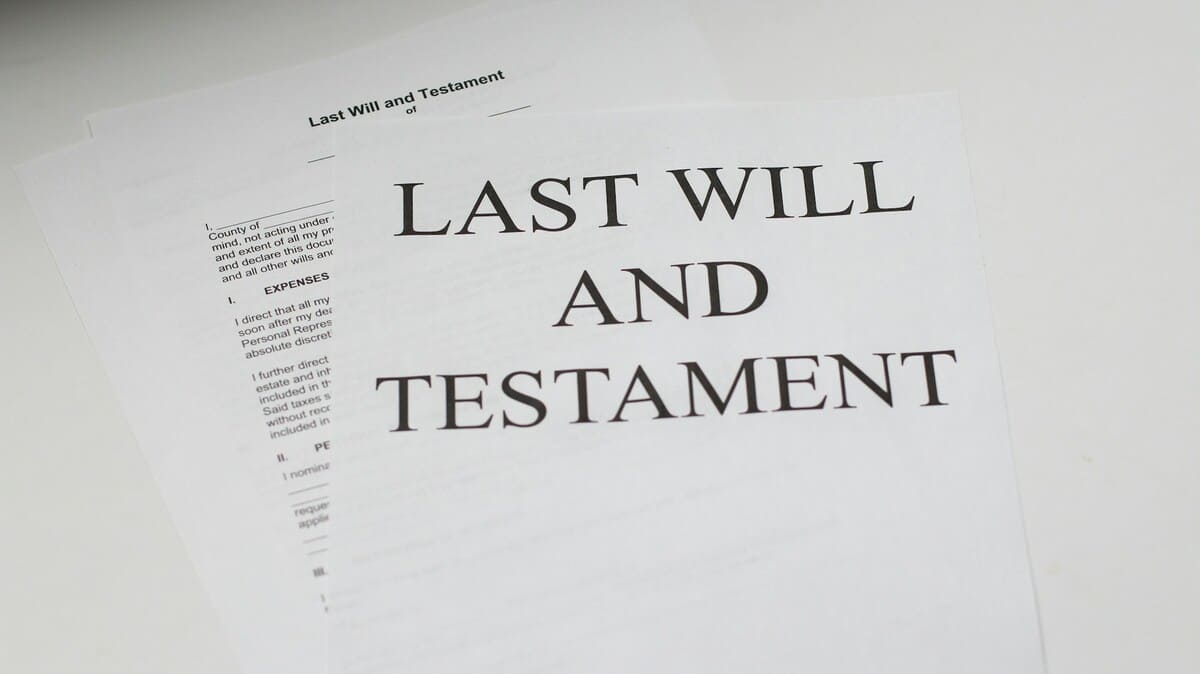
法定相続人以外の人が財産を受け取る遺贈について、気になる点がいくつかあるという方も多いでしょう。
- 遺贈の受遺者が被相続人よりも先に亡くなった場合どうなるの?
- 遺贈を放棄することはできる?
- 遺言なしで法定相続人以外に相続はできない?
- 遺贈と死因贈与は何が違う?
ここでは、遺贈についてよく寄せられる質問を紹介します。
7-1. 遺贈の受遺者が被相続人よりも先に亡くなった場合どうなるの?
遺贈の受贈者が財産所有者よりも先に亡くなった場合、遺言内容は無効となります。
一点注意したいのが、遺言書そのものの効力がなくなるわけではなく、亡くなった人の部分のみが無効になることです。
そのほかの内容については効力が生じるため、ほかに受贈者がいれば、遺言書通りに財産を分配しなければなりません。
先に亡くなった人がもらう予定だった財産は、法定相続分に戻されます。
7-2. 遺贈を放棄することはできる?
遺贈によって受け取る財産が不要、または受け取ることを拒否したい場合は、遺贈を放棄することが可能です。
前述したように、遺贈には特定と包括の2種類があります。
特定の場合は、相続の権利を持つ人に放棄したいと伝えるだけです。
後々のトラブルを防ぐためにも、放棄の旨を記した文書を内容証明便で送るといいでしょう。
包括の場合は、相続人と同等の権利を有するため、家庭裁判所に放棄の申し立てを行わなければなりません。
特定に比べて手間がかかるため、早めに手続きを進めることが大切です。
7-3. 遺言なしで法定相続人以外に相続はできない?
遺言書なしでは法定相続人以外の人に遺贈できません。
介護や療養看護をする際、被相続人から「財産をあげる」と言われることもあるでしょう。
亡くなった後に財産をもらえると思いがちですが、遺言書がなければ財産をもらうことはできないため、注意が必要です。
財産をゆずることを証明するには、遺言書を作成することが重要です。
ただし、無効となる遺言書では意味がないため、公正証書遺言を作成しましょう。
公正証書遺言とは、公証人が遺言内容を書面にまとめるものです。
公証人は法律のプロなので、効力のある遺言書を作成・保管してくれます。
7-4. 遺贈と死因贈与は何が違う?
遺贈は財産所有者が亡くなった後に開封される遺言書によって判明、死因贈与は所有者の生前に譲る内容が判明するものです。
遺贈は所有者が亡くなるまで財産の譲り先がわからないものの、死因贈与は生前に譲る人・受け取る人の間で契約が成立しているため、相続税の対策をしやすいメリットがあります。
どちらも「贈」という漢字が付いているものの、財産を受け取るのは所有者の死後です。
そのため、受け取る財産に対する税金の種類は贈与税ではなく、相続税となります。
8. 法定相続人以外への相続は基礎控除の計算に含まない
法定相続人以外への遺贈は可能ですが、基礎控除の計算には含まれません。
この点にはとくに注意が必要で、知らないと受遺者の税負担が大きくなってしまう可能性があります。
遺贈には特定遺贈と包括遺贈の2種類がありますので、状況によって適切に使い分けましょう。
また、受遺者が法定相続人である場合は税負担が軽減されるケースもあるため、よく確認してください。
税の申告と納税には期限があり、過ぎると罰則が適用される場合もあります。
遺言書作成時には公正証書遺言が推奨され、遺留分侵害や遺言執行者の指定、付言を用いて相続トラブルを防ぐ工夫が必要です。
さまざまな要点を押さえたうえで、法定相続人以外への相続を検討しましょう。

監修
中村亨
日本クレアス税理士法人 代表
税理士
公認会計士
2002年8月に会計事務所として創業、2005年には税理士事務所を開業し、法人や個人のお客様の会計・税務の支援をする中で、「人事労務の問題を相談をしたい」「事業承継を検討している」といったお客様のニーズに応える形でサービスを拡大し続け、現在では社会保険労務士法人など複数の法人からなるグループ企業に成長してきました。お客様に必要なサービスをワンストップで提供できることが当社の強みです。