「遺言検索システム」とは?遺言書の有無を調べられる
生前対策など何もしていないように見えた人が突然亡くなり、遺族のだれも遺言書があるのかどうか分からない、という事はよくある話です。
このようなときには、ひとまずお近くの公証役場に行って、公正証書遺言の有無を確認してはいかがでしょうか。 公正証書遺言は、原本を公証人が管理しており(管理期間は150年)、遺言書が破棄・隠匿された場合でも、公証役場で謄本を入手することができるのは良く知られているかと思います。
「遺言検索システム」とは?
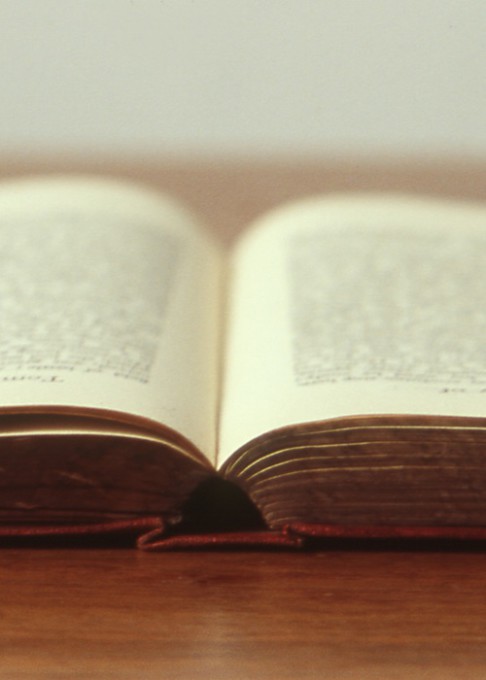
昨年より、全国いずれの公証役場においても、平成元年以降に作成した全国すべての公正証書遺言及び秘密証書遺言の有無が、確認できるようになりました。
日本公証人連合会は、公正証書の原本を電磁的記録化して、これをその原本とは別に保管する、いわゆる「原本の二重保存」を進めています。
これは、東日本大震災を教訓に、今後予想される大規模災害等の発生により遺言公正証書の原本・正本・謄本のいずれもが滅失する事態に備えたものです。 重要な公文書の二重保存という政府の施策の一環であり、また、国民の権利保護と私的紛争の予防に重要な役割を果たす公正証書の原本保存の保管体制を整備・強化して、公正証書への信頼を一層確保しようとするものです。
検索申請が可能な人
遺言者の存命中は、遺言者本人のみが申請できます。 遺言者の死亡後は、法定相続人、受遺者、遺言執行者などの利害関係人に限って申請することができます。
検索申請の仕方
遺言書の検索は、相続人が近くの公証役場に出向き、
- 相続開始の事実を証明する書類(除籍謄本、死亡診断書等)
- 法律上の利害関係を有していることを証明できる書類(戸籍謄本)
- 請求される方の身分を証明する書類
以上の書類を提出したのち、公証人からオンライン一元管理している日本公証人連合会に対して照会することで実施されます。 公証役場に備え付けられた端末で誰でも自由に検索できるというわけではありませんので、秘密はしっかり守られるわけです。
原本が保管されている公証役場の情報がもたらされたら、実際に保管されている公証役場に出向き、はじめて遺言書の謄本の交付を受けることになります。
【お役立ちコンテンツ】
相続相談はどこにするべき?専門家(税理士、司法書士、弁護士)の強み
【クレアスの相続税サービス】
