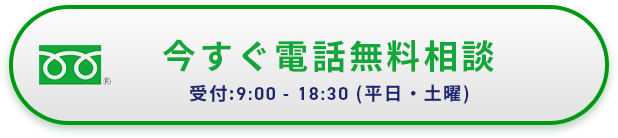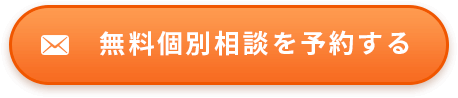保佐人とは?得られる4つの権限やできないこと、補助人・成年後見人との違いを分かりやすく解説

監修
中村亨
日本クレアス税理士法人 代表 税理士 公認会計士
高齢の祖父母のサポートをするにあたり、保佐人という言葉を目にしたけれど、何ができるのかわからないとお困りではありませんか。
保佐人は、判断能力の低下が認められる人に欠かせない存在です。
高齢の親族のサポートを検討しているのなら、保佐人についてくわしく知ることがおすすめです。
この記事では、保佐人とは何か、本人に代わって何ができるのかを解説します。
保佐人になれる人や必要になるケース、終了するタイミングまでを紹介するので、興味のある方は参考にしてください。
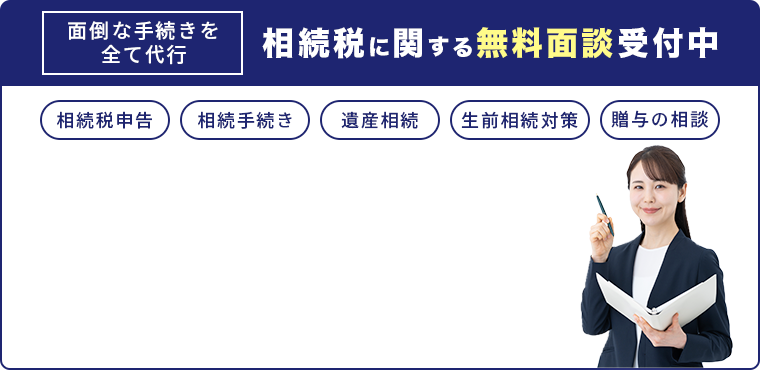
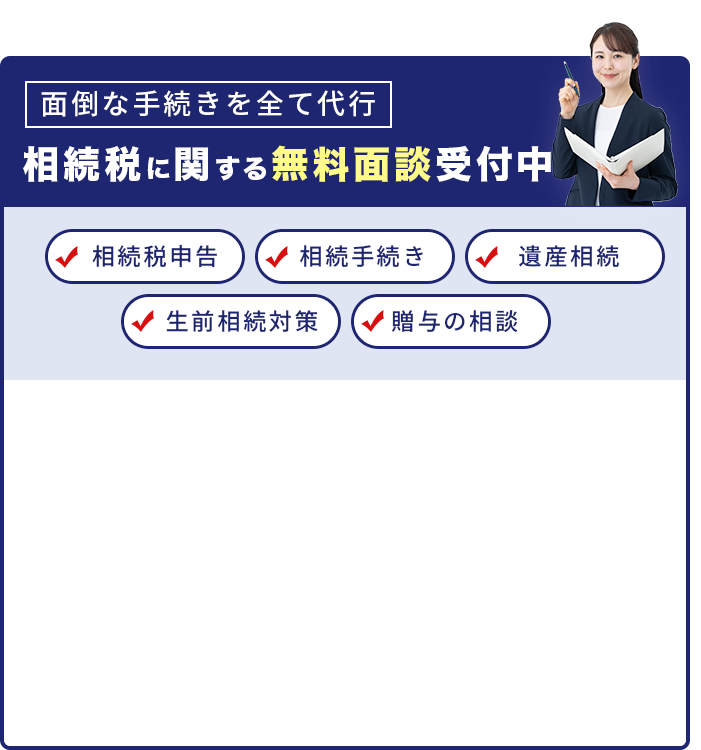
目次
1. 保佐人とは?
高齢の親族がいる人に知っておいてほしいのが、保佐人の存在です。
ここでは、保佐人とは何か、何ができるのかを解説します。
1-1. 判断能力が低下した人に代わって一部法律行為を行える人
適切な判断ができなくなった人に代わって、一部法律行為を行える人を保佐人といいます。
人は、年齢とともに損得や正否を判断する能力が低下します。
若いときは甘い話に騙されることがなくても、高齢になって分別がつかなくなり、詐欺に遭ってしまうケースも少なくありません。
保佐人は、詐欺や多大な浪費などのトラブルを防止するために存在します。
本人が行った一部法律行為に対し、4つの権限を行使できるため、高齢の親族への経済的搾取を未然に防ぐことが可能です。
1-2. 補助人・成年後見人との違い
保佐人とよく似た言葉に、補助人と成年後見人があります。
それぞれの特徴をまとめました。
| サポートする対象 | 職務の内容 | |
| 保佐人 | 契約における必要性や損得、正否などを判断しづらくなっている人 | 本人が行った一部法律行為に権限を行使できる |
| 補助人 | 日常生活に支障がないものの、適切な判断がしにくくなっている人 | 家庭裁判所が定める重要な契約、または特定の行為に権限を行使できる |
| 成年後見人 | 認知症や精神疾患などによって判断能力が失われている人 | 本人に代わって、すべての法律行為に権限を行使できる |
それぞれで対象となる人の特徴が異なります。
能力の度合いによって行使できる権限も変わるため、サポートする人の状態から名称が変わると考えておきましょう。
2. 保佐人が持つ4つの権限

保佐人はいくつかの権限を持つため、本人が行った一部法律行為に関与できます。
どのような権限が与えられるのか見ていきましょう。
2-1. 同意権
サポートの対象者が重要と判断される法律行為を行うには、保佐人から了承を得なければなりません。
了承を得る必要がある行為は以下の通りです。
- 預貯金の払い戻し
- お金を貸す
- 貸していたお金を返済してもらう
- 金融機関からの借り入れ
- 第三者の債務の保証人の引き受け
- 不動産の売買
- 不動産や土地などの賃貸借の解除
- 不動産の抵当権の設定
- 株式の購入と売却
- 訴訟や和解、仲裁合意
- 贈与と贈与申し込みの拒絶
- 遺贈の放棄
- 相続の承認・放棄・遺産分割
- 不動産の新築や改築、増築など
- 一定期間以上の賃貸借の申し込み
- 上記の行為を未成年者の法定代理人として行った行為
日常生活に関する行為は除外されますが、上記のいずれかを本人が行った場合、保佐人の関与が可能です。
本人が損をすると認められれば、保佐人は取消権を行使できます。取消権については、後ほど紹介しましょう。
2-2. 代理権
特定の人が家庭裁判所に申し立てることで、保佐人は代理権を得られます。
原則として、保佐人は代理権を持ちません。
本人に代わって法律行為を行えないので、知らない間に本人が損をするような契約を締結してしまう恐れがあります。
法律行為におけるトラブルを徹底的に防ぐのなら、代理権の申し立てを行うことがおすすめです。
代理権の申し立てを行えるのは、以下の人物です。
- 本人
- 本人の配偶者
- 四親等以内の親族
- 後見人
- 保佐人
- 補助人
多くの人が申し立てを行えるため、本人の判断能力に不安を覚える場合は、早めに手続きを行いましょう。
代理権を与えられることで、特定の法律行為を保佐人が代わりに行えます。
2-3. 取消権
取消権とは、本人が保佐人の了承を得ずに行った一部の法律行為を取り消せる権限です。
前述したように、保佐人を付けると、生活のなかの一部法律行為で同意を得る必要があります。
了承がなければ契約の締結や解除ができないので、なかには黙って法律行為を進める人もいるでしょう。
保佐人が本人の法律行為に気付き、損をすると判断すれば法律行為の取り消しが可能です。
本人が被る損害を早めに抑えられるため、サポートする対象者の動向をしっかりチェックすることが大切です。
2-4. 追認権
追認権は、契約を締結、または解除する相手側にとって重要な権限です。
本人が保佐人に黙って契約の締結・解除をしてしまうケースは珍しくありません。
しかし、本人が損をする内容だと判断されれば、保佐人によって法律行為が取り消されてしまいます。
契約する相手は、一度決まった契約を取り消されては困るでしょう。そこで使えるのが追認権です。
追認権は、本人が締結した契約を、保佐人が後から認めるものです。
たとえば、本人が不動産会社から住宅を購入する契約を締結したとします。
本人が同意を得ていない場合、後から契約を取り消される可能性を考慮して、不動産会社が保佐人に確認することが可能です。
保佐人が締結した契約を追認すれば、その後、取消権を行使できません。
3. 保佐人ができない2つのこと

いくつもの権限が与えられる存在であるものの、場合によっては関与できないこともあります。
ここでは、保佐人ができない2つのことを紹介しましょう。
3-1. 日常生活に必要なこと
保佐人は、本人の日常生活に必要なことには関与できません。
同意見や取消権を行使できるのは、あくまで法律行為のみです。
何らかのものの売買や賃借など、法律行為が発生する行為に対して権限を行使できます。
たとえば、本人が家事をできず、家事代行サービスを頼むとします。
家事代行サービスの契約は法律行為にあたるため、保佐人の介入が可能です。
しかし、契約後の家事代行については介入できません。
つまり、契約そのものは保佐人の了承を得なければ締結できませんが、サービス内容に関しては本人が決めることになります。
3-2. 連帯保証人や身元引受人
保佐人は、本人の連帯保証人や身元引受人にはなれません。
連帯保証人は高額のものを購入する際にローンを組むとき、身元引受人は病院への入院や施設に入所する際に必要です。
しかし、保佐人にはどちらの権限もないため、引き受けないよう注意が必要です。
権限を持たない人がどちらかを引き受けてしまうと、後々のトラブルを招く恐れがあります。
本人がローンを返済しなかったり、入所先の病院や施設でトラブルを起こすと、連帯保証人や身元引受人が損害賠償を請求される恐れがあります。
トラブルを避けるためにも、本人から同意を求められても応じないようにすることが大切です。
4. 保佐人になれる人とは?

高齢の親族のサポートをしたいけれど、自分は認められるの?と気になっている方も多いでしょう。
ここでは、保佐人になるための要件を解説します。
4-1. 家庭裁判所から認められればOK
家庭裁判所から保佐人としてふさわしいと判断されれば、誰でもなれます。
特別な資格や本人との関係性についての要件が定められているわけではないので、親族のサポートをしたいと思ったら、申し立てをすることがおすすめです。
高齢者のサポートをする立場になるため、多くは親族が申し立てを行います。
前述したように、特別な要件は定められていませんが、なかには親族でも認められないケースがあるので、認められない人の特徴を把握しておきましょう。
4-2. 親族でも認められないケースがある
親族でも認められない人の特徴は以下のとおりです。
- 未成年
- 自己破産の経験がある人
- 家庭裁判所から解任されたことがある法定代理人・補助人・保佐人
- 本人に訴訟を起こした経験のある人、その配偶者や親族
- 行方がわからない人
上記のいずれかに当てはまる人は、保佐人として認められません。
特徴に該当する人は、本人への適切なサポートが行えないと判断されるからです。
上記の特徴に該当せず、適切なサポートができると認められれば、問題なく認められるでしょう。
高齢の親族のサポートが必要であるにもかかわらず、親族内に適切だと判断される人がいなければ、弁護士や司法書士が保佐人に適用されるケースもあります。
5. どのようなケースで保佐人を用意すべき?
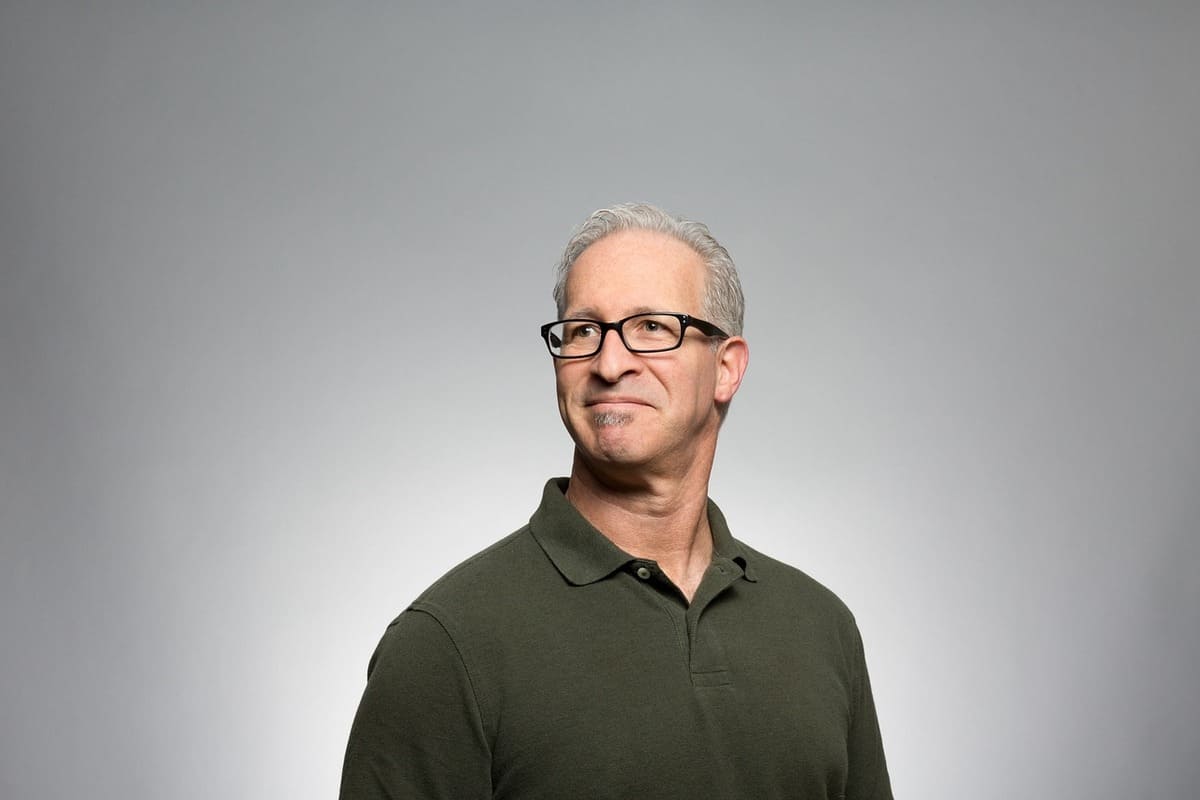
親族が高齢になったからといって、必ずしも保佐人を用意する必要はありません。
日常生活に支障がなく、適切な判断を下せる能力を有していれば、親族のちょっとしたサポートのみで問題なく生活できるでしょう。
では、どのようなケースで必要とされるのでしょうか。
民法11条で保佐人を必要とするケースが定められています。

親族が「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者」に該当する場合、保佐人の申し立てを行えます。
年齢や精神疾患などが原因で判断能力が低下し、不当な契約を締結する恐れがあると判断されれば、申し立てを行うことが可能です。
契約における必要性や損得の判断ができなくなっているようであれば、早めに申し立てを行いましょう。
家庭裁判所からも必要性を認められれば、保佐人を付けられます。
6. 保佐人を選定するまでの流れ
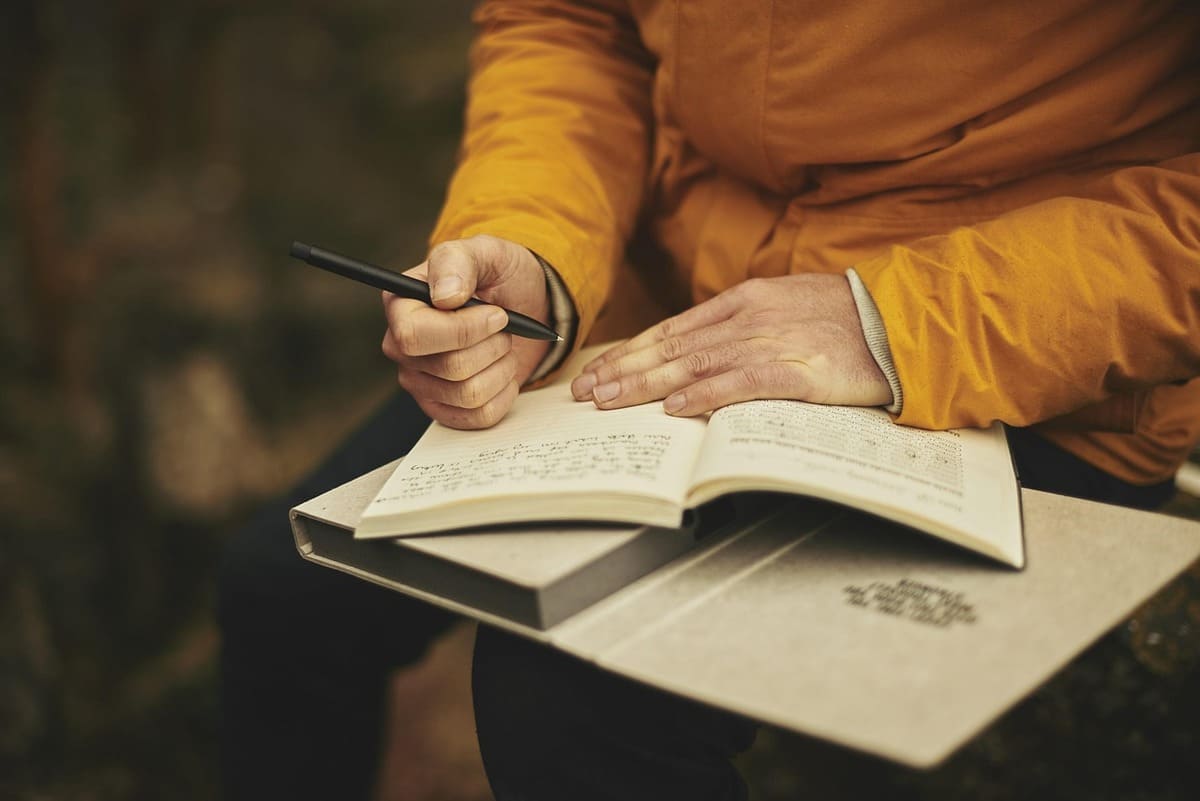
高齢の祖父母にサポート役を付けたいけれど、どのように手続きを進めていけばいいかわからないとお悩みの方も多いでしょう。
ここでは、保佐人を選定するまでの流れを解説します。
6-1. 保佐人に関する書類の準備
まずは、家庭裁判所への申し立てに必要な書類を準備しましょう。
用意する書類は以下の通りです。
| 必要な書類 | 入手場所 |
| 申し立ての書類 | 裁判所のホームページ |
| 保佐人になる人の戸籍・住民票 | 自治体 |
| 本人の診断書 | 裁判所のホームページ |
| 本人が成年後見人などに登記されていないことを証明する書類 | 法務局 |
| 本人の財産に関する資料 | 通帳のコピーや不動産登記事項証明書など |
| 本人の収支に関する資料 | 給与明細書や確定申告書など |
| 同意見や代理権が必要な行為に関する資料 | 契約書のコピー |
自治体で入手できるものや本人が保管している書類のほか、裁判所のホームページからダウンロードするものもあります。
本人の診断書は、病院で発行してもらう必要はありません。
裁判所ホームページにある「成年後見制度における診断書作成の手引 本人情報シート作成の手引」の診断書部分をダウンロードしましょう。
診断書部分には、医学的診断や受けた検査名を記入する項目があるため、事前に本人を病院に連れていく必要があります。
診断を終えなければ必要な書類を準備できないので、早めに受診しましょう。
6-2. 家庭裁判所に申し立てを行う
必要な書類を準備したら、家庭裁判所に審判の申し立てを行います。
済んでいる地域を管轄する家庭裁判所に出向き、必要書類を提出して手続きを進めましょう。
申し立て後、裁判所で事情聴取が行われます。
6-3. 家庭裁判所が判断する
事情聴取後、家庭裁判所にて審判を実施します。
審判によって保佐人を付ける必要があること、候補者がサポート役にふさわしいと認められれば、登記開始です。
完了後に保佐人として動けるようになるため、家庭裁判所からの通知を待ちましょう。
6-4. 保佐人への報酬も忘れずにチェック
保佐人を付ける際は、報酬も忘れずに確認しておきましょう。
保佐人として認められた人には、月額の報酬が与えられます。
目安は月額20,000円前後、正確な金額は家庭裁判所が決定します。
通常の職務のほかに特別な行動が求められる場合、付加報酬も上乗せしなければなりません。
付加報酬は基本報酬の50%以内が目安とされているので、基本・付加どちらの報酬も確認することが大切です。
7. 保佐人をやめる・終了するケース

親族のサポートをしていたけれど、事情があって職務を全うできなくなったという方もいるでしょう。
保佐人として動けなくなった場合、どうやってやめればいいのかを解説します。
保佐人としての職務が終了するケースもあわせて紹介しましょう。
7-1. 家庭裁判所の許可が下りればやめることが可能
保佐人を続けられない事情が家庭裁判所で認められれば、やめることが可能です。
人は生きていくなかで取り巻く環境が大きく変化していくため、ときには職務を続けられない事情も出てくるでしょう。
仕事の転勤で本人の居住地から離れなければならない、病気で本人のサポートが難しくなったなど、職務を続けることができないと判断されれば、保佐人をやめられます。
ただし、保佐人をやめるときは家庭裁判所の許可が必要です。
また、自身がやめた後の代わりを探す必要もあるので、サポートできる人を選定したうえで、家庭裁判所に出向きましょう。
7-2. 要件に該当する場合は保佐人の業務が終了
保佐人としての業務は、無条件に続くわけではありません。
保佐人が終了する要件を見てみましょう。
- 本人の判断能力が回復したと判断されるとき
- 本人の後見開始、または補助開始の審判が行われるとき
- 家庭裁判所から保佐人が解任されたとき
- 保佐人が自己破産の手続きを開始したとき
- 保佐人、その配偶者や親族が本人に対して訴訟を起こしたとき
- 保佐人の行方がわからなくなったとき
いずれかに該当するときは、保佐人の業務が終了します。
8. 高齢の親族がいる場合は早めに保佐人を選定しよう
高齢で判断能力が不安視される親族がいる場合は、早めに保佐人を選定することがおすすめです。
判断能力が低下した状態では正常な判断ができず、不要な売買や詐欺にあうリスクが高まります。
保佐人がいればリスクを回避できるため、親族も安心できるでしょう。
保佐人になるのに特別な要件はありませんが、親族でも認められないケースもあります。
サポートをしたいと考える方は、認められないケースに該当しないかを確認しましょう。
早めに手続きを進めることで、高齢の祖父母の安全な暮らしをサポートできます。

監修
中村亨
日本クレアス税理士法人 代表
税理士
公認会計士
2002年8月に会計事務所として創業、2005年には税理士事務所を開業し、法人や個人のお客様の会計・税務の支援をする中で、「人事労務の問題を相談をしたい」「事業承継を検討している」といったお客様のニーズに応える形でサービスを拡大し続け、現在では社会保険労務士法人など複数の法人からなるグループ企業に成長してきました。お客様に必要なサービスをワンストップで提供できることが当社の強みです。