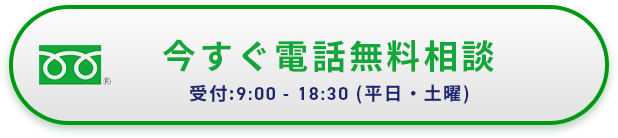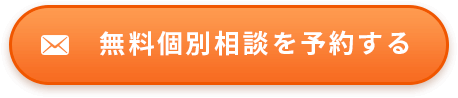投資信託の相続税評価方法は3つ!種類ごとの計算方法や注意点を解説

監修
中村亨
日本クレアス税理士法人 代表 税理士 公認会計士
亡くなった親が投資信託をしており、利益を得られそうだけど、相続の対象になる?と気になっていませんか。
投資信託は、投資したお金をもとに専門家が運用し、利益を得るものです。
投資信託によって得られる利益も故人の財産になるため、相続税が発生すると考えておきましょう。
本記事では、投資信託の相続税の評価方法を解説します。
相続する流れや注意点も紹介するので、両親や祖父母が投資信託を行っている方は参考にしてください。
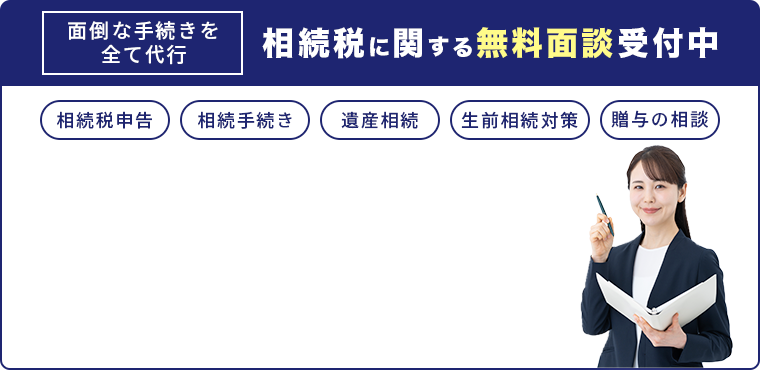
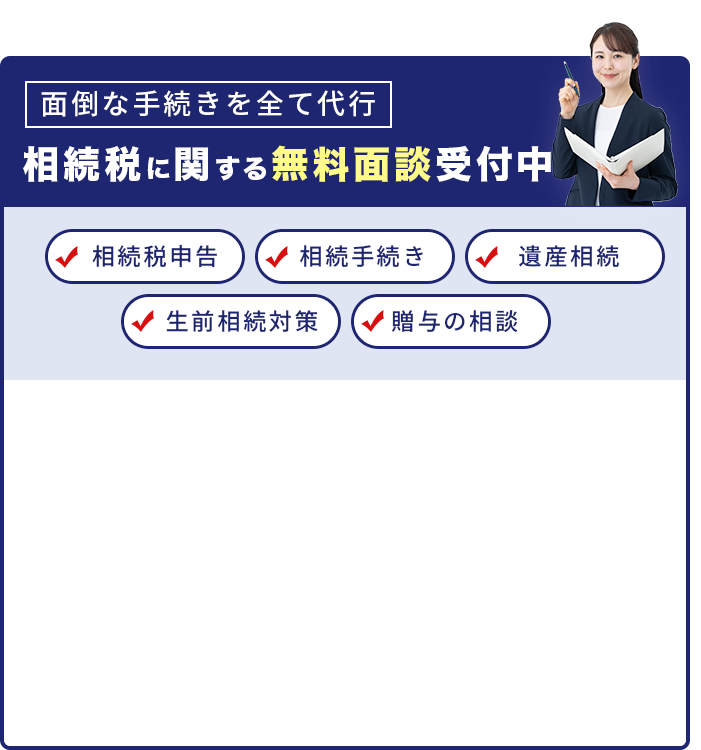
目次
1. 投資信託は相続税の対象

両親や祖父母が行っていた投資信託は相続税の対象になるため、計算する際に必ず評価額を算出しておきましょう。
ここでは、なぜ投資信託は相続税の課税対象なのか、相続が決まったらまずは何をすべきなのかを紹介します。
1-1. 相続税がかかる理由
投資信託は故人が所有していた財産に該当するため、相続する場合は税金が発生します。
相続税は、亡くなった人が持っていた財産を法定相続人が受け取る際に課せられる税金です。
投資信託の場合は、運用によって発生した利益を受け取る権利である受益権が財産とみなされます。
受益権を相続すれば、運用時に得られる利益をもらえるため、相続税の対象になると覚えておきましょう。
1-2. 相続財産目安額の把握
両親や祖父母が亡くなった際は、投資信託を含めた故人の所有財産すべてを調査しなければなりません。
現金や口座に預けているお金、家や土地など、人によって所有する財産は多岐にわたります。
すべてを把握し、財産がどれくらいあるかを確認することで相続の手続きを進められます。
財産の調査は1人では難しいため、親族と協力して行うことがおすすめです。
協力を得られない場合は、調査の専門家である税理士に相談してみましょう。
2. 相続税の計算に必要な投資信託の評価方法は?

投資信託にはいくつかの種類があり、それぞれで相続税の計算に必要な評価方法が異なります。
|
上記の投資信託について、種類別の評価法を詳しく解説します。
2-1. 日々決算型投資信託の相続税評価額
日々決算型投資信託の評価額を算出する方法は以下の通りです。
|
日々決算型投資信託の計算方法 「1口あたりの基準価額×口数+再投資されていない未収の分配金-未収の分配金で源泉徴収されるべき所得税の相当額-信託財産留保額および解約手数料」 |
所得税の相当額には、源泉徴収・道府県民税・復興特別所得税に相当する額も含めましょう。
いくつもの情報を集めたうえで計算する必要があるため、情報に誤りがないかを入念に確認することが大切です。
2-2. 一般投資信託の相続税評価額
一般投資信託の評価額を算出する方法は以下の通りです。
|
一般投資信託の計算方法 「1口あたりの基準価額×口数-源泉徴収税額-信託財産留保額および解約手数料」 |
源泉徴収税額は、投資信託をしていた人が亡くなった日に売却することを想定して算出しましょう。
売却した場合の含み益×20.315%から算出される数字が、源泉徴収税額です。
2-3. 上場投資信託・不動産投資信託(J-REIT)の相続税評価額
上場投資信託・不動産投資信託の評価額を算出する方法は以下の通りです。
|
上場投資信託・不動産投資信託の計算方法 「1口あたりの基準価額×口数」 |
基準価額は、金融機関が発行する残高証明書で確認できます。
なかには証明書に基準価額が記載されていないものもあるため、その場合は自身で計算して算出しなければなりません。
基準価額を算出する際に確認すべきポイントは以下の通りです。
基準価額の算出に必要なポイント
|
上記4つのポイントを確認し、最も安い数値を評価額の計算に用います。
最も安い数値÷口数から1口当たりの基準額を算出し、保有する口数を掛けましょう。
出た数字が上場投資信託・不動産投資信託の評価額となります。
2-4. 投資信託の種類を確認する方法
相続で投資信託を引き継いだものの、種類がわからないとお困りの方も多いでしょう。
投資に関する知識を持っていなければ、相続した投資信託の種類を判断できません。
評価額の算出も難しくなるため、種類を判断する方法を確認しておくことが大切です。
まずは、相続した投資信託の決算のタイミングを確認しましょう。
毎日決算が行われていて収益を得ている場合は、MRF・外資健MMFが該当します。
毎日決算が行われていない場合は、投資信託が株式市場で上場しているかを確認してみてください。
上場している場合は上場投資信託、上場していない場合は一般の投資信託です。
ここを見ても種類を判断できない場合は、相続する投資信託を運用する金融機関に問い合わせてみましょう。
3. 投資信託を相続する際の流れ

投資信託の受益権を相続することになったけれど、どうやって手続きをすればいいかわからないとお困りの方も多いでしょう。
ここでは、手続き開始前に押さえておきたい相続の流れを解説します。
3-1. 証券会社への連絡
投資信託を行っていた人が亡くなったら、まずは証券会社や信託銀行に連絡しましょう。
投資者が亡くなったことを伝えると、証券口座は凍結されます。
凍結手続きとともに、残高証明書の発行を依頼しましょう。
残高証明書の発行依頼をする際、投資者との関係がわかる書類の提出が求められるケースもあります。
連絡したときに必要な書類を説明されるので、早めに用意することがおすすめです。
3-2. 必要書類の提出
残高証明書を取得した後は、相続手続きに必要な書類を準備しましょう。
遺言書があるケース・遺産分割協議を終えたケース・相続人の代表を決めたうえで手続きを行うケース別に用意する書類が異なります。
必要な書類は以下の通りです。
ケース別に必要な書類
|
ケース |
書類 |
|
遺言書があるケース |
・遺言書 ・遺言執行者の印鑑証明書 ・相続手続きの依頼書 ・投資者が死亡したことを確認できる書類 |
|
遺産分割協議を終えたケース |
・遺産分割協議書 ・法定相続人全員の印鑑証明書 ・相続人全員の戸籍を確認できる書類 ・投資者の出生~死亡までを確認できる書類 ・相続手続き依頼書 |
|
相続人の代表を決めたうえで手続きを行うケース |
・法定相続人全員の印鑑証明書 ・相続人全員の戸籍を確認できる書類 ・投資者の出生~死亡までを確認できる書類 ・相続人代表者の選任委任状 ・相続手続き依頼書 |
人によって状況が異なるので、該当するケースに必要な書類を準備しておきましょう。
3-3. 遺産分割協議
遺言書がない、または相続人全員で話し合っていない場合は、遺産分割協議を行いましょう。
遺産分割協議では、亡くなった人が所有する財産をどのように分配するかを話し合います。
そのため、協議までに相続できる財産すべてを調査しておかなければなりません。
協議によって決まった内容は、書面に残しておくことも大切です。
書面に残すことで後々のトラブルを防げるため、スムーズに相続分の手続きを進められるでしょう。
3-4. 必要書類を用意して金融機関に口座開設申請を行う
遺産分割協議が終了したら、亡くなった人が利用していた金融機関に自身の口座を開設しましょう。
亡くなった人が所有する投資信託の口座は、解約できません。
そのため、相続する人が新たに口座を解説し、そちらに投資信託を移す手続きを行う必要があります。
口座に投資信託を移した後は、投資信託を続行する・解約して現金化するのどちらでも構いません。
相続した人が自由に選べます。
4. 投資信託を相続する時の注意点

投資信託の受益権を相続する際に注意しておきたいポイントがあります。
- 価格変動によるリスク(休日にも注意)
- 売却益への税負担
- 解約違約金の可能性
- 信託財産留保額の確認
- 受け取っていない分配金の計上漏れに注意
どのような点に気を付けるべきか、みていきましょう。
4-1. 価格変動によるリスク(休日にも注意)
投資信託の受益権相続時と実際の受け取りの際に価格が変わっている可能性があります。
協議のときは1,000万円の価値があったものの、実際に相続する際に500万円に値下がる可能性も。
反対に、価値が値上がればほかの相続人から不満が出る恐れもあると考えておきましょう。
また、価格変動によるリスクを抑えるために早めに受け取る場合でも、休日がある際は注意が必要です。
休日の間に価格が変動し、相続時に値が上がったり下がったりする可能性があるので、休日を避けて早めに手続きを行いましょう。
4-2. 売却益への税負担
投資信託の受益権を売却する場合、取得時の費用と売却額の差額に税金が課せられます。
所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%の計20.315%の所得税を支払わなければならないので、売却金のすべてを受け取れるわけではないと考えておきましょう。
4-3. 解約違約金の可能性
投資者の証券口座を解約する際に、違約金を請求される恐れがあります。
死亡による解約なので、必ずしも違約金が請求されるわけではありません。
しかし、なかには違約金が発生する証券会社・投資銀行もあるため、連絡をする際に確認しておきましょう。
4-4. 信託財産留保額の確認
解約時にペナルティが発生する可能性にも注意が必要です。
信託財産留保額とは、投資信託解約時に支払うペナルティを指します。
投資信託解約におけるペナルティは、0~0.3%の間で設定されていることが多くなっています。
証券会社によって設定が異なるため、こちらも死亡の連絡をする際に聞いておきましょう。
4-5. 受け取っていない分配金の計上漏れに注意
投資信託の評価額を計算する際は、まだ配られていない分配金の計上漏れに注意しましょう。
投資信託は、種類によって収益を得るタイミングが異なります。
収益が手元に入るのは、決算から数日後になるため、決算直後に相続が発生すると、受け取っていない分配金の計上漏れが起こるかもしれません。
評価額を計算する際に受け取っていない分配金があるかを確認しておきましょう。
受け取っていない分は、未収分配金として計上してください。
5. 投資信託の評価方法に迷ったら税理士に相談しよう!
投資信託は運用によって得た利益を受け取れるため、受益権も相続税の対象になります。
相続する際は税金の計算に含める必要があるので、まずは評価額を計算してみましょう。
計算する際は残高証明書をもらう必要があるため、証券会社や投資銀行に連絡することも大切です。
投資信託の評価額の計算は種類別に異なります。
いずれもさまざまな情報が必要になるため、個人では計算が難しいと感じる場面もあるでしょう。
評価額の計算は税理士にお任せできるため、不安な方は税理士に相談してみることがおすすめです。

監修
中村亨
日本クレアス税理士法人 代表
税理士
公認会計士
2002年8月に会計事務所として創業、2005年には税理士事務所を開業し、法人や個人のお客様の会計・税務の支援をする中で、「人事労務の問題を相談をしたい」「事業承継を検討している」といったお客様のニーズに応える形でサービスを拡大し続け、現在では社会保険労務士法人など複数の法人からなるグループ企業に成長してきました。お客様に必要なサービスをワンストップで提供できることが当社の強みです。