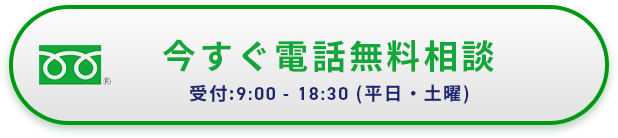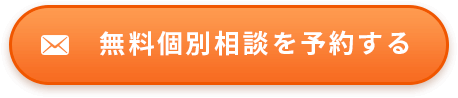家族間の借金に借用書は必要?正しい書き方と贈与扱いを防ぐコツ
両親や祖父母からお金を借りることになったけれど、借用書は必要なの?と気になっていませんか。
家族間であれば文書の必要性は感じない方も多いでしょう。
しかし、税務署からの調査によって贈与と判断される恐れがあることから、親子であっても借用書の作成がおすすめです。
この記事では、親子や身内の借金に借用書が必要な理由を解説します。
書面の作り方や知っておきたい金利の決め方、贈与とみなされないコツも紹介するので、家族からお金を借りる予定がある方は参考にしてください。
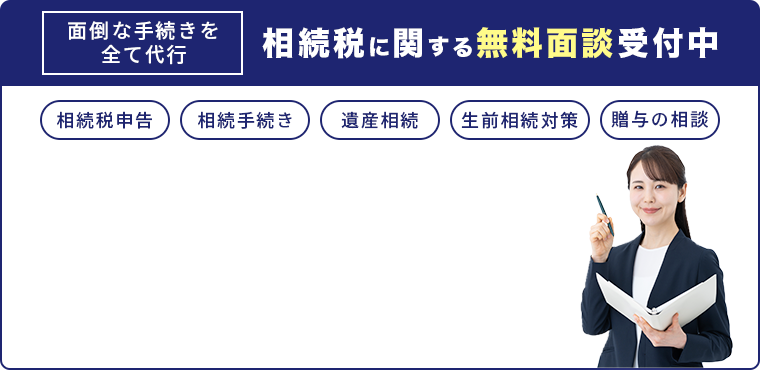
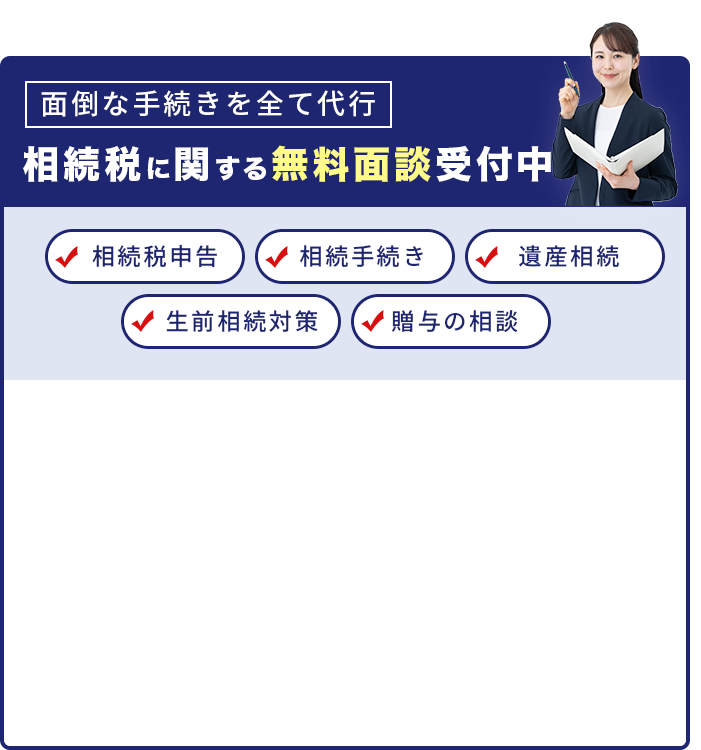
目次
1. 家族間での金銭の貸し借りに借用書は必要?
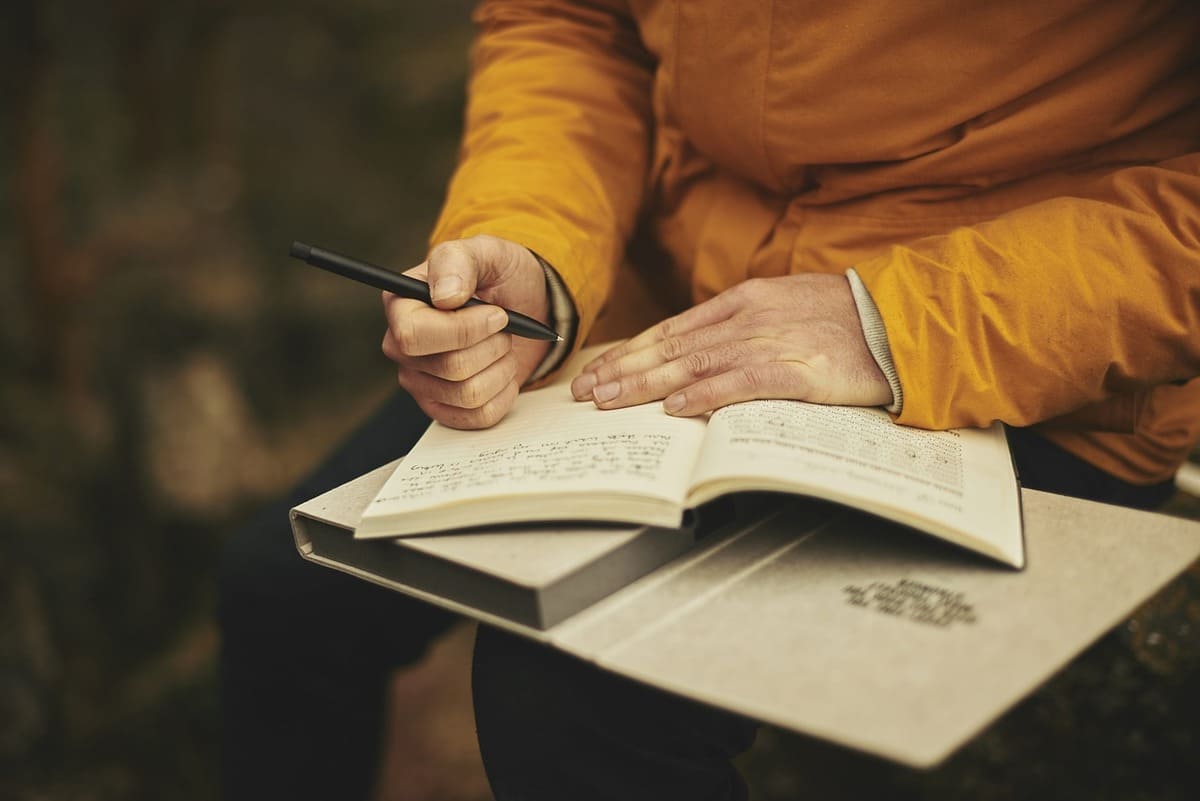
両親、または祖父母からお金を借り入れる際、借用書を作成しないという方も多いでしょう。
友人や知人であれば作成の必要性を感じるものの、家族なら必要ないのでは?と考えるかと思います。
ここでは、親子間での借金に借用書が必要な理由を解説します。
1-1. 借用書は返済の意思を証明するために必須
誰かからお金を借りる際は、相手が誰であっても借用書を作成することがおすすめです。
借用書は、借りたお金を返す意思があると証明できる書類です。
もらったものではなく、返済する意思があると証明することで、贈与の疑いをかけられずに済みます。
1-2. 借用書なしでお金を借りると贈与扱いされる
文書を作成せずに借金すると、税務署の調査が入った際に贈与を疑われる恐れがあります。
親子間の借金のなかには、数十万、数百万円を借りるケースも少なくありません。
大きな単位のお金が親子間の口座で動いていた場合、調査が入るかもしれません。
調査が入ったとき、借用書があれば返済の意思があると証明できます。
しかし、書面がなければ返済の意思を証明できないので、贈与と判断されてしまうのです。
贈与とみなされれば贈与税がかかるため、余分な出費が増えてしまいます。
2. 家族間の金銭の貸し借りで作成する借用書の作り方

親子同士の借金でも書面が必要な理由はわかったけれど、書類の作り方がわからないとお困りの方も多いでしょう。
ここでは、借用書の作り方をくわしく解説します。
2-1. 家族間の借用書に記載する項目
書面作成する際は、以下の項目を記載しましょう。
|
項目 |
内容 |
|
表題 |
借用書と記載する。借用証書や念書でもOK |
|
お金を貸す人の名前 |
お金を貸す人の名前を記載する |
|
借りる金額と日時 |
借りる金額とお金を借りた日を明確に記載する |
|
返済期日と返済方法 |
元金を返済する期日を書く。返済方法は手渡しや振り込みなど、希望する方法でOK |
|
利息 |
利息制限法を参考に決める |
|
返済が遅れた場合の遅延損害金 |
返済が遅れた場合のペナルティを書く。ペナルティの上限も利息制限法を参考にする |
|
借用書を作成した日 |
書面を作成した日時を記載する |
|
お金を借りる人の氏名と住所 |
お金を借りる人の氏名と住所を書く |
書面には、上記の項目を記載しましょう。
いずれもあげたものではなく、貸したものと証明するために必要な項目なので、漏れのないよう書くことが大切です。
2-2. 家族間の借用書を作る際の注意点
書面を作成する際は、以下の点に注意が必要です。
- 漢数字は壱・弐で書く
- 返済期日を確実に記載する
- 親子間であっても利息は必要
- 返済方法をくわしく書く
- 借入額によっては収入印紙が必要
借り入れ金額を記載するときは一・二ではなく、壱・弐を使いましょう。
難しい方の漢字を使うのは、書類の改ざんを防ぐためです。
一や二は、線を足せば簡単に別の漢数字に変えられます。
親子の間で改ざんする恐れはないものの、念のため難しい漢字を使うことがおすすめです。
返済期日は借金であることを証明する重要な要素なので、忘れずに記載しましょう。
返済期日のない書面は、いつまでに返せばいいかが明確ではないため、贈与を疑われる原因となります。
また、身内からの借り入れであっても、利息を設けることも重要です。
金利を設定することで、借金であることを明確にできます。
無理に金利を設定する必要はありませんが、税務署から疑われたくない方は、利息と遅延損害金の設定を忘れずに行いましょう。
返済方法をくわしく書くことも大切です。
銀行に振り込む場合は銀行名や口座番号などの必要な情報を書いておきましょう。
親子であれば手渡しでもいいのですが、記録の残る方法を選べば、お金を返済していることを証明できます。
借りる金額によっては収入印紙が必要になる点にも注意が必要です。
借り入れ金額が1万円を超える場合、金額に応じて収入印紙を貼らなければなりません。
収入印紙は郵便局やコンビニで購入できるので、1万円以上を借りる際は事前に用意しておきましょう。
2-3. 借用書の作成が難しい場合はテンプレートを活用
借用書の作成が難しい場合は、テンプレートの利用がおすすめです。
インターネットで検索すれば、さまざまなテンプレートがヒットします。
先ほど紹介した記載すべき項目がすべて盛り込まれているひな形を探し、活用しましょう。
ファイルによって記載されている項目が異なるため、ダウンロード後は自身で編集しなければなりません。
編集によって効力が失われるのでは?と不安な方は、税理士に相談することがおすすめです。
税理士が書類をチェックしたうえで、有効な書面を作成してくれます。
3. 借り入れ金額や利息に注意!ケース別のデメリット

家族間の借金には、さまざまなケースが存在します。
利息なしでお金を貸している、または返済期日を過ぎてもお金が振り込まれないなど、親しい間柄だからこそ、いくつもの問題が生じるでしょう。
ここでは、お金の借り入れの注意点をケース別に解説します。
3-1. 利息なしで元金のみを返済しているケース
利息なしで借りた元金のみが返済されていると、本来の利息分を贈与したとみなされます。
前述したように、親子であっても金利の設定が大切です。設定することで、親子間の借金であると明確に証明できるからです。
しかし、子どもや孫にお金を貸すのに利息を付けたくないと考える方も多いでしょう。
両親や祖父母の思いから、利息なしでお金を貸すケースも少なくありません。
貸す側と借りる側が利息なしでの借金を了承していても、税務署は利息分が贈与されていると判断します。
その結果、利息分に対して贈与税が発生するため、借りる側は余分な出費を強いられることになります。
3-2. 元金の返済もされていないケース
両親や祖父母への借金であることから、元金の返済が滞るケースも珍しくありません。
借りてから一度も返済していない、または返済期日をどんどん先延ばしにするなどのことが見られると、贈与と判断される恐れがあります。
親子間で大きなお金が動いたにもかかわらず、その後返済の動きが見られなければ税務署が調査に入ります。
返済期日を過ぎている場合は、借用書があっても借金であることを証明しにくくなるでしょう。
その結果、貸したお金全額が贈与と判断され、借りた側は金額に応じた税金の支払いを命じられます。
3-3. 金額が大きく完済が難しいケース
借りる人の収入に対し、高額の貸し付けが行われると、贈与を前提としていると判断されます。
事業を始める資金や住宅を購入する資金など、高額のお金が必要になるケースもあるでしょう。
その際に、親が子どもに高額のお金を渡すと、あげることを前提にしているとみなされる恐れがあります。
たとえば、年収350万円の子どもに対し、親が事業資金として5,000万円を貸したとします。
書面を作っていたとしても、年収を見る限りでは返済が困難であることを容易に推測できるため、借金だと証明できません。
高額の貸し付けが贈与と判断されると、多額の税金を納める必要があります。
お金を貸す際は、子どもの年収に応じて金額を設定することが大切です。
4. 贈与とみなされずに家族間で金銭の貸し借りを行うポイント

借用書を作っても、贈与を疑われて税務署から調査が入るのでは?と不安を覚える方も多いでしょう。
ここでは、疑われずにお金を借り入れる行うポイントを解説します。
4-1 .お金を借りていることを証明する書類(借用書)を作成する
贈与ではなく、お金の借り入れを証明する書類の作成が大切です。
借用書は、借りた人がお金を返す意思があると証明する書類です。
書面がなければ即座に贈与と判断される恐れもあるため、返済期日や返済方法をくわしく記載しておきましょう。
ただし、借りるお金が小額で翌月には全額返せる場合には、借用書を作る必要はありません。
書面を用意すべきなのは、すぐに返せないほどの高額のお金を借りる場合です。
借りる人の年収によってすぐに返せるかどうかが変わるため、必要に応じて作成するものと考えておきましょう。
4-2. 記録の残る振込で返済する
返済方法には、記録の残る方法を選択することがおすすめです。
家族であれば、現金の手渡しで返済していくケースも多いでしょう。
しかし、手渡しだとお金を返したという証拠が残らないので、後々贈与を疑われるかもしれません。
銀行振り込みや電子マネーでの返済など、記録に残る方法で返していけば、贈与を疑われずに済みます。
親の口座に返済金額を振り込む、または電子マネーで親に返済していくなど、子どもが親にお金を返している証拠が残る方法を選びましょう。
4-3. 家族間でも利息を払う
税務署から疑われたくない、または贈与税を払いたくないと考える方は、身内同士の借金でも利息を設定することが大切です。
金利設定なしでお金を貸す場合、利息分が贈与とみなされる恐れがあります。
税務署が贈与と判断すれば、利息にかかる税金の支払いを求められるかもしれません。
小額の貸し付けであれば、利息分は贈与の基礎控除内に収まるでしょう。
ただし、高額の貸し付けを行う場合は、金額に伴って利息も大きくなるため、基礎控除の範囲を超える恐れがあります。
たとえば、親が子どもに1,000万円を貸す場合に利息を設定しなかったとしましょう。
法律における100万円以上の貸し付けへの上限金利は15%なので、1,000万円への利息は150万円となります。
基礎控除は110万円なので、150万円-110万円=40万円に贈与税がかかります。
金額によっては納税を求められるので、家族の借金であっても、利息を決めておくことがおすすめです。
家族同士の借金における利息の決め方については、次でくわしく解説します。
5. 家族間での利息の決め方

親子同士でお金を借り入れする際、金利を設定しない方も多いでしょう。
利息分が課税対象になっても、小額であれば贈与の基礎控除の範囲内に収まります。
そのため、万が一調査が入っても、納税せずに済みます。
ここでは、身内での利息の決め方を解説します。
5-1. 利息制限法を参考に金利を決める
家族で利息を設定するときは、法律を参考にしましょう。
利息制限法とは、お金を貸し付ける際に設定する金利の上限を定める法律です。
利息制限法では、金額別に上限金利を以下のように定めています。
- 10万円未満:年20%
- 10万円以上100万円未満:年18%
- 100万円以上:年15%
消費者金融や銀行は、利息制限法を元に金利を設定しています。
貸す金額に応じて、上限までの金利を定めるといいでしょう。
上記の数字は上限なので、必ずしも上限の数字を設定する必要はありません。
特に、親子であれば利息をできるだけ抑えたいと考えるため、上限までの範囲で、借りる側に無理のない利息を設定してください。
5-2. 上限を超える金利での借り入れは無効になる
利息制限法で定められている金利の上限を超えると、貸し付けそのものが無効となります。
たとえば、親が子どもに30万円を貸し付け、金利を20%に設定したとしましょう。
30万円の貸し付けの上限金利は年18%なので、貸し付けは無効です。
親子間であれば無効で済むものの、消費者金融や銀行が上限を超過した金利を設定すると、出資法違反として刑罰の対象になります。
貸し付けの際に違法金利だと気づかなくても、税務署からの調査の際に違法だと発覚するため、上限金利内の利息を設定することが大切です。
6.家族間で作成する借用書に寄せられる質問

家族間の借り入れで借用書を作成するつもりだけど、いくつかわからない点があるとお困りの方も多いでしょう。
ここでは、家族間で作成する借用書によく寄せられる質問を紹介します。
6-1. 家族間の借用書に収入印紙は必要?
親子同士で作成する借用書であっても、借り入れ金額によっては収入印紙が必要です。
親子間でやり取りする書類なら、簡略化した書面で収入印紙も必要ないのでは?と考える方も多いでしょう。
しかし、必要事項が書かれていない・借り入れ金額や返済方法が不明瞭・収入印紙がないなどの不備がいくつもあると、法的な効力を失う恐れがあります。
税務署の調査の際に効力のない書面を見せても、金銭の貸し借りであると認められないかもしれません。
6-2. 家族間であれば現金手渡しで返済してもいい?
家族間の借金でも、現金手渡しで返済することは避けましょう。
たとえば、親が子どもにお金を貸すために、子どもの口座に10万円を振り込んだとします。
翌々月、子どもが親に10万円を手渡しで返済した場合、後々の税務調査で贈与を疑われるかもしれません。
これは、親から子どもに10万円への振り込みがあったものの、その後、子どもから親に10万円が振り込まれていないためです。
手渡しだと返済した証拠が残らないので、親が子どもにお金をあげたと判断されます。
現金手渡しは手軽な方法ではあるものの、証拠が残らないのでよい方法だとはいえません。
返済するときは、記録が残る銀行振り込みを行いましょう。
6-3. 家族間の借書は手書きで作成してもいい?
家族間の借用書は、手書きで作成してもかまいません。
パソコン操作が苦手な方は、手書きで必要事項を記載し、書面を作成しましょう。
書面を作るときは、鉛筆やシャーペンなどの消せる文房具を使わないことが重要です。
消せる文房具で書面を作ると、内容を改ざんされる恐れがあるので注意しましょう。
ボールペンや万年筆であれば消すことはできないので、作成時に活用してください。
7.家族間の借用書についての疑問は税理士に相談しよう!

両親や祖父母からお金を借りる際は、念のため借用書を用意しておきましょう。
借用書を作成していないと、税務署から調査が入った際に贈与を疑われます。
突然調査が入る可能性もあるため、疑いをなくすためにも、借用書を用意しておきましょう。
借用書は、借りる人が返済する意思があることを証明する大切な書面です。
自身で作成することもできるため、金銭の貸し借りを行う際は必ず作成しましょう。
借用書の作成で不安な点がある方は、税理士に相談してみてください。
疑問点を解決し、借り入れにおける適切なアドバイスをもらえます。