小規模宅地等の特例とは、亡くなった方が所有していた土地のうち、住んでいた土地や事業をしていた土地について相続するときに、一定の要件を満たすものの相続税評価額の最大80%が安くなるという制度です。
小規模宅地等の特例制度をよく理解して、相続対策のときに上手に制度を利用することができれば、相続税を節税することができます。詳しく見ていきましょう。
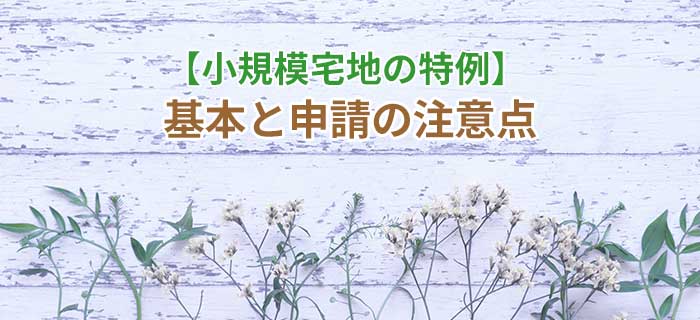
1.小規模宅地等の特例が出来た背景
一般的な家庭を考えると、相続における財産の中で「自宅」の割合はとても高くなります。そのような状況で自宅を相続するにあたって、相続税を支払うために自宅を売却せざるを得ないというのでは、住む場所を失う人がたくさん出てしまいます。
そこで「自宅を相続税によって手放さない」ために、「自宅にかけられる相続税を低くする」ことが求められ、小規模宅地等の特例ができました。
2.小規模宅地等の特例が適用されるための要件
小規模宅地等の特例が適用されるためには、要件にあてはまっているかどうかが大切です。
「要件1」にあてはまっているものにについて、さらに宅地の種類ごとに「要件2」にあてはまっているかどうかを考えます。
要件1:土地の要件
①亡くなった方(被相続人)か、亡くなった方と生計一である親族が住んでいた土地か、事業をしていた土地であること。
※生計一である親族かどうかについては、立場によって定義が異なってきます。
- 配偶者
別居状態であっても、婚姻期間が短期間であっても、配偶者は小規模宅地等の特例を受けることができます。 - 高校生などの子供
子供が親の自宅を相続する場合、子供が親と同居している場合(生計をともにしている場合)は、小規模宅地等の特例を受けることができます。高校生や大学生など仕送りを受けて別の場所で暮らしている場合も、生計を共にしているとみられますので、小規模宅地等の特例を受けることができます。 - 成人後の子供
結婚等で親と別の場所で所帯をもって暮らしている場合や仕事の関係で、通勤に便利な場所にマンションを借りていて親と一緒に住んでいない場合は、同一の家計とは見なされないため、特例の対象になりません。
②その土地の上に建物又は構築物があること
以上の「要件1」にあてはまっているものについて、さらに以下の「要件2」にあてはまっていることが必要です。
要件2:宅地の種類の要件
さらに小規模宅地等の特例は、宅地の種類ごとに要件があります
①特定事業用宅地等
亡くなった方(被相続人)の名義で事業をしていた場合で、貸付事業は含みません。
この貸付事業以外の事業をしていた土地は、被相続人の事業を相続税の申告期限までに引き継いで継続し、その土地を保有していることが必要です。
②特定居住用宅地等
亡くなった方(被相続人)の自宅がある場合です。
- (イ)被相続人の配偶者
- (ロ)被相続人と同居していた親族
- (ハ)被相続人と同居していなかった親族
被相続人の配偶者か、被相続人の生計一親族が相続した場合のみ、特例の適用があります。ただし、生計一家族については、相続税の申告期限まで引き続きその家に住んでいて、その土地を相続税の申告期限まで保有していることが必要です。
③特定同族会社事業用宅地等
貸付事業を除く、被相続人や被相続人の親族が株式や持分の50%を超えて所有している法人です。
この場合には、その土地を相続した親族が、相続税の相続税の申告期限に、その法人の役員であることなどの要件があります。
④貸付事業用宅地等
アパートやマンションなどの賃貸事業のほかに、駐車場などにも適用されます。
被相続人等が貸付事業をしていた土地には、その貸付事業を相続税の申告期限までに引き継いていで、貸付事業を申告期限までに継続していることなどの要件があります。
※複雑な小規模宅地の特例については、シリーズで解説をしています。適用要件の詳細など、それぞれの記事も合わせてご参照ください。
【適用条件】小規模宅地等の特例とは?適用条件をわかりやすく解説
【宅地の種類】小規模宅地等の特例が適用される土地・宅地の種類と適用要件
小規模宅地等の特例は、宅地の種類ごとに要件が異なってくるため、特例を活用するには要件の判断や計算が複雑になってくるケースが非常に多いです。特例の活用を検討されている場合は、一度、相続税に詳しい税理士などの専門家に相談してみるとよいでしょう。
続いては小規模宅地等の特例を使うにあたって満たしておく条件と注意点について解説していきます。
3.小規模宅地等の適用には相続税申告が必要
小規模宅地等の特例を使うための条件として、遺産分割を申告期限までに確定させ、相続税の申告を行う必要があります。
相続税が控除された結果、相続税が0円となった場合でも、小規模宅地等の特例を活用するには相続税申告書の提出が条件となっているため、税務署への相続税申告が必要となります。
申告の期限は通常の相続税の申告と同じく、相続が発生(被相続人の死亡)してから10ヶ月以内です。
また、小規模宅地等の特例を適用する宅地の区分によって、保有や居住の有無、事業の継続等に関する条件が細かく決まっています。
4.まとめ
小規模宅地等の特例は、適用が認められれば相続税が大きく減額されます。
小規模宅地等の特例は、相続税評価額が最大80%まで安くなる制度で、多くの方が財産として所有している「自宅」にも適用される特例ですので、検討する方も多いでしょう特例が実際に適用できるかどうかについては、実際のケースごとに判断していくしかないので、相続税に強い信頼できる税理士に相談し、相続対策をしていくことをおすすめいたします。
【お役立ちコンテンツ】
相続相談はどこにするべき?専門家(税理士、司法書士、弁護士)の強み
【クレアスの相続税サービス】
