名寄帳とは所有不動産の一覧表!取得方法から必要書類・見方まで解説!
家族が亡くなり、遺産相続を話し合うときに、初めて名寄帳(なよせちょう)を知ったという方も多いでしょう。
名寄帳は、土地・建物の名義やその他の情報をエリアごとにまとめた帳簿です。
特に、相続や税金に関わる場面で必要になります。
本記事では、名寄帳とは何か、どのような場面で必要になるのかを分かりやすく解説します。
交付の手続きや活用方法なども紹介するため、将来の備えや相続対策として、ぜひ最後までご覧ください。
目次
1. 名寄帳とは:被相続人所有の不動産が一覧でわかる

名寄帳とは、行政機関が作成した、土地・建物に関する情報を1つにまとめた資料です。
名寄帳には、以下の情報が記録されています。
- 所持者
- 土地・建物がある場所(住所)
- 不動産の種類(土地か建物か)
- 土地・建物にかかる税金額
亡くなった人がどこに、どのような土地や建物を持っていたのかをまとめて、知ることができます。
2. 名寄帳はどんな相続のときに必要?

名寄帳は、亡くなった人が持っていた土地や建物を、正確に把握したいときに必要です。
たとえば、明らかに持っている不動産が1つしか無い場合は問題ありませんが、
- 故人が土地や建物を複数持っていた
- 故人が他の方との共有不動産を持っていた
- 故人が税金がかからない土地・建物を持っていた
などの場合には、遺産分割や相続税の申告が難しくなります。
それぞれの場合で、名寄帳が必要となる理由を1つずつ解説します。
2-1. 被相続人が不動産を複数所有していた
被相続人がいくつもの土地や建物を持っているときは、名寄帳がとても重要な資料になります。
複数の不動産を持っている場合、土地だけでなく建物など種類の異なる不動産を持っているケースも少なくありません。
名寄帳は、それらの土地・建物の情報を1つにまとめて確認できます。
情報の把握漏れを防ぎ、相続手続きを正確に進められます。
2-2. 被相続人が共有名義で不動産を所有していた
ほかの人と一緒に土地・建物を所有することを「共有名義」といいます。
共有名義の不動産は、代表者にしか固定資産税の「課税明細書」が送付されません。
そのため、被相続人が代表者でなかった場合は、書類が送付されず不動産が把握できないこともあります。
しかし、名寄帳には、共有名義の不動産も掲載され、どれくらいの割合で持っていたかも分かります。
2-3. 被相続人が固定資産税非課税の不動産を所有していた
税金がかからない不動産も、名寄帳には情報が載っています。
持っている土地が公共の道路に面している、公共の保有林などの場合は、税金がかからないため固定資産税の通知書に載っていません。
そのため、土地・建物を把握できないこともあります。
名寄帳には、税金がかからない土地・建物の情報も載っているので、抜け漏れなく把握できます。
3. 名寄帳の取得方法

名寄帳を発行する際には、以下の項目を確認しましょう。
- 発行できる人
- 必要な書類
- 閲覧・発行できる場所
- 発行料
1つずつ解説します。
3-1. 名寄帳を請求できる人
名寄帳は、その土地・建物に関係している人だけが請求できます。
たとえば、不動産の持ち主本人や、その人が亡くなった場合の相続人・相続人の代理人などが対象です。
名寄帳は、誰でも閲覧・発行できる訳ではないことを知っておきましょう。
3-2. 名寄帳の取得に必要な書類
名寄帳の発行を依頼するときは、以下を準備しましょう。
- 本人が確認できる資料(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 相続関係を証明する資料(戸籍謄本想定相続一覧図など)
- 申請書
- 委任状(※代理人の場合)
参考:「東京都主税局」
交付を依頼する人や、交付する市区町村によって必要な書類は異なります。
事前に役場のホームぺージを確認しましょう。
3-3. 名寄帳を閲覧・取得できる場所
名寄帳は、土地や建物がある自治体の行政機関でしか閲覧・発行できません。
不動産を複数持っている場合は、それぞれの行政機関で発行依頼をしましょう。
役所によっては、窓口や郵送、オンラインでの手続きが可能です。
居住地以外で不動産を持っている場合は、郵送やオンラインでの交付も検討しましょう。
3-4. 名寄帳の発行料
名寄帳を取り寄せるときには、発行料がかかります。
一部自治体の発行料は以下のとおりです。
- 東京都:300円
- 大阪市:300円
- 名古屋市:300円
自治体によって名寄帳の発行料は異なるため、市区町村役場のホームぺージなどで確認しておきましょう。
4. 名寄帳を取得・確認するときに注意すべき4つのこと
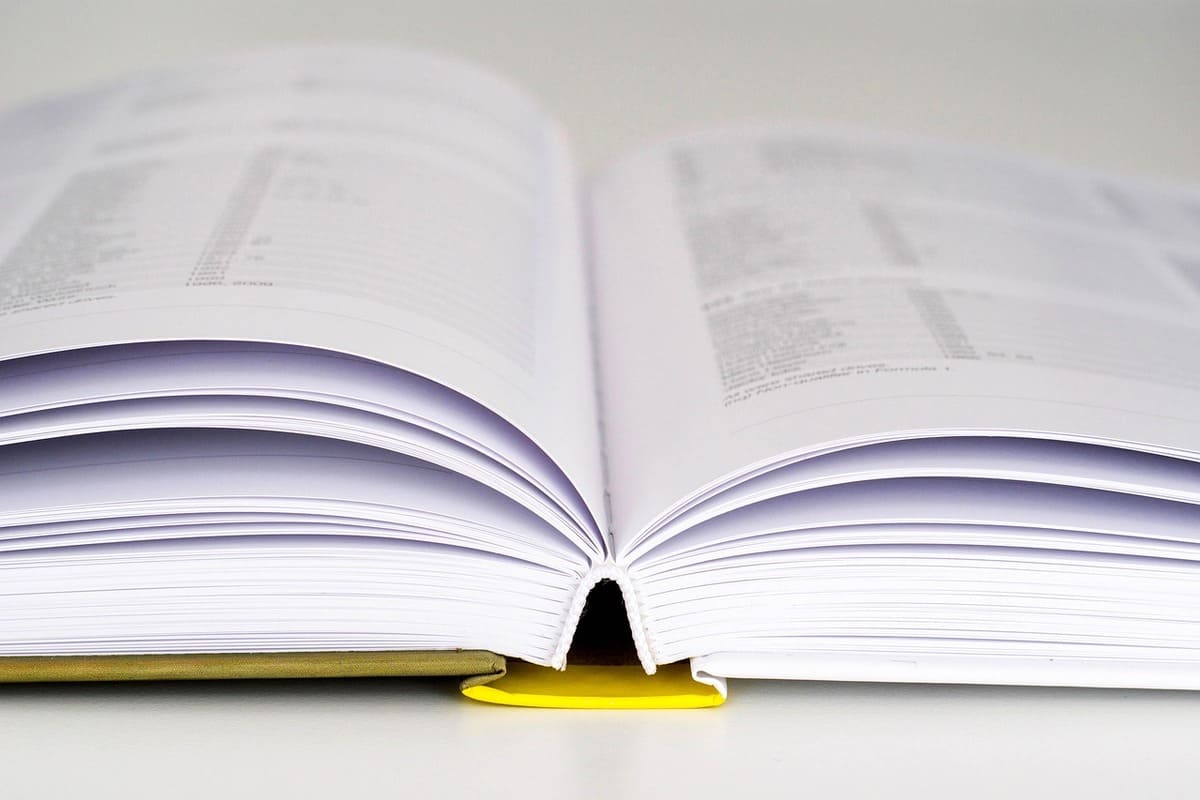
名寄帳を発行し、内容を確認するときには、いくつか注意すべきポイントがあります。
ポイントを確認しておくと、抜け漏れなく必要な資料を準備できます。
スムーズな相続手続きを行うために、ポイントを1つずつ解説します。
4-1. 不動産所在地の自治体ごとに取得しなければならない
名寄帳は、土地・建物がある場所を管轄している自治体でしか発行できません。
そのため、不動産を複数持っている場合は、土地・建物がある自治体で発行依頼を行います。
別の自治体では発行ができないので、注意しましょう。
4-2. 名寄帳にはその年の1月1日時点の情報しか載っていない
名寄帳は、毎年1月1日時点での内容のみしか載っていません。
たとえば、それ以降に土地・建物を売買しても、その情報は翌年の1月1日まで反映されません。
最新の情報を知りたい場合は、登記簿謄本や契約書など別の方法で確認しましょう。
4-3. 個人名義の不動産のみで法人名義で所有しているとわからない
名寄帳には、個人の名義で持っている不動産情報しか載っていません。
被相続人が法人を経営しており、法人で土地・建物を購入した場合は、名寄帳にその不動産は載っていません。
会社で持っている土地・不動産を知りたい場合、法人名で名寄帳を取り寄せる必要があります。
個人の場合とは別の手続きになるため注意しましょう。
4-4. 名寄帳を発行していない自治体もある
名寄帳は、すべての市区町村で発行できるわけではありません。
いくつかの自治体では名寄帳を発行していない場合があります。
その場合は「固定資産評価証明書」など、別の方法で土地や建物の情報を確認しましょう。
5. 名寄帳の見方・見るべきポイント

名寄帳を取り寄せたら、以下3つのポイントを確認しましょう。
- 誰の不動産か:土地・建物所有者
- どこにあるか:土地・建物の所在地、土地の広さ
- 価値や税金の情報:不動産の評価額や固定資産税
3つのポイントを確認することで、名寄帳を使って正確に相続手続きや対応ができるようになります。
6. 複数の不動産が絡む相続の場合には名寄帳を取得しよう!
名寄帳は、被相続人が持っていた土地・建物を知るための欠かせない資料です。
特に複数の土地や建物を持っていた場合には、名寄帳ですべてを把握できるため、抜け漏れなく相続手続きができます。
名寄帳を取り寄せるには書類の準備や申請がありますが、役場窓口や郵送で比較的簡単に入手できます。
早めに確認し、相続時の思わぬトラブルを防ぎましょう。


