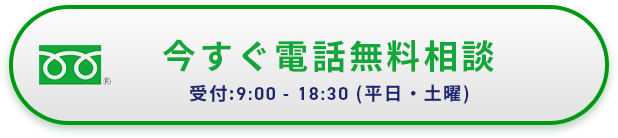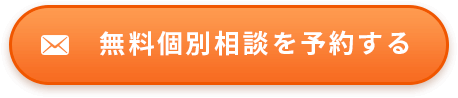贈与税額の早見表 ~ 初心者でもひと目でわかる!【保存版】

監修
中村亨
日本クレアス税理士法人 代表 税理士 公認会計士
贈与税の税率や計算方法は難しく見えますが、基本を押さえれば意外とシンプルです。
特に「110万円を超える贈与があった場合にいくら税金がかかるのか?」という疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。
平成27年(2015年)1月1日の改正で、贈与税の税率構造が見直されました。
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与により受けた財産について、以下のケースに該当する場合には申告が必要です。
- 暦年課税を適用する場合で、財産の合計額が基礎控除額の110万円を超えるとき
- 相続時精算課税を適用するとき
本章では、「暦年課税」を適用する場合の贈与税額についてご紹介いたします。
なお、実際に保有している財産の価格から大まかな贈与税額を知りたい場合には、こちらのコラムをお勧めします。「納税額はいくら?財産価格別の贈与税額シミュレーション【保存版】(2021.9.28更新)」200万円~1億円まで、合計9パターンの価格レンジで贈与税のシミュレーションを行っています。
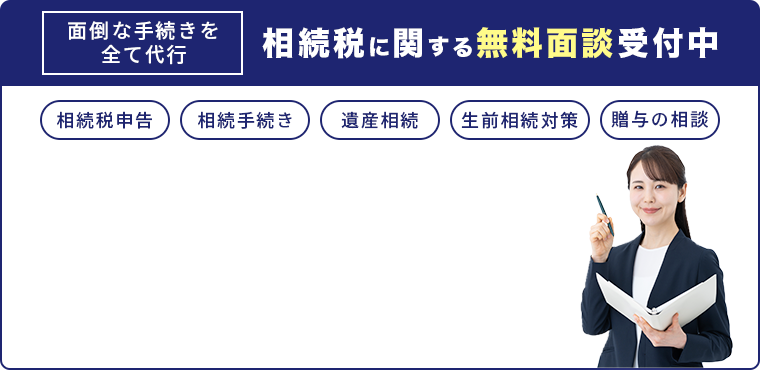
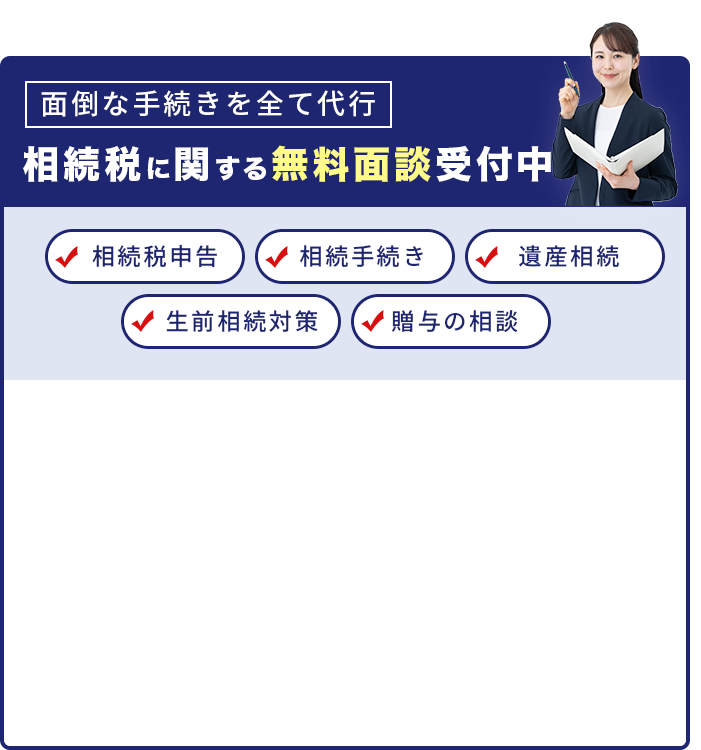
目次
1.贈与税の課税方式
贈与税には、財産を受け取った際に適用できる2つの課税方式があります。それが「暦年課税」と「相続時精算課税」です。
「暦年課税」を適用した場合の贈与税の課税方法は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産を合計し、その合計額から基礎控除額の110万円を差し引きます。
その後、残りの金額に税率をかけ、税額を計算します。贈与のたびに毎年課税される仕組みなので、110万円以下であれば申告も税金も不要です。
複数年に分けて少しずつ贈与する場合などにも活用できます。
「相続時精算課税制度」は原則として親や祖父母(60歳以上)から、18歳以上の子や孫への贈与が対象となる制度です。
特徴は、贈与を受けた時点では、2,500万円までは贈与税がかからない点にあります。
ただし、次の点に注意が必要です。
- 贈与額が 2,500万円を超えた部分には一律20%の税率がかかる
- 将来、贈与者が亡くなった際には、贈与された金額も相続財産に加算されて相続税が計算される
- 一度この制度を選ぶと、あとから暦年課税へ戻すことはできない
そのため、「とりあえず相続時精算課税制度を使っておこう」と安易に選ぶと、後で不利になることもあります。
詳しくは以下のコラムで制度のメリット・デメリットをご確認ください。
【関連記事】相続時精算課税制度のメリットとデメリットをわかりやすく解説~安易な判断をしないために
2.贈与税の計算方法
贈与税は、「いくらの財産を、誰から、誰が受け取ったか」によって税額が決まります。
暦年課税で贈与税を計算する際には、次のような流れです。
- 贈与税を計算する流れ(暦年課税の場合)
①1年間(1月1日~12月31日)で受け取った財産の合計額を出す
②110万円の基礎控除を差し引く
③残った金額を「特例贈与財産」と「一般贈与財産」に分類
④それぞれに応じた税率(特例税率・一般税率)をかけて税額を計算
⑤両者を合計した金額が、支払う贈与税額となる
- 特例贈与財産と一般贈与財産の違い
|
区分 |
対象となる贈与 |
適用税率 |
|
特例贈与財産 |
親や祖父母(直系尊属)から、18歳以上(※)の子・孫への贈与 |
特例税率(優遇される) |
|
一般贈与財産 |
上記以外の贈与(例:配偶者・兄弟・姉妹・友人など) |
一般税率 |
※2022年以降、特例贈与の受贈者年齢は「20歳以上」→「18歳以上」に引き下げられました。
- 基礎控除110万円の注意点
贈与税には、すべての受贈者に適用できる「年間110万円の非課税枠(基礎控除)」があります。
ただし、この110万円は 贈与を受けた人ごとに年1回のみ適用可能です。
つまり、「特例」と「一般」それぞれに110万円ずつ控除されるわけではなく、合計額から110万円を差し引いたうえで、「特例」「一般」に分けて税率を適用するという流れになります。
3.平成27年(2015年)1月1日改正 現行の贈与税額早見表
平成27年(2015年)1月1日の贈与税の税制改正により、贈与額が高額な場合を除いて、贈与税の負担が少なくなりました。高齢者の方の資産を次世代に移転、推進するのが狙いと言われています。
贈与税の税率が6段階から8段階に変更になり、新たに45%、55%の税率が増えました。 また、20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合(①特別贈与財産用)には、一般の贈与(②一般贈与財産用)より低い税率となります。
※相続時精算課税制度の対象とならない贈与財産についての見直しです。
①20歳以上の方が直系尊属から贈与を受けた場合の税率構造(祖父母から孫へ、両親から子へ等)【特別贈与財産用(特別税率)】
| 平成26年12月31日まで | ||
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | - |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,000万円超 | 50% | 225万円 |
| 平成27年1月1日以降(現行) | ||
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | - |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
②(20歳以上の方の直系尊属からの贈与)以外の贈与財産の税率構造【一般贈与財産用(一般税率)】
| 平成26年12月31日まで | ||
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | - |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,000万円超 | 50% | 225万円 |
| 平成27年1月1日以降(現行) | ||
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | - |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
今回の改正により、相続税と同様に贈与税も最高税率が「50%→55%」に引き上げられました。
とはいえ、課税価格が比較的低いゾーンでは税率が引き下げられ、控除額も変更されたため、結果として多くの人にとって税負担が軽減される設計です。
特に、若年層への資産移転を考えている方にとって、特例贈与税率の適用は大きなメリットと言えるでしょう。
4.贈与の具体例
具体例1 祖母から20歳以上の孫へ1,500万円の贈与
例えば、祖母から20歳以上の孫が1,500万円の贈与を受けた場合を見てみましょう。
①(直系尊属から贈与を受けた場合)の表で計算します。
| 平成26年12月31日迄 | (1,500万円 – 110万円) × 50% - 225万円 = 470万円 |
| 現行 | (1,500万円 – 110万円) × 40% - 190万円 = 366万円 |
現行の制度となったことで、104万円贈与税が減額されることになりました。
具体例2 祖父から20歳未満の孫へ5,000万円の贈与
祖父から20歳未満の孫に5,000万円を贈与する場合を見てみましょう。 孫は直系尊属ですが20歳未満の場合は、②の表で計算します。
| 平成26年12月31日迄 | (5,000万円 - 110万円)× 50% – 225万円 = 2,220万円 |
| 現行 | (5,000万円 – 110万円) × 55% – 400万円 = 2,289.5万円 |
現行の制度により、5,000万円贈与する場合は、69万5千円贈与税が増額することになりました。
このように贈与額が5千万などの高額な場合は贈与額が多くなりますが、20歳以上の子供や孫が直系尊属から贈与を受ける場合、改正後は最高税率55%を適用される一部の贈与のみを除いて贈与税が減額されます。 今後は、祖父母や両親からの贈与がしやすくなると思われます。
(2021年4月追記)贈与税の税率構造は、令和3年(2021年)税制改正では見直しは実施されておらず、以下の税率が適用されます。国税庁:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
5.贈与税の負担を軽くするには「誰に・いつ」贈与するかが重要
平成27年の税制改正によって、直系尊属である祖父母や両親から、18歳以上の子や孫への贈与は、従来よりも税負担が軽くなる傾向が強まりました。
一方で、贈与額が高額な場合や、配偶者・兄弟姉妹・20歳未満の孫などへ贈与するケースでは、かえって税率が上がり、負担が増す可能性もあります。
贈与を行う際には、受け取る人の年齢や続柄、贈与する金額の大きさを含め、どの課税方式を選ぶかまで総合的に判断することが重要です。
税制の仕組みをよく理解したうえで計画的に贈与すれば、無駄な税負担を回避することができ、資産の円滑な承継にもつながるでしょう。
ただし、贈与額が大きくなればなるほど判断が複雑になるため、制度の選び方に不安がある方は、早めに税理士に相談することをおすすめします。
【お役立ちコンテンツ】
相続相談はどこにするべき?専門家(税理士、司法書士、弁護士)の強み
【クレアスの相続税サービス】

監修
中村亨
日本クレアス税理士法人 代表
税理士
公認会計士
2002年8月に会計事務所として創業、2005年には税理士事務所を開業し、法人や個人のお客様の会計・税務の支援をする中で、「人事労務の問題を相談をしたい」「事業承継を検討している」といったお客様のニーズに応える形でサービスを拡大し続け、現在では社会保険労務士法人など複数の法人からなるグループ企業に成長してきました。お客様に必要なサービスをワンストップで提供できることが当社の強みです。