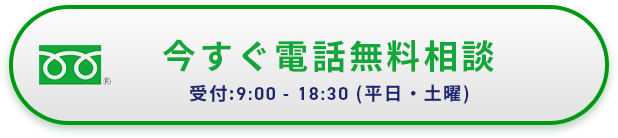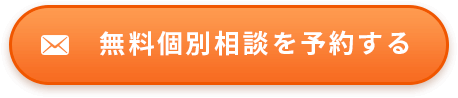教育資金贈与が使いきれないと贈与税がかかるリスクがある!対策と知っておくべきこと

監修
中村亨
日本クレアス税理士法人 代表 税理士 公認会計士
一般的には年間110万円を超える贈与には、贈与税がかかります。
しかし、親から子や祖父母から孫への教育資金贈与は、最大1,500万円まで贈与税が非課税となります。
贈与を受けた子や孫の中には、贈与された教育資金が使い切れず「贈与税の支払いが必要かも」と不安に感じている方も多いでしょう。
教育資金が残った場合、一定の条件下では贈与税が課される可能性があります。
本記事では、教育資金贈与で資金が使い切れない場合の税務リスクと、贈与税を回避するための具体的な対策について詳しく解説します。
子や孫に教育資金を一括で贈与したいと考え得ている方や、教育資金としてお金を受け取ったけど使いきれず「贈与税」の支払いを不安に感じている方はぜひ最後までご覧ください。
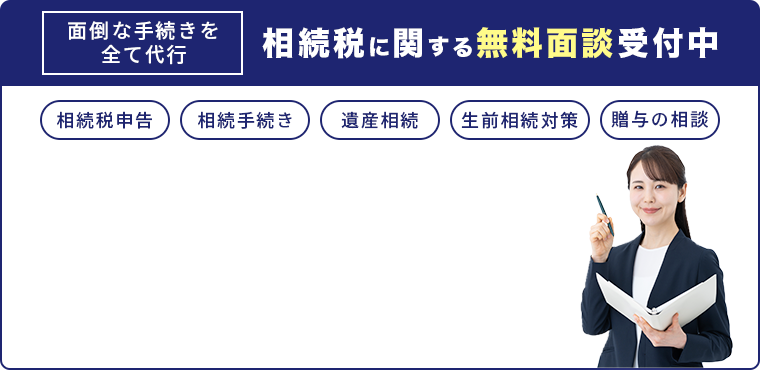
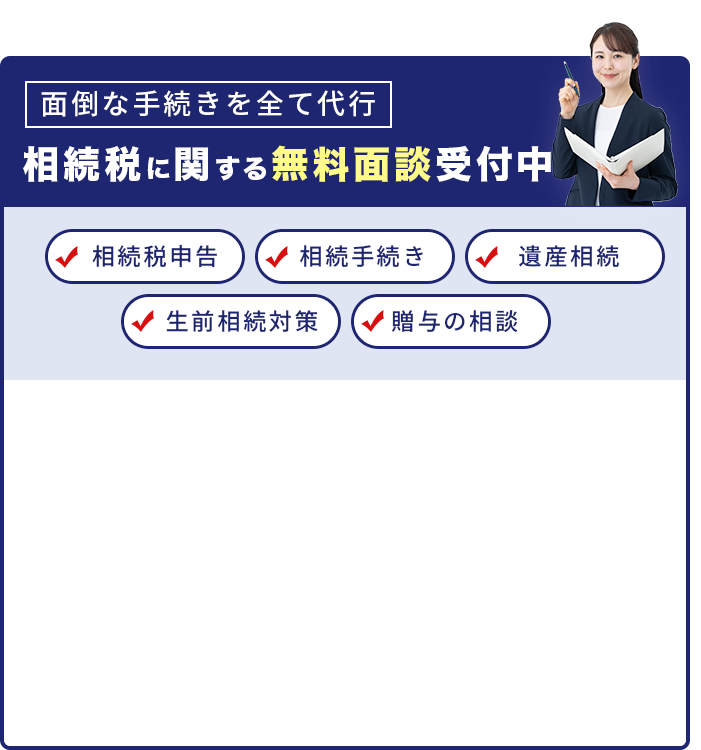
目次
1. 教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置とは
教育資金の一括贈与の方法として以下の2つがあります。
- 信託型
- 現金型
それぞれ異なる仕組みや条件で贈与税の非課税措置が適用されます。
仕組みや条件を確認し、非課税制度を活用しましょう。
1-1. 教育資金一括贈与の概要と非課税になる仕組み
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置は、祖父母や父母が子や孫の教育費として資金を一括で贈与する際、一定の条件を満たせば贈与税が非課税となる制度です。
この制度には「信託型」と「現金型」の2つの方法があります。
- 信託型:金融機関の信託口座や預金口座を活用する方法です。領収書を金融機関に提出して教育費であることを証明します。
- 現金型:現金で直接教育費を支払う方法です。現金型の場合、贈与の事実を証明できるものがないため、贈与契約書の作成が必要です。
その実務性や管理の利便性から、実際には「信託型」が多く選ばれています。
1-2. 制度の対象者と適用条件|贈与者・受贈者の要件とは
この制度を利用するには、贈与者と受贈者それぞれに要件があります。
- 贈与者:受贈者の直系尊属(祖父母や父母など)
- 受贈者:30歳未満の直系卑属(子や孫など)かつ前年の合計所得金額が1,000万円以下
贈与者、受贈者どちらの条件も満たさないと、制度は適用されません。条件を満たしているか、必ず確認しましょう。
1-3. 非課税枠と適用期限|令和8年3月末までに注意
教育資金の一括贈与制度の非課税枠と適用期限は、以下のとおりです。
- 非課税枠:1,500万円(このうち学校等以外に支払う費用(習い事など)は500万円まで)
- 適用期限:令和8年3月31日まで
この制度は平成25年4月に開始され、これまで何度も延長されてきた経緯があります。
平成31年には令和3年3月末まで、その後令和5年3月末まで延長され、現在は令和8年3月末までとなっています。
延長されている経緯はありますが、制度活用するには期限内に手続きを行うことが大切です。
制度の利用を検討している場合は、早めに準備をしましょう。
2. 一括贈与された教育資金が使いきれないと贈与税がかかるって本当?
教育資金の一括贈与で受け取った資金が、使いきれずに残った場合、一定の条件下では贈与税の対象となる可能性があります。
- 贈与税がかかる4つの条件
- 贈与税がかからない3つのケース
具体的な条件を踏まえながら、それぞれを確認します。
2-1. 4つの条件を満たす場合には残った資金に贈与税がかかる
資金が残っている場合、以下4つの条件をすべて満たすと残額に贈与税がかかるかもしれません。
- 受贈者が30歳に達して契約が終了していること
- 契約終了時に110万円以上の管理残額があること
- 贈与者が存命であること
- 受贈者が学校を卒業していること
たとえば、大学院を卒業した孫が30歳になった時点で300万円が残っており、祖父母が健在な場合です。
残った300万円に対して贈与税が課税されます。この場合の贈与税額は、基礎控除110万円を差し引いた190万円に対する税率で計算されます。
2-2. 贈与税がかからないケースは3つある
教育資金が残っても贈与税がかからないケースは、以下の3つです。
- 受贈者が30歳到達時点で在学中または教育訓練給付金対象講座を受講している場合
この場合、教育資金管理契約継続届を提出することで、40歳まで契約延長が可能です。40歳までに教育資金を使い切れば贈与税はかかりません。 - 契約期間中に贈与者が死亡した場合
この場合、死亡時に残っていた資金は贈与者の「相続財産」として扱われるため、贈与税ではなく相続税が課されます。 - 契約期間中に受贈者が死亡した場合
この場合、死亡時に残っていた資金は受贈者の「相続財産」として扱われるため、贈与税ではなく相続税が課されます。
手続きが必要なケースもあるため、注意しましょう。
3. 贈与税率と申告手続きについて
もしも教育資金が使い切れず贈与税を払う必要がある場合、どれくらい課税されるのか、贈与税の申告は必要かが気になる方もいるでしょう。
贈与税の基礎控除と税率と確定申告の手続きについて解説します。
教育資金が使い切れなかった場合も、以下を参考に必要な手続きを行いましょう。
3-1. 贈与税の基礎控除と税率
贈与税には年間110万円の基礎控除があり、これを超えた部分に課税されます。
税率は贈与額に応じて10%から55%の累進税率が適用されます。
- 一般贈与財産用(一般税率):受贈者が未成年の場合
|
基礎控除後 |
200万円以下 |
300万円以下 |
400万円以下 |
600万円以下 |
1,000万円以下 |
1,500万円以下 |
3,000万円以下 |
3,000万円超 |
|
税率 |
10% |
15% |
20% |
30% |
40% |
45% |
50% |
55% |
|
控除額 |
- |
10万円 |
25万円 |
65万円 |
125万円 |
175万円 |
250万円 |
400万円 |
たとえば残額が300万円の場合、基礎控除110万円を差し引いた190万円が課税対象です。
税率10%なので、税額は19万5千円となります。
- 特例贈与財産表(特例税率):受贈者が成人の場合
|
基礎控除後の |
200万円以下 |
400万円以下 |
600万円以下 |
1,000万円以下 |
1,500万円以下 |
3,000万円以下 |
4,500万円以下 |
4,500万円超 |
|
税率 |
10% |
15% |
20% |
30% |
40% |
45% |
50% |
55% |
|
控除額 |
- |
10万円 |
30万円 |
90万円 |
190万円 |
365万円 |
415万円 |
640万円 |
たとえば残額が450万円の場合、基礎控除110万円を差し引いた340万円が課税対象となります。
税率は15%なので、税額は51万円で、そこから控除額の10万円を差し引いて税額は41万円です。
贈与税を支払えば、受贈者の自由財産とみなされ教育費以外の用途にも資金を利用可能です。
3-2. 贈与税申告の流れと必要書類
教育資金に贈与税が課される場合、受贈者は贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに贈与税申告を行う必要があります。
申告書は税務署で入手するか、国税庁のホームページからダウンロードできます。
申告は住所地を所轄する税務署に提出し、税金が発生する場合は同時に納付も必要です。電子申告(e-Tax)も利用可能で、自宅からでも手続きができます。
申告期限を過ぎると延滞税がかかるため注意しましょう。
4. 教育資金贈与を使い切るための対策と知っておくべきこと
教育資金を効果的に活用し、贈与税が発生しないようにするための具体的な対策と重要なポイントを4つ紹介します。
- 支出計画を立てておく|学費・習い事・留学費用の想定
- 暦年贈与との併用を検討する
- 税理士や金融機関への相談した上で活用する
- 贈与税を払うことができれば残った資金は自由に使える
教育資金を使い切らないと贈与税が課税される場合もあるため、事前に確認しておきましょう。
4-1. 支出計画を立てておく|学費・習い事・留学費用の想定
教育資金を使い切るには、長期的に支出計画を立てることが大切です。
教育資金には、以下の2つが含まれます。
- 学校等に直接支払われるもの:入学費用や授業料、学用品代、修学旅行費など
- 学校等以外のものに対して支払われるもの:習い事に係る費用や留学の渡航費、通学の定期代など
そのため、教育資金贈与として1,500万円を受け取った場合、大学4年間の学費だけでなく、習い事や塾の費用・海外留学費用なども含めて総額を見積もりましょう。
たとえば、私立大学の場合、4年間で約400~800万円ほどの学費がかかります。
それに加え、通学用の定期代や、大学院への進学、資格取得に関わる費用でも贈与資金を活用することができます。
どこにいくら使用するのかの計画や見通しを立てておくと、教育資金を使い切れるでしょう。
また定期的に計画を見直し、実際の支出状況と照らし合わせることが大切です。
受贈者の進路に合わせて、適切に資金調整を行いましょう。
4-2. 暦年贈与との併用を検討する
教育資金の一括贈与制度と暦年贈与を併用することで、より効率的な贈与が可能です。
暦年贈与では年間110万円まで贈与税がかからないため、この枠を活用して教育費以外の生活費や将来のための資金を贈与できます。
たとえば祖父母が孫に教育資金として1,000万円を一括贈与し、さらに毎年110万円を暦年贈与で渡すことで、合計の贈与額を増やせます。
ただし、暦年贈与は継続的な贈与と認定されると定期贈与として課税される可能性があるため、贈与のタイミングや金額を変えるなどの工夫が重要です。
4-3. 税理士や金融機関への相談した上で活用する
教育資金贈与制度は複雑な仕組みのため、専門家への相談が大切です。
税理士は税務面での最適な活用方法をアドバイスし、金融機関は制度利用の手続きや管理方法をサポートしてくれます。特に贈与額が大きい場合や家族の状況が複雑な場合は、事前の相談により思わぬリスクを回避できます。
税理士への相談には、相談費用はかかりますが、適切な制度活用により得られるメリットが大きくなる場合が多いです。
4-4. 贈与税を払うことができれば残った資金は自由に使える
教育資金が残って贈与税を支払った場合、その後の資金は受贈者が自由に使用できます。
残った教育資金の贈与税を支払うことで、残った資金の使途制限はなくなります。
そのため、生活費や住宅資金、事業資金などに充てることも可能です。
贈与税率は相続税率より低い場合も多く、早期の資産移転により相続税対策にもなります。
資金が余る可能性がある場合は、贈与税の負担も含めて総合的に判断することが大切です。
5. 教育資金の一括贈与についてよくある質問
教育資金贈与制度について、よく寄せられる以下の3つの質問とその回答をまとめました。
- 30歳を過ぎても大学に在学中なら非課税枠は延長される?
- 契約中に贈与者(祖父母や父母など)が亡くなったらどうなる?
- 契約中に受贈者(子や孫など)が亡くなったらどうなる?
1つずつ解説します。
5-1. 30歳を過ぎても大学に在学中なら非課税枠は延長される?
受贈者が、30歳到達時に大学や大学院などに在学している場合、教育資金管理契約継続届を提出することで40歳まで非課税措置を延長可能です。
非課税措置の対象となるのは学校教育法で定められた大学・大学院・専門学校などで、通信教育や夜間コースも含まれます。
また、教育訓練給付金の対象となる職業訓練講座を受講している場合も延長が可能です。
継続届は在学証明書と共に金融機関に提出する必要があります。
受贈者が30歳になっても、非課税枠を活用できるため手続きを忘れないようにしましょう。
5-2. 契約中に贈与者(祖父母や父母など)が亡くなったらどうなる?
贈与者が死亡した場合、死亡時点での管理残額は「相続財産」として扱われ、贈与税は課されません。
相続人は受贈者を含む相続人全体で、管理残額は相続税の課税対象です。
ただし、受贈者が23歳未満である場合や、学校などに在学中の場合は相続税の対象には含まれません。
それ以外の場合には、たとえば祖父が死亡時に管理残額が500万円ある場合、この500万円は相続財産として相続税の計算に含まれるのです。
教育資金管理契約は贈与者の死亡により終了し、その後の教育費は通常の相続財産から支出することになります。
相続人間でのトラブルを避けるため、教育資金の贈与を行う際には、事前に親族内で話し合っておくことも大切です。
5-3. 契約中に受贈者(子や孫など)が亡くなったらどうなる?
受贈者が死亡した場合、教育資金管理契約は終了し、管理残額は受贈者の相続財産となります。
受贈者の相続人(配偶者や子など)が残額を相続することになり、相続税の課税対象です。
贈与者への返還は行われず、贈与税も課されません。
たとえば孫が交通事故で死亡し管理残額が200万円ある場合、この200万円は孫の相続財産として孫の法定相続人が相続します。
受贈者に配偶者や子がいない場合は、受贈者の両親や兄弟姉妹が相続人となります。
このような不測の事態に備えて、受贈者は相続人へ教育資金の贈与を受けていることを共有しておくことも大切です。
6. 教育資金贈与は計画的に使い贈与税がかからないようにしよう
教育資金の一括贈与制度は、適切に活用すれば贈与税を抑えながら効果的に教育資金を援助できます。
しかし、資金が使い切れない場合は贈与税が発生するリスクもあるため、事前に計画を立てるのが大切です。
制度を利用する際は、受贈者の将来の教育計画を詳細に検討し、学費だけでなく習い事や留学費用なども含めた長期的な支出計画を立てましょう。
また、受贈者の30歳到達時の状況や所得見込み、贈与者の健康状態なども考慮して、リスクを最小限に抑える工夫が必要です。
万が一資金が残った場合でも、贈与税を支払えばその後は自由に使用できる財産となるため、必ずしもデメリットばかりではありません。
制度の仕組みを正しく理解し、税理士や金融機関の専門家に相談しながら、家族の状況に最適な活用方法を見つけましょう。

監修
中村亨
日本クレアス税理士法人 代表
税理士
公認会計士
2002年8月に会計事務所として創業、2005年には税理士事務所を開業し、法人や個人のお客様の会計・税務の支援をする中で、「人事労務の問題を相談をしたい」「事業承継を検討している」といったお客様のニーズに応える形でサービスを拡大し続け、現在では社会保険労務士法人など複数の法人からなるグループ企業に成長してきました。お客様に必要なサービスをワンストップで提供できることが当社の強みです。