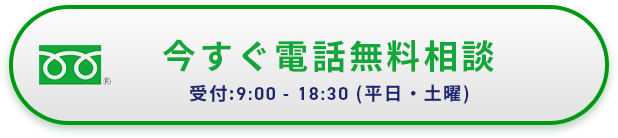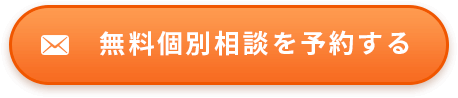相続税の税務調査に選ばれやすい家庭とは?特徴・傾向・防ぐための実務対策

監修
中村亨
日本クレアス税理士法人 代表 税理士 公認会計士
相続税の申告を終えたご家庭の中には、「無事に申告したから安心」と思われる方も多いでしょう。
しかし実際には、申告後に税務署から税務調査を受ける家庭が少なくありません。
国税庁のデータによると、相続税の申告を行った家庭のうち、毎年約10〜15%前後が税務調査の対象となっています。
税務署は「どの家庭を調べるか」を、被相続人の資産状況・収入・預貯金の動き・申告書の精度などを総合的に分析して選定しています。
つまり、税務調査には“選ばれやすい家庭”があるのです。
この記事では、税理士が実務経験と最新の税務調査傾向を踏まえて、調査対象になりやすい家庭の特徴、税務署が注目するチェックポイント、選ばれないためにできる対策をわかりやすく解説します。法令・制度は2025年10月時点の情報に基づき記載しています。
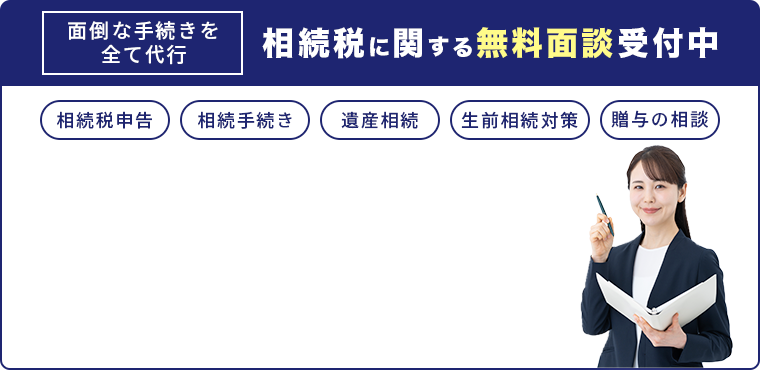
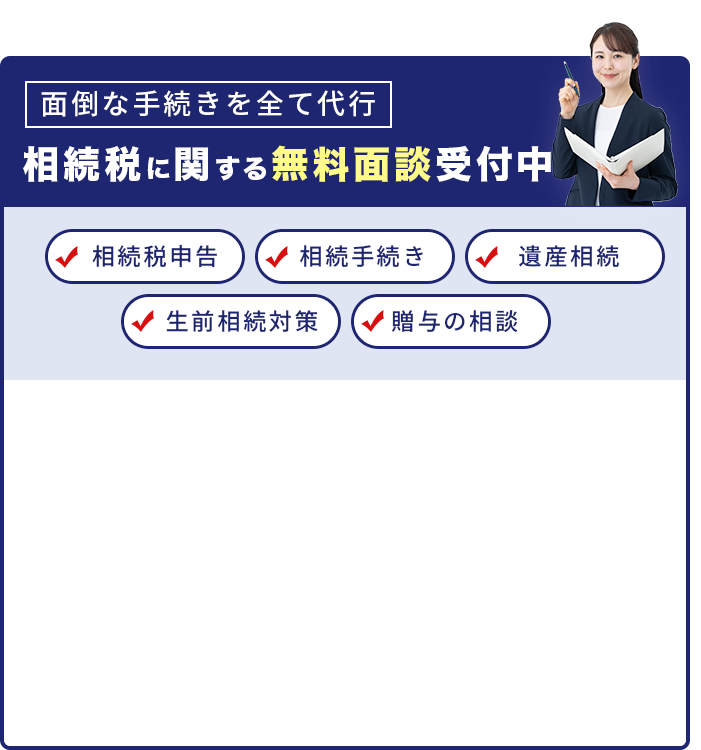
目次
1. 相続税の税務調査とは?――その目的と発生率
1-1. 税務調査の目的
相続税の税務調査とは、相続税の申告内容に誤りや申告漏れがないかを確認するために、税務署が実施するものです。
国税庁は公式サイトで「税務調査は、適正・公平な課税の実現を目的とする」と説明しています(出典:国税庁「税務行政の現状と課題」)。
相続税の税務調査は、大きく分けて次の2種類があります。
-
実地調査(臨場調査):税務署職員が自宅や税理士事務所を訪問し、通帳や財産の確認を行う。
-
簡易調査(文書・電話確認):書面での質問・確認のみを行う。
1-2. 調査の発生率と追徴税額
国税庁の統計によると、令和4年度に行われた相続税の実地調査件数は約8,000件。そのうち約8割で何らかの申告漏れが指摘されています。
1件あたりの追徴税額は平均で500万円前後にも達しており、「知らなかった」だけでは済まされない結果となることが多いのです。
2. 税務調査に「選ばれやすい家庭」の特徴
税務署は全件を調査するわけではありません。限られた人員と時間の中で、「調べる価値がある」と判断したケースに絞って実地調査を行います。
その際に注目されるのが、以下のような特徴を持つ家庭です。
2-1. 財産規模が比較的大きい家庭
当然ながら、相続財産が多ければ申告内容の誤りが生じるリスクも高く、税務署としても重点的に確認したくなります。
おおむね相続財産が1億円を超える家庭では調査対象になる確率が高まります。
特に、複数の不動産を所有している、預貯金が数千万円単位である、上場株式や投資信託を多く保有しているといった場合には、財産評価の誤りや申告漏れが発生しやすく、重点的な調査対象になりやすい傾向があります。
2-2. 預貯金や現金の動きが不明瞭な家庭
被相続人の預金口座の入出金に不自然な点がある場合、税務署は「生前贈与」「隠し財産」「名義預金」などの可能性を疑います。
例えば、相続開始直前に多額の引き出しがある、家族名義の口座に繰り返し振込がある、預金残高に対して生活費支出が少なすぎるといったケースは調査対象になりやすい典型例です。
国税庁は近年、金融機関からの情報照会を強化しており、複数の口座を横断的に把握できる体制を整えています。
2-3. 不動産や株式など、評価が難しい資産を多く持つ家庭
不動産、特に貸家や私道持分のある土地などは、評価方法の違いによって税額が大きく変わります。
また、非上場株式やゴルフ会員権なども評価が複雑なため、専門的な判断が必要です。
税務署は「評価誤りが起きやすい財産」に注目して調査対象を絞っています。
特に、路線価と実勢価格の差が大きい都市部の土地を所有している場合は注意が必要です。
2-4. 相続人構成が複雑・情報が整理されていない家庭
相続人が多い、あるいは相続人同士の連絡が取れない場合など、情報整理が難しい家庭も調査対象に選ばれやすくなります。
また、海外に居住している相続人がいる、相続人が未成年・高齢者である、申告を税理士に依頼せず自力で行っているといったケースも、税務署側から見ると「誤りが生じやすい」と判断されやすい傾向にあります。
3. 最新の税務調査傾向 ― データとAIによる選定強化
国税庁では、相続税の税務調査対象を選定する際に、過去の申告データ・所得データ・金融機関情報などを統合的に分析しています。
特に、KSK(国税総合管理)システムのデータベース化により、次のような情報が自動的にクロスチェックされる仕組みになっています。
-
被相続人の過去の所得税申告内容
-
不動産登記・株式保有情報
-
贈与税申告・生前贈与履歴
-
金融機関からの支払調書(利息・配当・解約金など)
これにより、従来は見逃されていた「相続財産と収入のギャップ」「生活実態との不一致」が簡単に検出されるようになっています。
したがって、“富裕層”だけでなく中間層の家庭も調査対象に選ばれる可能性が高まっているのが現状です。
4. 調査対象になる前にできるチェックリスト
調査に選ばれやすい家庭には一定の共通点があります。
次のチェック項目を確認して、該当するものが多い場合は専門家への早期相談をおすすめします。
- 被相続人の預貯金の出入りが多い
・大きな出金や振込が頻繁にある場合は注意。
→ 出金・振込の理由を明確に記録し、通帳メモなどで管理しましょう。 - 家族名義の口座を被相続人が管理していた
・税務署に「名義預金」と見なされるリスクがあります。
→ 贈与契約書や振込記録を残して、実際の贈与であることを証明しましょう。 - 不動産の評価を自分で行った
・評価方法の誤りにより税務調査の対象になる可能性。
→ 路線価・倍率の確認を税理士に依頼し、適正評価を行いましょう。 - 相続人が多数・連絡が取りづらい
・資料共有や意思統一の遅れが、申告漏れにつながることも。
→ 代表相続人を決め、書類や情報を一元管理する仕組みを整えましょう。 - 申告書を自作した
・添付資料や計算ミスが起こりやすく、申告内容に不備が生じる恐れ。
→ 税理士によるダブルチェックを受け、誤りを防ぎましょう。 - 贈与や貸付金の証拠がない
・口頭約束や現金手渡しでは、税務署に説明できないケースも。
→ 契約書・振込明細などの証拠を整理し、データ化して保管しておきましょう。
これらの対策を行うことで、税務署の「確認したい対象」として選ばれるリスクを大幅に下げられます。
5. 税務調査を受けた場合の流れと正しい対応
税務調査は突然訪問されることはありません。通常、事前に税務署から「調査実施の通知」が届きます。
調査までの一般的な流れ
-
税務署からの連絡(電話・書面)
調査日程・対象・場所などを調整します。 -
事前準備
通帳・印鑑・契約書・領収書など、財産関連書類を整理。 -
調査当日
税務署職員2〜3名が訪問。ヒアリング・通帳確認・金庫の現金確認を行うこともあります。 -
結果の説明・修正申告
誤りがあれば修正申告・追徴課税が発生し、納付期限が設定されます。
税務調査で重要なポイント
-
感情的にならないこと。調査官も事実確認が目的です。落ち着いた対応を心がけましょう。
-
その場で判断しないこと。疑問点があれば税理士を通じて回答します。
-
記録をすぐ提出しないこと。原本提出前にコピーを保管し、内容を税理士が確認してから対応します。
税務調査は「怖いもの」ではなく、「適正な説明を求める場」です。誠実に対応すれば、多くのケースでスムーズに終了します。
6. 「選ばれない家庭」にするための3つの対策
対策①:日頃から財産記録を整える
預金通帳・不動産登記・保険証券・株式保有一覧など、財産の全体像を一つのファイルにまとめておくことが大切です。
また、出金理由や振込の目的をメモしておくだけでも、調査時の説明が格段に楽になります。
対策②:贈与・資金移動の記録を残す
生前贈与を行っている場合は、必ず契約書と振込記録を残しましょう。
特に110万円以下の贈与は非課税である一方、証拠がなければ「名義預金」として相続財産に含まれるリスクがあります。
税務署は「契約書がある贈与」と「ない贈与」を厳密に区別しています。
対策③:専門家による申告と事前相談
税務署が着目するポイントは、税理士の目線で事前に予測できます。
経験豊富な税理士に相談すれば、財産評価の誤りや書類不備を未然に防ぎ、税務調査リスクを大幅に減らせます。
7. まとめ|「選ばれやすい家庭」を知ることが、最善の防御策
税務調査に選ばれやすい家庭には、明確な傾向があります。
財産規模が大きい、預貯金の動きが不自然、評価の難しい資産が多い、書類や記録が不十分といった特徴です。
一方で、これらの特徴は適切な管理と専門的サポートで改善できます。
申告前から「見られやすいポイント」を意識し、記録・契約・相談を徹底すれば、調査の可能性を最小限に抑えられます。
税務調査は“運”ではなく“準備”で防げるものです。
ご家庭の相続が円滑に進むよう、早めの見直しをおすすめします。

監修
中村亨
日本クレアス税理士法人 代表
税理士
公認会計士
2002年8月に会計事務所として創業、2005年には税理士事務所を開業し、法人や個人のお客様の会計・税務の支援をする中で、「人事労務の問題を相談をしたい」「事業承継を検討している」といったお客様のニーズに応える形でサービスを拡大し続け、現在では社会保険労務士法人など複数の法人からなるグループ企業に成長してきました。お客様に必要なサービスをワンストップで提供できることが当社の強みです。