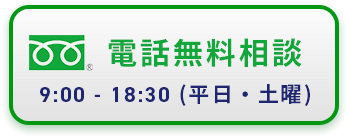相続税の時効はいつから?5年・7年?ペナルティについても解説
相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10か月後」です。しかし申告手続きを必要とするケースのなかには、相続開始当初の誤解が原因で無申告や申告漏れが生じたり、現金資産がなく納税できなかったりといったケースが少なからずあります。
このような場合、相続税の確定と納税義務は原則5年で時効完成を迎えますが、税務署が時効完成を許すことは基本的にありません。
本記事では、相続税の時効について法律上の考え方を分かりやすく解説し、そのうえで「申告にミスがある・期限に手続きが間に合わない」「期限までに納税できない」という不安への対処法を紹介します。
目次

1.相続税にも時効はあるの?
相続税の課税では、法令に基づき正しい金額の納税を実現させる「国税債権」が国税庁側に認められます。
また「国税債権は一定期間が経過すると消滅する」とも法律で定められており、消滅までの期間が一般に“時効”と呼ばれています。
法律で定められた一定期間が経過して“時効完成”に至れば、正当な金額の相続税を納税させようとする国税庁の行動に法的根拠はなくなります。
そもそも時効制度の目的は、国税庁・納税義務者の双方の視点での公平化にあります。
納税義務者が「税務調査や差押えが実施されるかもしれない」という不確実性の高い状況に置かれ続けるのは、たとえ落ち度(申告漏れや納期限後の未納など)があっても許容できません。
国税庁の立場を法律的に解釈しても、早々に納税を実現させる手続き(税務調査や督促など)を取らないのであれば、その債権は保護するに値しません。
本来相続税は正しく申告・納税されるべきものですが、以上のように納税義務者の立場を悪化させない配慮も“時効”の考え方に表れています。
2.相続税の時効は起算日から5年または7年!
相続税は原則として「起算日から5年」で時効完成に至ります。
起算日とは相続税の法定申告期限(死亡を知った日から10か月)の翌日です。
しかし正確に“時効”を理解するには、国税債権を巡る法律上の2つの権利を押さえる必要があります。
2-1.時効起算日は2つある(賦課権・徴収権)
相続税の課税に関し、国税庁は下記2つの権利を有しています。
- 賦課権:申告または更正および決定で課税額を確定させる権利
- 徴収権:課税額の確定後に納税を実現させる権利
一般に“時効”と呼ばれる期間も法律上の呼称は異なり、賦課権では「除斥期間」・徴収権では「消滅時効」がそれぞれ正しい呼び方です。
課税の権利を2つに区分し、時効の呼び分けを行うのは、起算日の扱いを含む権利消滅までの仕組みが異なるため。
以下では、賦課権の時効(除斥期間)から順に詳しく仕組みを解説します。
※除斥期間・消滅時効ともに便宜上“時効”と表現することがあります。
2-2.賦課権の時効(除斥期間)
賦課権、つまり正しい課税額を確定させる権利の時効の起算日は「法定申告期限の翌日」です。
起算日から5年の除斥期間中は、納税義務者が正しい申告を行わない限り、管轄税務署は税務調査を実施するなどして課税額を確定させることができます。
また、虚偽申告などの不正行為による脱税が認められた場合、除斥期間は7年に延長されます。
下記のルールによって、申告手順を把握するための追加の調査を実施し、ペナルティ(加算税)を課す猶予が生まれるのです。
<「除斥期間」の性質について>
賦課権の除斥期間は「一定期間が経てば自動的に成立し、時効完成の阻止もあり得ない」という2つの性質を持ちます(下記参照)。
これは時効の基本趣旨に添い、課税額を二転三転させられる状態を長期化させないようにするためです。
【除斥期間の性質】
- 中断・停止しない…課税を巡る当事者がいかなる手続きを取っても、除斥期間の進行は止まりません。相続開始から5年と10か月が経過した段階で、例外なく時効完成に至ります。
- 当事者の援用不要…「援用」とは、時効完成後にその事実を主張することを指します。除斥期間の経過による賦課権の消滅は、これによって利益を受ける納税義務者側からわざわざ主張せずとも、自動的に成立します。
一見すると納税者側に有利ですが、5年経過をじっと待つことも現実的ではありません。
詳しく後述するように、税務調査の実態や万一申告漏れが発見された場合のペナルティの大きさから「除斥期間が経過するまで賦課権が行使されない」というのは考えにくいからです。
2-3.徴収権の時効(消滅時効)
徴収権、つまり税務署長が既に確定した国税債権の履行を求める権利の起算日は「納期限の翌日」です。
起算日から5年の消滅時効完成までのあいだ、相続税を納税するよう督促し、なお納税がなかった場合には裁判所を通じて財産を差押えする権利を国税庁は有します。
<「消滅時効」の性質とは>
徴収権の消滅時効は、債権者である国税庁側に有利な下記の性質があります。
ただし、債権者が強制力の強い回収手段がとれる官公庁であるという状況を踏まえ、民間で設定された私債権にはない性質も認められています。
【消滅期間の性質】
- 中断・停止がある…「納税義務者が確定した課税額を承認する」「国税庁が差押え手続きなどの裁判上の請求に踏み切る」等の事由が生じた場合、その発生時点で時効起算日まで巻き戻されたり(=中断)、時効完成までのカウントが一時的にストップしたり(=停止)します。
- 当事者の援用不要(絶対的効力)…いったん消滅時効が完成すれば、利益を受ける納税義務者側からあえて主張せずとも、納税は免除されます。これは私債権(銀行からの融資など民間で成立する債権)のルールと対比し「消滅時効の絶対的効力」と呼ばれます。
2-4.消滅時効の中断事由・停止事由
徴収権の消滅時効は、賦課権(除斥期間)のように期間延長が認められない代わりに、時効中断または停止の事由(下記参照)が生じれば無限に完成を先延ばしできる仕組みを持ちます。
【徴収権の消滅時効】中断事由・停止事由にあたるもの
- 中断事由→国税債権を確定させる処分(更正および決定※)→裁判外で納税を実現させようとする処分(賦課決定・納税の告知・督促・交付要求)→裁判上で納税を実現させようとする処分(差押え手続きの開始など)→納税義務者側からの「納税申告(修正申告あるいは更正の請求)※」「納税猶予または換価猶予」「延納」「一部納税」の各申請
- 停止事由→「納税猶予または換価猶予」「延納」の猶予期間中である
※修正申告・更正・決定などで課税額が増えた場合、時効中断にかかるのはその増額分だけです。確定した課税額のうち、当初の申告によって納税義務が生じた金額については、時効中断は起こらず完成までのカウントが進みます。
以上の時効の仕組みをまとめると、国税庁の権利行使の過程では、時効完成時期が絶対的な「賦課権」の行使後、実質的に時効完成に至ることがない「徴収権」が生まれます。
すでに述べたように、賦課権が未行使のまま除斥期間が完成するケースは考えにくいと言わざるを得ません。
“時効”はあくまでもイレギュラーな事例での救済手段として用意されているだけで、ほとんどの場合は申告・納税を逃れられないのです。
3.相続税を申告・納税しなかった場合のペナルティ
万一にも相続税について納税義務者の落ち度(未申告・過少申告・不正行為・未納)が確認された場合、修正申告や納税の際にペナルティとして「加算税」があります(表参照)。
【表】相続税申告に誤り等があった場合の加算税一覧
| 申告・納税ミスの内容 | 加算税の種類 | 加算税割合 |
|---|---|---|
| 正当な理由なく 法定申告期限までに手続きしなかった |
無申告加算税 |
50万円以下の部分:課税額の15%
50万円超300万円以下の部分:20%
300万円超の部分:30%【令和5年度改正】
|
| 相続税の申告金額が不足していた | 過少申告加算税 | 課税額追加分の10%(加算分が当初の課税額と50万円のどちらか多い方を上回る場合は15%) |
| 申告時に不正行為があった | 重加算税※ | 過少申告の場合:課税額追加分の35%無申告の場合:40% |
国税について法定納期限後に |
不納付加算税
|
10%
|
参考:財務省「加算税の概要」
※期限後申告等があった日以前の5年以内に無申告加算税または重加算税を課された(徴収された)ことがある場合、加算税割合が10%上昇します。
納税義務者側の不利益は加算税ばかりではありません。
ミスや不正行為を指摘されて期限後申告に至った場合、税額軽減につながる特例の一部が適用できなくなるのです。
不動産を対象に大幅な軽減を可能にする特例(“小規模宅地等の特例“など)の利用ができないともなると、加算税とは比べ物にならない巨額の損失につながるでしょう。
以上の点から、ペナルティ回避の努力は最大限払わなければなりません。
4. 相続税のペナルティを軽減する対処法
どれだけ気をつけていたとしても、申告内容をミスしてしまったり、遺産分割協議が進まずに期限に間に合わなかったりと、ペナルティを受けてしまう可能性は充分にあります。
そのような場合には、すべてのペナルティを受け入れるしかないのでしょうか。
相続税のペナルティを軽減する対処法を3つ紹介します。
- 修正申告
- 申告期限の延長
- 延納・物納
1つずつ解説します。
4-1.修正申告:申告の誤りに対する加算税を低減
言うまでもなく法定申告期限内に正確に手続きするのが理想ですが、大切なのは「ミスに気づいたときにすぐ修正申告する」ことです。
税務調査が実施されるまでに修正申告が実施できれば、その努力が認められて加算税を大幅にカットされる可能性があります(下記参照)。
【加算税が一部or全額免除されるケース】
- 過少申告に気づいた場合調査後の加算税10%~15% → 税務調査前の修正申告で対象外に
- 無申告に気づいた場合調査後の加算税15%~20% → 税務調査前の期限後申告で5%に
もし修正内容にミスがあることに気付いた場合には、税務署に指摘される前に自分で再度申告しましょう。
4-2.申告期限の延長:やむを得ず申告が遅れる場合
なかには、相続トラブルや災害発生が原因で「遺産分割協議が進まず申告期限に間に合わない」というケースもあるでしょう。
該当の事情が発生した際にすぐ管轄税務署に申し出ることで、最大2か月の申告期限延長が認められます。
【参考】相続税の期限延長が認められるケース
- 死亡時点で胎児だった相続人が誕生した
- 相続人の異動(廃除や欠格による相続権喪失)があった
- 遺留分侵害額請求権が行使された
- 法定相続分とは異なる内容を記載した遺言書が、遅れて発見された
- 災害や感染症流行※などの特殊事情に巻き込まれた
※令和2年4月より、新型コロナウイルス流行を受けて特別対応が実施されています 。
自粛要請・テレワークの開始・関係者の感染等が原因で申告期限に間に合わない場合、管轄税務局に問い合わせた上で「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出しましょう。
4-3.延納・物納:納期限までに相続税が支払えない場合
相続税を支払えないときは、最大20年間の分割払いへ切り替える「延納」・金銭の代わりに相続財産そのものを支払い手段とする「物納」のいずれかが利用できます。
利用されることの多い「延納」は、延滞税の代わりに利子税が加算されるものの、延納特例基準割合(銀行の新規の短期貸出約定平均金利をベースとする割合)の加味により利率が下がります。
手持ちの現金が足りない場合は、出来るだけ税理士と相談し、各制度の活用を検討しましょう。
5.相続税の還付請求にも時効がある?
ここまでは「申告・納税された金額が課税額に満たないケース」を前提としていましたが、「当初申告時の課税額が正しい金額を超える(または払いすぎた)」場合はどうでしょうか。
結論として、過誤税額の返還を求める権利(=還付請求権)にも、やはり法定申告期限の翌日を起算日とする5年の消滅時効があります。
これに伴い、還付請求の前提として行うべき「更正の請求手続」(審査の上で当初より少ない課税額を認めてもらうための手続き)の期限は、還付請求権の消滅時効に準じるものとされています。また、相続手続きで避けがたい事情(後発的理由※)が生じた場合「その事実が生じた日の翌日から2か月または4か月以内」と短い手続き期限が設けられている点に注意しましょう。
※後発的理由とは
…「被相続人名義だと思っていた財産が実は他人名義だった」「負担付遺贈を解除した」等の事情を指します。
6.相続税の税務調査の時期や反面調査とは?
脱税の意図の有無にかかわらず、納税義務者の誤解による申告ミス・無申告は防ぎきれません。
こうした事例を発見する目的で実施されているのが「税務調査」です。
調査の実施時期は明確にされていないものの、過去に調査された事例や税務署の年間スケジュールに照らし合わせると、申告後1~2年以内の秋頃(7月から11月のあいだ)に対象者へ通知されるケースが大多数です。
比較的早期に調査が実施される点から、対象者の納税不足分が時効完成に至ることは到底ありえないことが分かります。
調査対象者の抽出方法についても明らかにはされていませんが、実施率は決して低くありません 。
平成29年分の申告に関する国税庁の発表※によると、課税対象となった被相続人の数は約11万2千人であるのに対し、調査件数は約1万2千件(課税対象人数の約10%)です。
※国税庁:平成29事務年度における相続税の調査の状況について(PDF)
税務調査は相続人への聞き取りや口座取引の調査など多岐に渡りますが、相続人が非協力的な悪質のケースの場合には反面調査という調査がされます。
反面調査とは相続人ではなく、相続人とやり取りをしていた相手方に対して調査を行うことを指します。
なお、反面調査は税務職員に与えられている正当な権限です。
税務調査の結果税務署側からの指摘を受けた場合には、ペナルティはかなり重いものになってしまいますので相続税は必ず申告しましょう。
7.名義預金の相続税には時効がない?
実際に過少申告や無申告が起きやすいのは“預貯金”です。
とくに、被相続人以外の名義で形成されている預貯金(名義預金)は無条件で相続財産にあたらないと誤解されやすい点は問題です。
下記のような名義預金は相続税申告時の遺産総額に含めなければならず、他の遺産と同じく時効にかかるものの、やはり税務署に見逃される可能性は低いと考えるべきでしょう。
【名義預金の例】
- 被相続人の配偶者の口座にある「へそくり」
- 被相続人の子や孫の名義で積み立てられた教育・結婚等の資金
個別のケースでの「相続税申告を要する名義預金にあたるか」の判断は、預金形成における客観的事実に基づいて判断されます。
具体的には、預金の原資が主に被相続人の財産だった場合、申告を要する可能性を考慮すべきです。
過去の裁決事例を参照すると、以下のような要件にあてはまるものが「申告を要する名義預金」と判断されています。
【名義預金の要件】
→預金原資が被相続人の財産である+以下①・②のいずれかに該当する場合
①被相続人の生前から、名義人は預金の存在を把握していた
②名義人には「預金が贈与されたもの」という認識がない
該当の資産を名義預金ではなく「生前に贈与されたもの」として扱うには、贈与契約書・贈与税申告の実績などの裏付けとなる事実が欠かせません。
ケースによっては、口座への入金手段(被相続人名義の口座からの振込など)で贈与された財産だと立証できます。
どのようなケースでも、相続人自身の判断による手続きは、申告ミスを指摘されるリスクを回避できません。
被相続人が遺したものの中に子・孫・その他親類などの第三者名義の預貯金がある場合は、税理士による個別の判断とアドバイスの上で申告するのがベストです。
8. 申告はしたが納税をしなかった場合にはどうなる?
申告はしたが納税をせずに期限を過ぎてしまった場合には、税務署から督促状が届きます。
その督促を無視していると財産の差押えなどの処分に繋がってしまいます。
相続税は相続人の連帯責任となるため、誰か1人が支払わなかった場合には、ほかの相続人が肩代わりしなければなりません。
督促状には支払いを促す意味合いもありますが、支払いの時効を延長させる効果があります。
周りに迷惑をかけないためにも、督促状が届いたらすぐに相続税を支払いましょう。
9.相続税の時効完成は望めないため税理士に相談しよう!
相続税の時効は、起算日を法定申告期限とする「課税額を確定させる権利」(=賦課権)・起算日を納期限とする「納税を実現させる権利」(=徴収権)の2つに区分され、それぞれ原則5年で完成します。
法律上は以上のルールがある一方で、税務調査の実施状況や時効の中断事由・停止事由を考慮すると、時効完成に期待するのは誤りです。
理想はやはり、正確な申告を期限までに行い、未納を生じさせないようにすることです。
上記がどうしても実現できなければ、税務調査が実施されるのを待たずに「修正申告」を行い、手持ちの現金資産が少ないときは延納・物納の相談を行うのが適切な対処法です。
加算税や差押え等のペナルティを避けるため、相続開始のより早い段階から、遅くとも万一のトラブルに気づいたときにすぐ税理士のサポートを得ましょう。