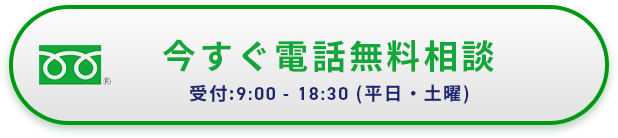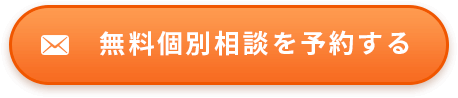生前贈与加算(持ち戻し)とは?相続開始前7年以内が対象|いつから?100万円控除も解説

監修
中村亨
日本クレアス税理士法人 代表 税理士 公認会計士
結論:生前贈与加算(持ち戻し)は、相続(遺贈)で財産を取得した人が、被相続人から「加算対象期間」内に受けた暦年贈与を、相続税の計算上、相続財産に加算するルールです。対象期間は段階的に3年から7年へ拡大し、期間内であれば110万円以下の贈与も加算対象になります。
相続税対策として生前贈与を行う方は多いですが、一定期間内の贈与は「相続税の計算上、いったん相続財産に足し戻す(持ち戻し)」必要があります。これが生前贈与加算です。
本記事では、制度の基本から改正内容(3年→7年)、移行期の考え方、延長4年分の総額100万円控除、110万円以下でも対象になる注意点、対象外になる贈与まで体系的に解説します。
※本記事は一般的な制度解説です。最終判断は個別事情(相続人構成・遺産内容・特例の適用可否)により異なります。
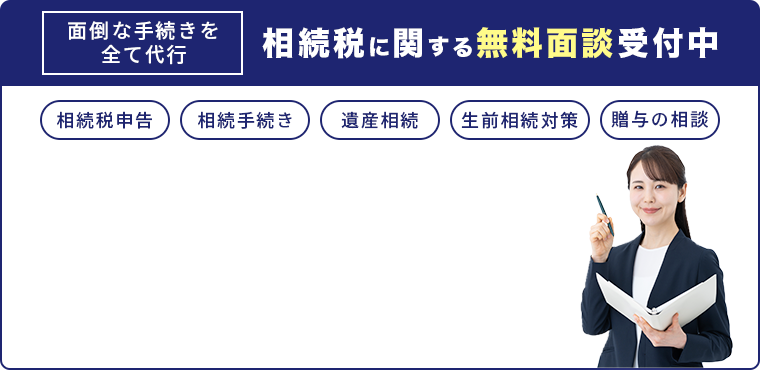
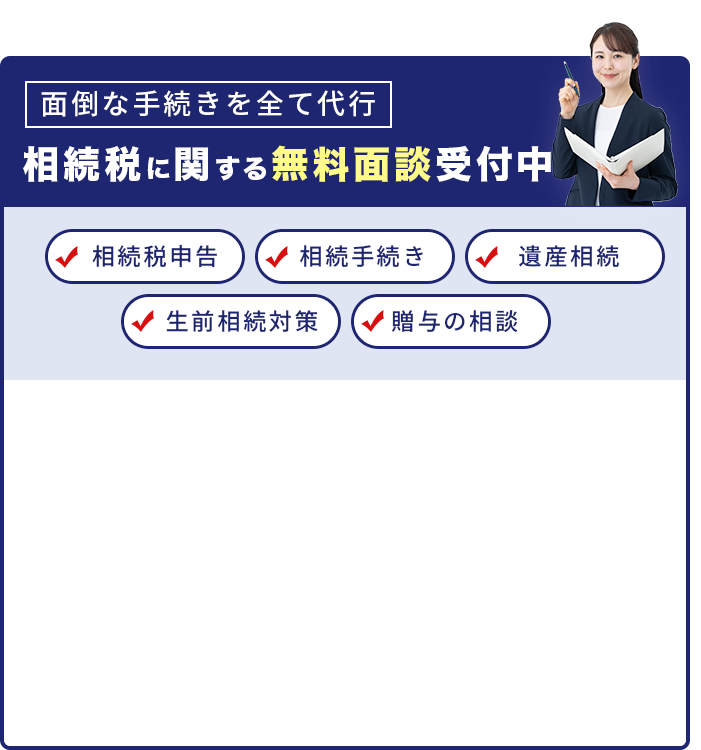
目次
1. 生前贈与加算(持ち戻し)とは?
生前贈与加算とは、相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人から一定期間内に受けた贈与について、その贈与時の価額を相続税の課税価格に加算する制度です。
目的は、相続直前の「駆け込み贈与」によって相続税だけが不自然に軽減されることを防ぐ点にあります。
1-1. 判定基準は「相続開始日(死亡日)」
持ち戻しは贈与日ではなく、相続開始日(死亡日)から逆算して期間内かどうかで判断します。
贈与税が課税されたかどうかは、持ち戻し判定の基準ではありません。
1-2. 対象となるのは主に「暦年課税」の贈与
問題になるのは主に、年間110万円の基礎控除がある「暦年課税」による贈与です。
相続時精算課税は別制度であり、暦年課税の持ち戻しとは仕組みが異なります。
2. 【改正】持ち戻し期間は3年から7年へ拡大
税制改正により、持ち戻し期間は最大7年へ拡大しました。
ただし、すぐに全員が7年になるわけではありません。**相続開始日(死亡日)**によって段階的に適用されます。
2-1. 早見表:相続開始日で加算期間が変わる
| 相続開始日 | 加算対象期間 |
|---|---|
| ~令和8年12月31日 | 相続開始前3年以内 |
| 令和9年1月1日~令和12年12月31日 | 令和6年1月1日以後の贈与が対象(段階的拡大) |
| 令和13年1月1日以降 | 相続開始前7年以内 |
重要なのは、「7年になるのはいつ?」という問いの答えは死亡日基準であることです。
移行期(令和9年~令和12年)は、「令和6年1月1日以後の贈与」が対象に含まれるため、結果として対象年数が段階的に広がる仕組みです。
3. 110万円以下でも持ち戻し対象になる?
結論として、期間内の贈与であれば110万円以下でも加算対象になり得ます。
よくある誤解は、
「110万円以下は贈与税がかからない=相続でも無関係」
という考え方ですが、これは誤りです。
生前贈与加算は「贈与税の課税の有無」とは別ルールです。
したがって、贈与税がゼロでも、期間内であれば相続税の計算上は加算対象になります。
4. 延長4年分は総額100万円まで加算しない
持ち戻し期間が3年から7年へ延びましたが、影響緩和のための措置があります。
相続開始前3年を超える部分(3~7年前の贈与)については、贈与時の価額の合計から総額100万円まで加算しないとされています。
4-1. 「毎年100万円」ではない点に注意
100万円控除は、
・毎年100万円使える制度ではありません
・延長された4年分の合計で100万円まで
という扱いです。
相続開始前3年以内の贈与は従来どおり全額加算されます。
5. 誰の贈与が加算対象になる?
持ち戻しは、基本的に相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人から受けた贈与が対象になります。
つまり、
・相続で財産を取得する人
・相続で財産を取得しない人
では、同じ贈与でも扱いが異なる可能性があります。
実務上の重要論点になるため、具体的なケースでは専門家への確認が安全です。
6. 持ち戻しの対象外になりやすい贈与
次の制度を適用している場合、原則として持ち戻し対象外となる扱いがあります。
・贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)
・住宅取得等資金の非課税制度
・教育資金の一括贈与(非課税)
・結婚・子育て資金の一括贈与(非課税)
ただし、制度の適用要件を満たしていることが前提です。形式的に利用しただけでは認められない場合もあります。
7. 相続税の計算への影響(イメージ)
持ち戻しがある場合の計算は次の流れになります。
-
相続財産を確定
-
加算対象期間内の贈与(贈与時の価額)を加算
-
合計額を基に相続税を計算
7-1. すでに払った贈与税はどうなる?
加算対象の贈与について贈与税を支払っている場合、その金額は贈与税額控除として相続税から差し引かれます。
そのため、原則として二重課税にはなりません。
8. 生前贈与で失敗しないための実務ポイント
持ち戻し制度を踏まえると、次の点が重要です。
・亡くなる直前の贈与は節税効果が出にくい
・毎年同額・同時期の贈与は「定期贈与」と認定されない工夫が必要
・現金手渡しだけでなく、贈与契約書や振込記録を残す
証拠を残さない贈与は、税務調査で否認されるリスクがあります。
9. よくある質問(FAQ)
Q1. 110万円以下の贈与でも持ち戻しされますか?
はい。加算対象期間内であれば、贈与税がゼロでも加算対象になり得ます。
Q2. 7年になるのはいつからですか?
相続開始日(死亡日)によって段階的に適用されます。最終的に令和13年1月1日以降の相続開始分から7年基準になります。
Q3. 延長分の100万円控除は毎年使えますか?
いいえ。延長された部分(3~7年前)の贈与について、合計で総額100万円まで加算しないという仕組みです。
Q4. 相続時精算課税の贈与も同じように持ち戻しされますか?
相続時精算課税は暦年課税とは別制度であり、持ち戻しの考え方も異なります。制度ごとに扱いが違うため混同しないよう注意が必要です。
まとめ
生前贈与加算(持ち戻し)は、
・加算対象期間が3年から7年へ拡大
・110万円以下でも対象
・延長部分は総額100万円まで加算しない
・贈与税額は相続税から控除
という制度です。
相続税対策として生前贈与を行う場合は、「110万円以内なら安心」と考えるのではなく、死亡日を基準とした持ち戻し期間を前提に設計することが重要です。
【お役立ちコンテンツ】
相続相談はどこにするべき?専門家(税理士、司法書士、弁護士)の強み
【クレアスの相続税サービス】

監修
中村亨
日本クレアス税理士法人 代表
税理士
公認会計士
2002年8月に会計事務所として創業、2005年には税理士事務所を開業し、法人や個人のお客様の会計・税務の支援をする中で、「人事労務の問題を相談をしたい」「事業承継を検討している」といったお客様のニーズに応える形でサービスを拡大し続け、現在では社会保険労務士法人など複数の法人からなるグループ企業に成長してきました。お客様に必要なサービスをワンストップで提供できることが当社の強みです。