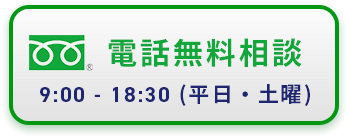遺贈とは?相続との違い、メリット・デメリットを解説
遺贈では、法定相続人でない親族や第三者に対して、財産を取得する権利を与えることができます。遺贈の相手を、法人とすることも可能です。
孫やお世話になった友人など、法定相続人以外の人に財産を遺すことができ、被相続人の想いを実現できる手段となり得る遺贈ですが、トラブルを回避するために注意しなければならない点もあります。
今回のコラムでは、遺贈についての理解を深めるために、遺贈と相続との違い・遺贈のメリットとデメリットを詳しくご紹介します。
1.遺贈とは?
遺贈とは、遺言によって個人の財産を承継させることです。遺贈によって財産を取得する人のことを「受遺者」といいます。
遺贈の最大の特徴は、法律上、相続人でない人にも財産を遺せるという点です。
被相続人(亡くなった人)の財産を相続する権利があるのは、法定相続人といって、法律で決められた親族の一部に限られます。
法定相続人にあたる親族とは、被相続人の配偶者と子、子がいなければ、直系尊属→兄弟姉妹の順で法定相続人になります。具体的には、次のとおりです。
| 法定相続人 | ||
| 第一順位 | 子 | 配偶者 (常に法定相続人になる) |
| 第二順位 | 直系尊属 | |
| 第三順位 | 兄弟姉妹 | |
しかし、亡くなった後の財産の行方は、故人の意思も尊重されるべきです。
「法定相続人ではないけれど、病気の妹にも財産を遺したい」、「婚姻していないけれど、一緒に過ごしてきたパートナーにも財産を遺したい」・・・など相続順位の低い親族や親族関係のない相手にも財産を遺したいというケースがあるでしょう。
このようなケースでは、遺言によって、法定相続人でない相手に財産を遺贈するという選択肢があります。
以下では、相続との違いや共通点を比較し、遺贈がどのようなものであるか理解を深めていきます。
2.遺贈と相続の違い
まずは、遺贈と相続の違いから確認していきましょう。
①遺贈は法定相続人以外の相手に財産を取得させることが可能
相続では、遺言がなければ、法定相続人がそれぞれの法定相続分に基づいて遺産分割協議を行い、相続した財産を振り分けます。したがって、何もしなければ法定相続人以外の人に、財産を取得する権利はありません。
これに対し遺贈では、法定相続人でない親族や第三者に対して、財産を取得する権利を与えることができます。遺贈の相手を、法人とすることも可能です。
②遺贈は遺言を行うことが必要
遺贈は、遺言によって行う必要があります。
遺言は、年齢が15歳に達しなければ行うことができませんので、遺贈もまた15歳を迎えた人しかできないことになります。また遺言をするときは、遺言の内容を理解し判断できる能力をもちあわせていることも必要です。
これに対し相続は、遺言によって行うこともできますし、遺言がなくても成立します。
<参考:「相続させる」遺言とは>
遺言書に、「長男A(法定相続人)に◯◯を相続させる」と書かれている場合、これは、相続と遺贈のどちらになるでしょうか。
答えは「相続」です。
この場合、長男Aに◯◯を相続させるという遺産分割の方法が指定されたものとして扱われ、長男Aは遺産分割協議を行うことなく、ただちにその財産を承継します。
「相続させる」遺言には、遺贈ではなく相続として扱われることによって相続登記や農地の承継手続きがスムーズになるといったメリットがあります。
こうした状況から、法定相続人に遺言で財産を承継させる場合は「相続する」と書くことが一般的に推奨されています。ただし、法定相続人でない人に「相続させる」と書いても、それは遺贈になります。
③相続登記の申請者が違う
被相続人の不動産を取得した場合、その不動産の登記を申請できる人について、相続と遺贈では考え方が異なります。
不動産を相続したときは、不動産を相続した相続人が登記の申請を行います。相続人1人で登記を申請することも可能です。
これに対し、遺贈の場合は、受遺者だけでは登記ができず、登記義務者と共同して登記を申請しなければなりません。
登記義務者とは相続人全員か、遺言執行者がいる場合は遺言執行者になります。法定相続人以外の人への遺贈のほか、法定相続人への遺贈もこの手続きとなります。
④不動産取得税の扱いが違う
こちらも不動産を取得したケースの話ですが、不動産を取得すると「不動産取得税」といって、都道府県に支払う地方税の納税義務が発生します。税額は、取得した不動産の価格の3%~4%です。宅地はさらに減額されます。
不動産取得税は、相続による取得であれば非課税ですが、遺贈の場合、それが法定相続人以外への「特定遺贈」にあたる場合は、課税の対象になります。
遺贈であっても、「包括遺贈」や法定相続人への「特定遺贈」であれば、非課税です。(「特定遺贈」や「包括遺贈」については後述します。)
⑤遺贈には代襲相続がない
相続では、たとえば被相続人の子が被相続人よりも先に亡くなっている場合、その子供(被相続人の孫)が法定相続人としての地位を引き継ぎます。これを代襲相続といいます。遺贈には、代襲相続は適用されません。
参考コラム:代襲相続と相続放棄 ~ 基本的なルール(子・兄弟姉妹・養子)について
たとえば遺言では「B子(知人)に100万円を遺贈する」としているのにB子が被相続人より先に亡くなっている場合、B子の子供がその地位を引き継ぐということはありません。 この場合、遺贈の権利は失効します(民法第994条)。また、失効した権利は、原則、法定相続人に帰属します(第995条)。
3.遺贈と相続の共通点
続いて、遺贈と相続の共通点を確認しましょう。
①被相続人の死亡によって効力が発生する
遺贈も相続も、被相続人の死亡によって効力が発生します(民法第882条、第985条第1項)。
なお、遺贈・相続ともに、遺言に停止条件を付けることによって、効力が発生するタイミングを変えることが可能です。停止条件付きの遺言とは、たとえば「長男Aが医師になったら病院を譲る」というような遺言になります。この場合は、その条件が成就したとき、つまり長男Aが医師になったときから効力を生じます(民法第985条第2項)。
②相続税の対象になる
税法上、遺贈は相続と同じ相続税の課税対象になります。 相続税は、亡くなった人から生存している人への財産の移転を課税対象とするため、その原因が相続・遺贈のどちらであっても、公平に課税されます。
相続税は、法定相続人や受遺者が取得した財産の総額から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いた額をもとに計算されます。
参考コラム:相続税はいくらからかかるのか?節税対策の必要性と金額の計算方法
③遺贈も相続も「放棄」できる
相続を放棄するには、自己のために相続のあったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の申述を行います。
遺贈も、相続と同じように放棄することが可能です。 遺贈が「包括遺贈」である場合は、相続と同様に自己のために遺贈があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所で放棄の手続きを行います。
これに対し遺贈が「特定遺贈」であれば、遺言者の死亡後いつでも遺贈を放棄できるものとされています(民法第986条)。
4.包括遺贈と特定遺贈
遺贈を検討する際に、必ず知っておかなければならないのが、「包括遺贈」と「特定遺贈」です。遺言を行うときは、このどちらかで遺贈を行うことになります。
包括遺贈と特定遺贈の違いは、マイナスの財産を承継するかどうかがポイントになります。
参考コラム:包括遺贈と特定遺贈の違い
4-1.包括遺贈の特徴
「包括遺贈」とは、遺贈する財産を特定せず、割合で財産を取得させる遺贈のことです。
たとえば「◯◯に財産の2分の1を遺贈する」というような遺言になります。
包括遺贈を受けた場合、受遺者は相続人と同じ権利と義務を承継するものとされます(民法第990条)。相続人の権利義務とは、被相続人の財産に属した一切の権利義務のことです(民法第896条)。
このことから包括受遺者になると、被相続人のプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も承継しなければなりません。
ただし、突然マイナスの財産まで背負うことになるというのは酷ですので、包括受遺者は、相続と同様に、単純承認・限定承認・包括遺贈の放棄を選択することができます。
特に何もしなければ、自己のために遺贈があったことを知ったときから3ヶ月が経過すると、単純承認が自動的に成立します。
また、包括遺贈によって財産の一部を承継した人は、相続人とともに遺産分割協議にも参加することになります。
4-2.特定遺贈の特徴
「特定遺贈」とは、特定の財産を相手に取得させる内容の遺贈のことです。
たとえば「◯◯に現金100万円を遺贈する」というような遺言による遺贈が該当します。
特定遺贈であれば、指定された財産のみを取得し、マイナスの財産は承継しません。また、期間経過によって単純承認が自動的に成立することもありません。
しかし、他の相続人からすれば、受遺者に遺贈を受けるのかどうかはっきり示してもらわなければ困ります。そのため相続人から受遺者に対し、相当の期間を定めて、遺贈を承認するのかどうか決めるよう催告することができます。もし定めた期間内に受遺者が意思表示をしなければ、遺贈を承認したものとみなされます。(民法第987条)
なお、特定遺贈を受けた人は遺産分割協議に参加することなく、遺言で指定された財産を取得することができます。(法定相続人でありながら特定遺贈を受けた場合は、法定相続人の立場で遺産分割協議に参加することは当然ありえます。)
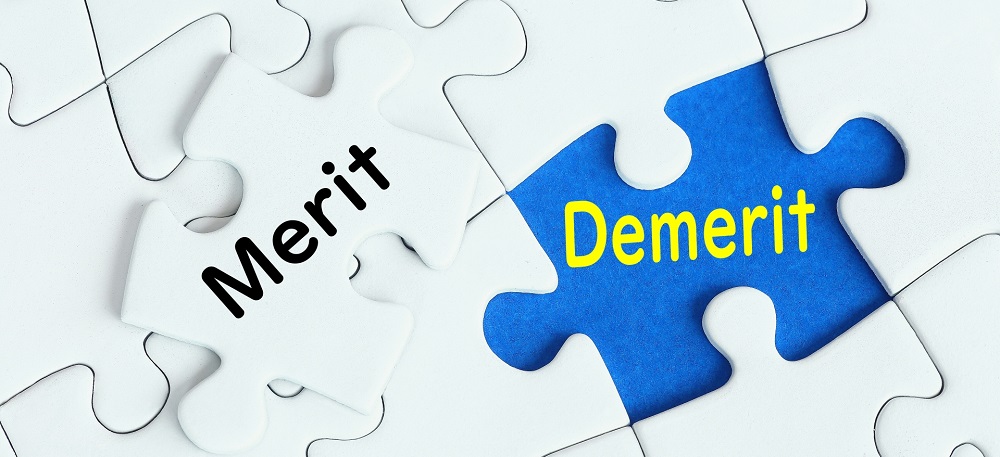
5.遺贈のメリットとは?
遺贈には、相続と比較してさまざまなメリットがあります。
①法定相続人でない孫にも財産を渡せる
相続では、法定相続人以外の相手に財産を遺すことはできませんが、遺贈であれば、お孫さんなど法定相続人でない親族や親族関係のない恩人などにも、財産を遺すことができます。
財産を遺すことで生前の感謝の気持ちなどを伝えるなど、自身の想いを実現することができるでしょう。
②亡くなるまで遺贈のことを秘密にできる
法定相続人以外の相手に財産を遺そうとしていることを、家族には知られたくないケースもあると思います。その場合、たとえば養子縁組をして相続させるといった、オープンな方法は活用しづらいものです。
遺贈であれば、自身が遺言の内容を漏らしたり、家族に遺言書の中身を見られたりすることのないように注意すれば、自身が亡くなるまで家族に知られることはありません。
遺言の方法には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種がありますが、どれも家族に内容を知られることなく作成できます。
<参考:遺言の種類>
| 自筆証書遺言 | 遺言者が自筆で作成する。 令和2年7月10日から、法務局に保管を申請できる。 |
| 公正証書遺言 | 公証役場で公証人に作成してもらう。 作成時は証人2名以上が立ち会う。 原本は公証役場で保管され、遺言者は正本や謄本を保管する。 |
| 秘密証書遺言 | 遺言者が作成した遺言書を、公証人らが封をし、その存在を証明してもらう。 |
参考コラム:自筆証書遺言書の正しい書き方を種類別、ケース別で解説
6.遺贈のデメリットはある?
遺贈には、相続にはない問題が生じることもあります。
①法定相続人と争いになることも
遺贈によって受遺者に特定の財産を取得させれば、当然、他の法定相続人の相続財産が減ります。それによって他の法定相続人から「うまく取り入って、遺言書を書かせたのではないか」といった疑念を抱かれ、感情のもつれから争いになることが考えられます。
また、遺贈の場合は遺言が必要ですので、納得のいかない遺贈が行われれば、その遺言の効力について争いになることもあります。
問題になりやすいのは、遺言のときに遺言能力があったかどうか、また遺言書の書式に不備はないかといった点です。たとえば認知症の方の遺言は、遺言能力が問題視されやすい典型となります。
また、文面を自作する自筆証書遺言、秘密証書遺言は、内容に誤りがないか、書式の法定要件を満たしているかに十分注意が必要です。
②遺留分を主張されることがある
法定相続人でない相手に、法定相続人よりも多く財産を遺贈したいという方もいらっしゃるかもしれません。
このようなときに問題となるのが、法定相続人のもつ「遺留分」です。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた最低限の財産を請求できる権利をいいます。
それぞれの遺留分は次のようになります。
| 法定相続人 | 遺留分 |
| 配偶者 | 相続財産の2分の1 |
| 子 | |
| 配偶者 + 子 | |
| 配偶者 + 直系尊属 | |
| 直系尊属 | 相続財産の3分の1 |
直系尊属のみが法定相続人となるケースを除き、相続財産の2分の1が遺留分です。遺留分のある法定相続人が複数人いるときは、遺留分をさらに法定相続分で分けます。
たとえば、相続財産が1億円で、法定相続人が妻と長男、次男の計3名のとき、それぞれの遺留分は次のとおりです。
・妻の遺留分
1億円×2分の1(全体の遺留分)×2分の1(妻の法定相続分)=2,500万円
・長男の遺留分
1億円×2分の1(全体の遺留分)×4分の1(長男の法定相続分)=1,250万円
・次男の遺留分
長男に同じ
遺贈によって法定相続人の遺留分が侵害された場合、法定相続人は受遺者に対して、遺留分に相当する財産の請求(遺留分侵害額(減殺)請求)を行う権利があります。
たとえば、被相続人である夫が遺言で「全財産をC子(愛人)に遺贈する」とした場合、妻、長男、次男は、C子に、それぞれの遺留分に相当する財産を渡すよう請求することができるということです。
遺留分には満たないけれどいくらか財産を相続しているときは、相続した財産をそれぞれの遺留分から差し引いた額を請求できます。この請求が行われた場合、C子は、遺留分を侵害した額を負担することとなります。
つまり遺留分のことを知らずに遺贈をすると、思い通りの遺贈が実現しない可能性が高いということです。
ただし、遺留分を侵害する遺贈が無効というわけではありません。また、遺贈の実現が妨げられないよう、遺言書の書き方を工夫する方法もあります。
「法定相続人でない人に多くの財産を遺贈したい」、「特定の法定相続人にだけ多くの財産を遺贈したい」といった場合は、相続の専門家に相談することをお勧めします。
<参考:遺留分の注意点>
前述のとおり、多くのケースで遺留分は、相続財産の2分の1となります。
「それなら2分の1までは自由に遺贈できる」となるわけですが、いくつか注意点があります。
まず遺留分を計算する基礎となる「相続財産」とは、被相続人が亡くなったときの財産に、相続開始前の一定の期間に行われた贈与の額を加え、さらに債務の全額(借金など)を差し引いたものとなります。
また、それぞれの遺留分を計算する際にも、各人が受けた遺贈や特別受益にあたる贈与の額を控除したり、各人が承継する債務があればそれを加算するといった調整が行われます。
単に、亡くなったときの財産の2分の1では判定されないので、注意が必要です。
③登記や相続税の申告がやりづらいことも
感情のもつれがあると、法定相続人の協力が必要となる受遺者の手続きがスムーズにできなくなってしまうおそれがあります。
前述のとおり、遺贈によって不動産を登記するときは、受遺者と登記義務者の共同申請が必要です。登記義務者とは相続人全員のことですので、受遺者のことをよく思わない者がいれば、協力が得られないおそれがあります。
そうならないよう、遺言執行者をあらかじめ遺言書で指定しておくといった対策が考えられます。
また遺贈には相続税がかかり、相続税の申告や納税は、他の法定相続人の情報が不可欠ですが、これも双方の関係が険悪になるとスムーズにいかなくなるため注意が必要です。
④相続税の2割加算に注意
配偶者と一親等内の血族以外の人が相続や遺贈によって財産を取得し、相続税が発生した場合、その相続税額は、通常の2割加算(つまり1.2倍)になるというルールがあります。一親等の血族とは、被相続人の実親や子です。
つまり祖父母や孫、兄弟姉妹、配偶者の家族、親族でない第三者は、相続税の2割加算の対象となります。(代襲相続で子の代わりに相続人となった孫は、加算の対象にはなりません。)
相続も遺贈も、要件に該当すれば2割加算の対象ですが、通常、法定相続人以外の相手に財産を取得させる目的で活用されやすい遺贈の方が、2割加算の対象となることが多いといえます。
7.まとめ
この記事では、
・遺贈と相続の違い
・遺贈を行うメリット・デメリット
について解説しました。
遺贈は、法定相続人以外の人に財産を遺すことができ、被相続人の想いを実現できる手段となり得ます。しかし、他の法定相続人の遺留分のことや、遺贈によって財産を受け取った後の受遺者の手続きについて理解していないと、かえって遺贈を受けた人につらい思いをさせるかも知れません。
特定の方に財産を渡したいときは、トラブルを回避するために注意しなければならない点もあるため、今回のコラムで紹介したメリット・デメリットを十分に把握し、必要に応じて相続経験が高い専門家に相談すると良いでしょう。
日本クレアス税理士法人
執行役員 税理士 中川義敬
2007年 税理士登録(近畿税理士会)、2009年に日本クレアス税理士法人入社。東証一部上場企業から中小企業・医院の税務相談、税務申告対応、医院開業コンサルティング、組織再編コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、経理アウトソーシング決算早期化等に従事。事業承継・相続対策などのご相談に関しては、個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業承継」、「争続にならない相続」のアドバイスを行う税理士として定評がある。(プロフィールページ)
・執筆実績:「預貯金債券の仮払い制度」「贈与税の配偶者控除の改正」等
・セミナー実績:「クリニックの為の医院経営セミナー~クリニックの相続税・事業承継対策・承継で発生する税務のポイント」「事業承継対策セミナー~事業承継に必要な自己株式対策とは~」等多数
【お役立ちコンテンツ】
相続相談はどこにするべき?専門家(税理士、司法書士、弁護士)の強み
【クレアスの相続税サービス】