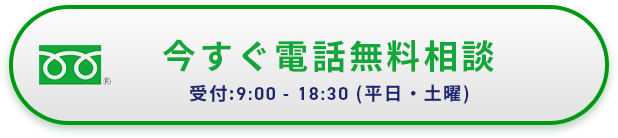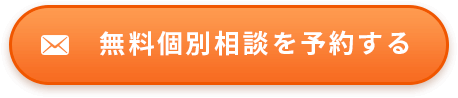5,000万円の遺産で払う相続税はいくら?早見表や計算方法を解説!

監修
中村亨
日本クレアス税理士法人 代表 税理士 公認会計士
【結論】遺産5,000万円の相続税は、配偶者の有無と法定相続人の人数で大きく変わります。配偶者+子2人なら目安10万円、配偶者のみなら税額0円(ただし申告が必要なケースあり)です。
「遺産が5,000万円くらいあるけど、相続税はいくらかかるの?」という不安はとても多いです。
結論からいうと、相続税は家族構成(法定相続人の人数)や配偶者の有無で大きく変わります。
この記事では、まず5,000万円の相続税の目安を早見表で提示し、そのうえで相続税がかかるかどうかの判定方法、計算手順、申告期限や注意点までまとめて解説します。
※本記事の金額は、一定の前提に基づく概算です(前提は各表の注記を参照)。
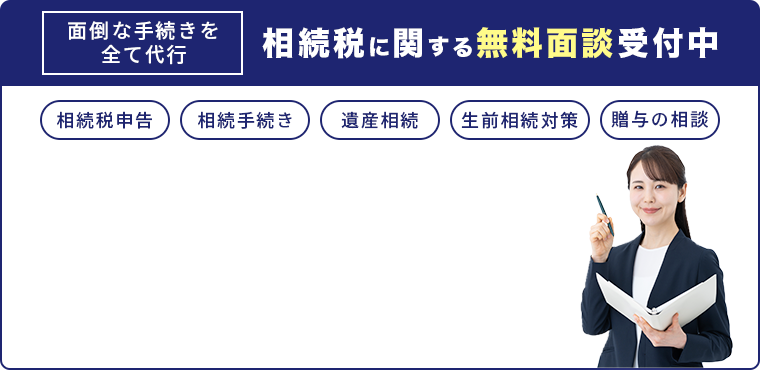
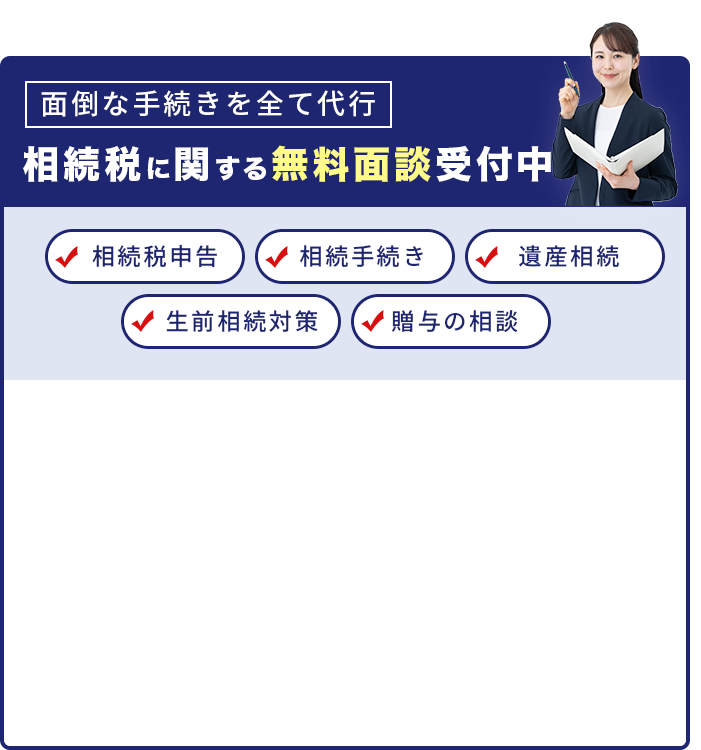
目次
1. 【結論】遺産5,000万円の相続税 早見表(家族構成別)

ここでいう「遺産5,000万円」は、相続税の判定に使う正味の遺産額(課税価格の合計額)を想定しています。
正味の遺産額は、遺産総額から非課税財産・葬式費用・債務を控除し、一定の生前贈与等を加算した金額です。
前提(この早見表の見方)
(1)遺産分割は「法定相続分どおり」
(2)配偶者がいる場合は「配偶者の税額の軽減」を適用
(3)未成年者控除など、他の税額控除・特例は入れていません
(4)万円単位で四捨五入(概算)
| 法定相続人(例) | 相続税の目安(遺産5,000万円) | 補足 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 0円 | 配偶者の税額軽減により、一定額まで配偶者に相続税はかかりません(ただし申告が必要になるケースがあります) |
| 配偶者+子1人 | 40万円 | 配偶者は軽減で0円、子に課税が残るイメージです |
| 配偶者+子2人 | 10万円 | 子が2人だと基礎控除が増え、税額も下がりやすいです |
| 配偶者+子3人 | 0円 | 法定相続人4人の場合、基礎控除が5,400万円となり、5,000万円は基礎控除内です |
| 子1人(配偶者なし) | 160万円 | 相続人が少ないほど基礎控除が小さくなり、税額が上がりやすいです |
| 子2人(配偶者なし) | 80万円 | |
| 子3人(配偶者なし) | 20万円 |
※配偶者の税額軽減は、配偶者が実際に取得した正味の遺産額が「1億6,000万円」または「法定相続分相当額」のいずれか多い金額まで、配偶者に相続税がかからない制度です。
参考:国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減
2. まずは判定:相続税が「かかるかどうか」は基礎控除で決まる
相続税は、正味の遺産額が基礎控除額を超えるときに、超えた部分(課税遺産総額)に課税されます。
2-1. 基礎控除額の計算式
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
法定相続人の人数ごとの基礎控除額は、ざっくり次のとおりです。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
ポイント
「遺産が5,000万円」と聞くと高額に見えますが、法定相続人が4人(配偶者+子3人など)なら、基礎控除が5,400万円になるため、そもそも相続税の申告・納税が不要となるケースがあります。
関連記事:相続税の基礎控除の考え方と非課税枠まとめ
3. 相続税の計算方法(全体像)

相続税は「各人が実際に取得した金額に、いきなり税率をかける」計算ではありません。
まず課税遺産総額を法定相続分で分けて税率を当て、いったん相続税の総額を出してから、実際の取得割合に応じて各人に按分します。
大まかな流れは次のとおりです。
① 正味の遺産額(課税価格の合計額)を出す(債務・葬式費用控除、生前贈与加算などを反映)
② 基礎控除を差し引き、課税遺産総額を出す
③ 課税遺産総額を法定相続分で按分し、各按分額に相続税の速算表(税率・控除額)を当てる
④ ③を合計して、相続税の総額を出す
⑤ 相続税の総額を、実際の取得割合で各人に按分し、配偶者の税額軽減などの控除を適用する
4. 【計算例】遺産5,000万円を「配偶者+子2人」で相続する場合(相続税10万円の根拠)

前提:遺産分割は法定相続分どおり(配偶者1/2、子は各1/4)、他の控除は使わないものとします。
4-1. 基礎控除を計算
法定相続人は3人(配偶者+子2人)です。
基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円
4-2. 課税遺産総額を計算
課税遺産総額 = 5,000万円 − 4,800万円 = 200万円
4-3. 法定相続分で按分し、税率を当てる
按分額は次のとおりです。
配偶者:100万円
子:50万円
子:50万円
税率はいずれも1,000万円以下のため10%とします。
算出税額
配偶者:100万円 × 10% = 10万円
子:50万円 × 10% = 5万円
子:50万円 × 10% = 5万円
合計:20万円
4-4. 各人に按分 → 配偶者の税額軽減を適用
按分後、配偶者には「配偶者の税額軽減」を適用できるため、配偶者分が0円になります(一定額まで)。
その結果、納付税額の合計は10万円程度になります。
5. 遺産総額別:相続税の早見表(概算)
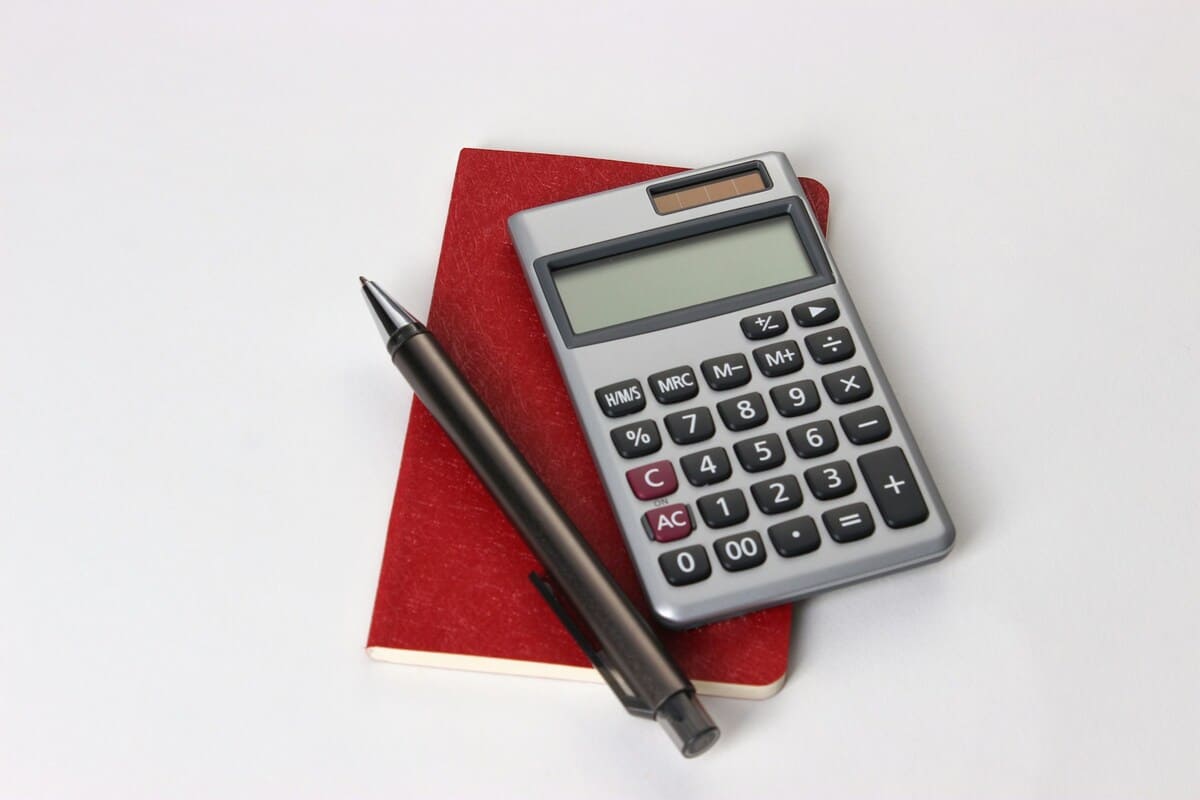
「5,000万円以外も見たい」という方向けに、遺産総額別の目安も掲載します(万円単位で四捨五入)。
※遺産分割は法定相続分どおり、配偶者がいる場合は配偶者の税額軽減を適用、他の控除・特例は未考慮です。
※表内の遺産総額は、課税遺産総額からマイナスの財産を差し引いた正味の財産を前提としています。
5-1. 配偶者+子1人の場合(配偶者1/2、子1/2)
| 遺産総額 | 相続税 |
|---|---|
| 5,000万円 | 40万円 |
| 6,000万円 | 90万円 |
| 7,000万円 | 160万円 |
| 8,000万円 | 235万円 |
| 9,000万円 | 310万円 |
| 1億円 | 385万円 |
| 1.5億円 | 920万円 |
| 2億円 | 1,670万円 |
| 3億円 | 3,460万円 |
| 5億円 | 7,605万円 |
| 10億円 | 1億9,750万円 |
| 30億円 | 7億4,145万円 |
5-2. 配偶者+子2人の場合(配偶者1/2、子1/4ずつ)
| 遺産総額 | 相続税 |
|---|---|
| 5,000万円 | 10万円 |
| 6,000万円 | 60万円 |
| 7,000万円 | 113万円 |
| 8,000万円 | 175万円 |
| 9,000万円 | 240万円 |
| 1億円 | 315万円 |
| 1.5億円 | 748万円 |
| 2億円 | 1,350万円 |
| 3億円 | 2,860万円 |
| 5億円 | 6,555万円 |
| 10億円 | 1億7,810万円 |
| 30億円 | 7億0,380万円 |
5-3. 子1人(配偶者なし)の場合
| 遺産総額 | 相続税 |
|---|---|
| 5,000万円 | 160万円 |
| 6,000万円 | 310万円 |
| 7,000万円 | 480万円 |
| 8,000万円 | 680万円 |
| 9,000万円 | 920万円 |
| 1億円 | 1,220万円 |
| 1.5億円 | 2,860万円 |
| 2億円 | 4,860万円 |
| 3億円 | 9,180万円 |
| 5億円 | 1億9,000万円 |
| 10億円 | 4億5,820万円 |
| 30億円 | 15億5,820万円 |
6. 5,000万円でも要注意:相続税が増減しやすいポイント

同じ「5,000万円」でも、次の要素で相続税が変わります。
(1)配偶者の税額軽減を使えるか(申告・分割状況で扱いが変わる)
(2)生命保険金・死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人など)
(3)小規模宅地等の特例(土地評価を最大80%減額できる場合)
(4)相続開始前の生前贈与が加算対象になるケース
7. 相続税の申告期限・納税期限は「10か月以内」
相続税の申告は、原則として死亡を知った日の翌日から10か月以内です。申告が必要な場合、納税も申告期限までに行います。
また、相続税は金銭で一度に納めるのが原則ですが、要件を満たせば延納・物納制度を利用できる場合があります。
申告遅れ・過少申告は加算税・延滞税の対象になるため、期限が近い場合は早めに専門家へ相談することをおすすめします。
関連記事:相続税の追徴課税・ペナルティまとめ
8. よくある質問(FAQ)
Q1. 遺産が5,000万円なら必ず相続税がかかりますか?
いいえ。法定相続人の数によって基礎控除額が変わり、5,000万円が基礎控除内になることもあります(例:配偶者+子3人なら基礎控除は5,400万円です)。
Q2. 配偶者が相続すれば相続税は0円になりますか?
配偶者が実際に取得した正味の遺産額が「1億6,000万円」または「法定相続分相当額」までなら、配偶者の相続税が軽減されます。
ただし、分割が申告期限までに確定していない場合は扱いが変わるため注意が必要です。
Q3. 申告しないとどうなりますか?
申告期限までに申告しない場合や、少ない額で申告した場合、加算税・延滞税がかかることがあります。
9. まとめ:5,000万円の相続税は「家族構成」で大きく変わる
遺産5,000万円の相続税は、同じ金額でも次の要素で大きく変わります。
(1)配偶者がいるか
(2)子どもが何人か(法定相続人が何人か)
(3)控除・特例を使えるか
「うちは相続税がかかる?」「配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使える?」など、前提整理だけでも税額が変わるケースが多いので、早い段階で試算しておくのがおすすめです。

監修
中村亨
日本クレアス税理士法人 代表
税理士
公認会計士
2002年8月に会計事務所として創業、2005年には税理士事務所を開業し、法人や個人のお客様の会計・税務の支援をする中で、「人事労務の問題を相談をしたい」「事業承継を検討している」といったお客様のニーズに応える形でサービスを拡大し続け、現在では社会保険労務士法人など複数の法人からなるグループ企業に成長してきました。お客様に必要なサービスをワンストップで提供できることが当社の強みです。