生前整理とは?遺品・老前整理との違いや流れ・メリット・デメリットを解説
生前整理という言葉を耳にしたけれど、内容がよくわからないとお困りではありませんか。
生前整理を実践することで、自身が亡くなった後の相続手続きが楽に進められる、身の回りがすっきりするなどのメリットを得られます。
この記事では、生前整理とは何か、遺品・老前整理とは何が異なるのかを解説します。
生前整理を行うメリットとデメリット、手順も紹介するので、身の回りの物を整理しようと考えている方は参考にしてください。
目次
1. 生前整理とは?

生前整理という言葉を耳にしたけれど、具体的な内容がわからないという方も多いでしょう。
ここでは、生前整理の意味と遺品・老前整理との違いを解説します。
1-1. 老後や介護・相続に向けて現時点での身の回りの物を整理すること
生前整理とは、健康で自身の体が動くうちに、身の回りのものを整理することです。
時間に余裕ができたタイミングで、身の回りの物をすっきりさせれば、老後の負担を減らせます。
また、身の回りの物を片づければ、所持している財産の把握も可能です。
財産リストを作成すれば、自身が亡くなった後の相続手続きもスムーズに進むため、今後のことを考えるのであれば早めに片づけを始めることがおすすめです。
1-2. 遺品・老前整理との違い
生前整理と似た言葉に、遺品整理と老前整理があります。それぞれ何が異なるのかをまとめました。
|
整理する人 |
実施する目的 |
時期 |
整理する内容 |
|
|
生前整理 |
自分 |
老後や亡くなった後のことを考え、身の回りをすっきりさせる |
子どもが独立した後や定年退職後 |
身の回りの物を整理したり、処分する、遺言書を作成する |
|
老前整理 |
自分、または親族 |
自分の身の回りをすっきりさせ、老後や相続に備える |
高齢になる前 |
身の回りの物を整理したり、処分する、遺言書を作成する |
|
遺品整理 |
親族 |
亡くなった人の身の回りのものを整理し、故人を悼む |
亡くなった後 |
財産の把握、遺品の処分、相続の手続きなど |
生前・老前整理は内容が似ているものの、片づける人や実施するタイミングが異なります。
遺品整理は亡くなった後に遺族が身の回りの物を片付けるので、内容が大きく異なると考えておきましょう。
2. 生前整理を行う3つのメリット

定年退職後に時間の余裕ができたから身の回りの物を片付けようと考えているけれど、生前整理にはどんなメリットがあるの?と気になっている方も多いでしょう。
ここで実施することでのメリットを挙げるので、いい点を確認したうえで始めてみてください。
2-1. 相続発生時の遺族への負担を抑えられる
生きている間に周辺のものを片付ければ、相続発生後の遺族の負担を抑えられます。
自身の身の回りを一切片付けずに亡くなった場合、遺族が遺品整理を行います。
物が多いほど整理する手間がかかり、処分するものも多くなるため、処分費用も高額になるでしょう。
何を持っているかを大体把握している本人が生前整理を行うことで、効率よく片づけることが可能です。
自身で片付ければ、これまでに形成してきた大切な財産を残すことが可能です。
価値のある財産をリストにまとめておけば、相続発生時の遺族の負担も軽くできるでしょう。
2-2. 老後の生活に向けて身の回りをすっきりさせられる
早めに身辺を整理しておけば、必要なものだけを残した快適な生活を送れます。
子育て中や仕事をしているときは、身の回りのものがどんどん増え、片づける暇もないでしょう。
育児や仕事が一段落すれば、今後の生活に必要なものは何かをゆっくりと考えられます。
若いころは必要だったものも、老後になれば不要になります。
体が元気に動くうちに不要なものをまとめて処分すれば、部屋の中が一気に片付くでしょう。
2-3. 相続トラブルを防げる
生きている間に身辺を整理し、所有財産を把握することで相続トラブルを防げます。
どのような財産を持っているかは、本人でなければ分かりません。
なかには、本人が忘れている財産もあるため、生前整理で所有する財産を洗い出すことがおすすめです。
あらかじめ身辺を片付けることで、亡くなった後に隠し財産が見つかる心配はありません。
親族にどのような財産があるかを伝えることで、相続が近づいてきたころに、何の財産を受け継ぐかを親族間で話し合えます。
財産を渡す相手を選びたいときは、財産リストを親族に共有せず、遺言書を作成しましょう。
遺言書に所有する財産と渡す相手を記載しておけば、亡くなった後に遺族間で揉めることもありません。
3. 生前整理を行う2つのデメリット

元気なうちに身辺の整理を行うと、さまざまなメリットが得られます。
しかし、その一方で気をつけておきたいデメリットもあるので気をつけましょう。
3-1. 物の量によって体に大きな負担がかかる
身の回りの整理は1日では終わらず、体力的にも大きな負担がかかります。
これまで特に身辺の片付けをしてこなかった方は、家中に物があふれているのではないでしょうか。
たくさんのものを必要・不要で分け、不要なものの処分に多大な時間と労力を費やさなければなりません。
不要なもののなかには、重たいものや大きいものもあるでしょう。
粗大ゴミシールを買いに行く手間に加え、ゴミ捨て場まで持っていく労力も必要なので、ある程度の体力が残っているうちに整理を始めることがおすすめです。
3-2. 処分費用が高くなる恐れがある
大型の家具や家電は処分する際に費用がかかる恐れがあるので、注意が必要です。
大型の家具・家電は、粗大ごみのシールを貼らずとも、処分業者に引き取ってもらえます。
ただし、処分費用を請求されるため、処分する量によっては高額の出費になるかもしれません。
比較的新しい家具や、まだ使える家電であれば、買い取ってもらうことも可能です。
買い取り業者のなかには自宅まで来てくれるところもあるため、売れそうなものは買い取ってもらい、お得に処分するといいでしょう。
4. 生前整理はいつから始めるべき?

体力がなくなる前に生前整理をしておきたいけれど、いつから始めるべき?とお悩みの方も多いでしょう。
身の回りの片付けに最適なタイミングがいくつかあるため、ここで紹介します。
4-1. 子どもが独立したタイミング
子どもが家を出たタイミングで生前整理を行うと、相続時の子どもの負担を減らせます。
子どもが家を出れば、家は大人だけの物になるため、不要なものを片付けやすくなるでしょう。
子どもが実家に残したものはそのままに、自分たちの荷物だけ整理することがおすすめです。
早めに身辺整理をしておくと、何らかの事情で亡くなってしまった後、子どもが遺品整理をする手間を省略できます。
相続時の負担を軽減し、両親から受け継ぐ財産をすぐに把握できるでしょう。
4-2. 定年退職したタイミング
定年退職後、時間にゆとりができたときに始めることもおすすめです。
仕事をしている間は毎日の仕事に追われ、ゆっくりする時間もありません。
しかし、定年退職後は仕事に時間を費やすこともなくなるため、自分のために時間を活用できます。
空いた時間を活用して、身の回りの整理を始めてみましょう。
定年退職後にある程度整理しておくことで、高齢になってから身辺整理をする必要がなくなります。
4-3. 30~40代で始めてもOK
30~40代で生前整理を行う方もいます。
さすがに早すぎるのでは?と思われるかもしれませんが、生前整理に遅い・早いはありません。
人は病気や事故などによって突然亡くなることもあるため、万が一に備えて少しずつ片づけをしておくことがおすすめです。
30~40代だと、整理後にさらに物が増えることもあるでしょう。
資産となるものはリストにまとめ、不要なものはできるだけ増やさないことが大切です。
5. 生前整理の流れ

身の回りの片づけを始めたいけれど、何から手を付ければいいかわからないとお悩みの方も多いでしょう。
たくさんのものがあふれる部屋を見ると、やる気もなくなってしまうかもしれません。
ここでは、生前整理の流れを紹介するので、手順を参考に始めてみてください。
5-1. 身の回りの物を整理する
生前整理は身の回りのものを片付けることが目的なので、必要なものと不要なものを分けていきましょう。
ものには、形あるもの・デジタル機器に入っている情報があり、以下のような特徴があります。
- 形あるもの:家具家電や雑貨など
- デジタル機器に入っている情報:写真や動画、友人・知人の連絡先など
整理をするときは、1部屋ずつ進めていくことが大切です。
全部屋まとめて始めると、必要なものと不要なものが混ざってしまい、整理が難しくなります。
1部屋終わったら次の部屋といった風に、少しずつ進めていきましょう。
まずは、形ある財産から選別します。
大型の家具家電や小さい雑貨など、家の中にはたくさんの形あるものがあふれています。
家具家電はゴミ袋に入りきらないものが多いため、空きスペースに置いておきましょう。
ほかの部屋にある不要な家具家電を集め、量に応じて粗大ごみのシールを購入するか、引き取り業者に任せるかを判断してください。
デジタル機器には、写真や動画、友人・知人の連絡先などのデータが入っています。
万が一のことがあった際、遺品整理のときに遺族がデータを見ることになるため、家族に見られたくないデータは早めに削除しておくことがおすすめです。
5-2. 財産となる貴重品をまとめる
家中を整理し、財産となる貴重品が見つかったら一カ所にまとめることがおすすめです。
貴重品を複数個所に置くと、どこに何があるかがわかりにくくなります。
場合によっては、遺品整理の際に見つからず、時間が経ってから発見されることもあるため、わかりやすい場所にまとめておきましょう。
財産となる貴重品には以下のようなものがあります。
- 通帳
- 銀行に届け出ている印鑑
- 現金
- 保険証書
- 不動産の権利書
これらのものは相続財産となるため、まとめて置いておくことが大切です。
まとめて置くことが不安な方は、金庫に保管しておきましょう。
パスワードを設定しておけば、第三者が解錠して持ち出すこともありません。
5-3. 財産リストを作成する
貴重品をまとめたら、自身が所有する財産をリストにまとめましょう。
生前整理をすることで、自身がどのような財産を持っているかを改めて確認できます。
価値の高い資産を見つける可能性もあるため、資産価値のあるものは厳重に保管することがおすすめです。
所有する財産のリストを作ることで、相続時の遺族の負担を軽減できます。
遺族は財産を探し回ることなく手軽に把握できるため、遺産分割協議もスムーズに進められるでしょう。
6. 効率よく生前整理を進める3つのポイント

生前整理の流れを把握したら、効率よく進めるための3つのポイントも押さえておきましょう。
ここで紹介するポイントを参考に片づけを進めれば、整理にかかる時間を短縮できます。
6-1. 短期間ではなく時間をかけて整理する
生前整理をするときは、一気にやろうとしないことが大切です。
身辺の整理は労力を使うため、早めに終わらせたいと考えるでしょう。
しかし、急ぐあまりに必要なものを不要なものに入れてしまったり、途中で挫折してしまったりする恐れがあります。
時間がかかっても特に急ぐ必要はありません。
ゆっくりと必要・不要なものを選別して、身の回りをすっきりさせていきましょう。
6-2. サポートを得られる場合は家族と一緒に作業を進める
サポートを得られる場合は、家族と一緒に作業することがおすすめです。
配偶者や子どもなどに手伝ってもらうことで、作業効率を高められます。
荷物量が多い、または部屋の数が多い家庭でも、複数人で手分けして進めれば早くに終わるでしょう。
家族と一緒に整理することで、所有する財産の情報を共有できるメリットも得られます。
特に相続の権利を持つ人には事前に伝えておいた方がいいので、整理のついでに所有する財産について話し合っておきましょう。
6-3. 自身での作業が難しい場合は業者に依頼を
時間にゆとりはあるけれど、体力がなく、片づけができない場合は業者に依頼することがおすすめです。
前述したように、生前整理は時間をかけて行う必要があるため、ある程度の体力が必要です。
体力の問題で作業を進められない場合は、専門の業者に依頼するといいでしょう。
生前整理業者は、依頼主と一緒に作業を進めてくれます。
体力の必要な作業はまとめてお任せできるので、依頼主は必要・不要の選別を行うだけで済みます。
家族に頼れず、1人で作業を進めなければならない方も、必要に応じて業者に依頼しましょう。
7. 生前整理の後に考えておきたい相続対策
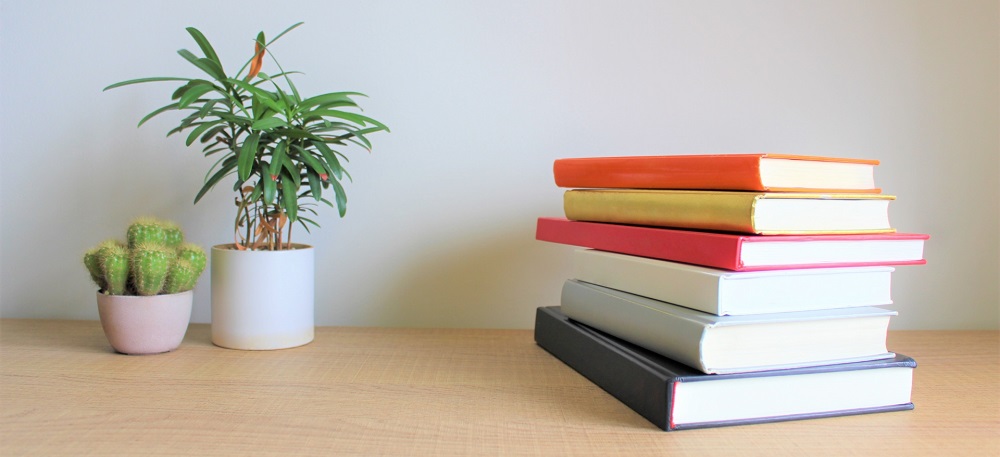
身の回りの整理を思い立った方のなかには、自身が亡くなった後のことまで考えているという人もいるでしょう。
財産を渡す相手を選びたい、できるだけ相続人に負担をかけたくない方は、相続対策を実施しておくこともおすすめです。
ここでは、生前整理が終わってから取り掛かりたい相続対策について解説します。
7-1. 財産の分配先を決めておきたいなら遺言書の作成がおすすめ
財産を渡す相手を選びたい、または遺産分割協議で揉めてほしくないと考える方は、遺言書の作成を検討しましょう。
遺言書がない場合、法定相続分に則って財産が分配されます。
分配内容は遺産分割協議で決まりますが、協議の際、分配先で揉める事例が多々あります。
財産をめぐるトラブルを防ぐためにも、遺言書を残しておくことが大切です。
遺言書があれば、内容通りに財産が分配されるため、遺族間で揉めることはありません。
遺言書は自筆で作成することも可能ですが、確実に内容を実現するためにも、公正証書遺言を作成することが重要です。
公正証書遺言は、公証役場の公証人が作成する書面です。
効力のある遺言書を作成できるので、亡くなった後に内容が反故にされる恐れもありません。
【関連記事】公正証書遺言とは?作り方や作成費用・必要書類を解説
7-2. 財産額の把握で相続税対策も行える
生前整理で大体の財産額を把握したら、相続税対策を実施しましょう。
特に財産はないと思っていたけれど、予想以上にいくつもの資産が見つかったというケースもあるでしょう。
財産額が多くなるほど、相続時の税金負担が高くなるので、額に応じて相続税対策を実施することがおすすめです。
相続税対策としては、生前贈与や特例・非課税措置を活用してお金を贈与する方法などがあります。
特例や非課税措置の適用には要件があるため、満たせる場合は制度を活用して財産を贈与するといいでしょう。
ある程度の財産が見つかったものの、どのように対策すればいいかわからないとお困りの方は、税理士に相談してみてください。
負担なく生前贈与を行うコツや、相続税を抑える方法をアドバイスしてくれます。
8. 生前整理や相続税対策のお悩みは税理士に相談
生前整理とは、老後に向けて身の回りを整理することです。
子どもが独立したときや定年退職のタイミングで実施する人が多い一方で、30~40代から始める人もいます。
体力のあるうちに身の回りを整理することで、家の中をすっきりさせられます。
所有する財産の把握もできるため、相続対策としても有効です。
整理後に財産を把握したら、相続についても考えましょう。
財産を誰に渡すか、配偶者や子どもの相続税負担を掛けないためにはどうすべきかなどを考えることが大切です。
相続税についてのお悩みは、プロにお任せしましょう。
税理士に相談すれば、相続税を抑えるためにできることを教えてもらえます。


