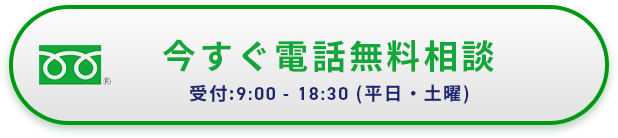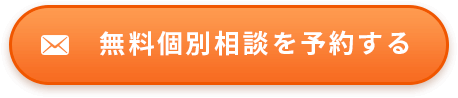【要注意】夫婦間でも贈与税はかかる?非課税のケースとおしどり贈与を税理士が解説

監修
中村亨
日本クレアス税理士法人 代表 税理士 公認会計士
配偶者へのプレゼントや生活費のやりとり、住宅購入資金の援助など、夫婦間でお金や財産が動く場面は日常的にあります。
「夫婦なのだから、いくら渡しても贈与税はかからないはず」と考えてしまいがちですが、実は夫婦間の贈与であっても原則として贈与税の対象になります。
一方で、一定の条件を満たす生活費や教育費であれば非課税とされたり、婚姻期間20年以上の夫婦が使える「おしどり贈与(配偶者控除の特例)」を活用することで、贈与税の負担を大きく抑えられるケースもあります。
反対に、へそくりや高額なプレゼント、配偶者名義の口座への多額の資金移動のしかたによっては、思わぬ贈与税や将来の相続税の対象になってしまうこともあります。
本記事では、夫婦間贈与でも贈与税がかかる基本的な考え方から、非課税となる3つのパターン、おしどり贈与の要件や注意点、贈与税の無申告リスクまで、税理士がわかりやすく解説します。
配偶者への贈与を検討している方や、贈与税・相続税をできるだけ抑えたいとお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。
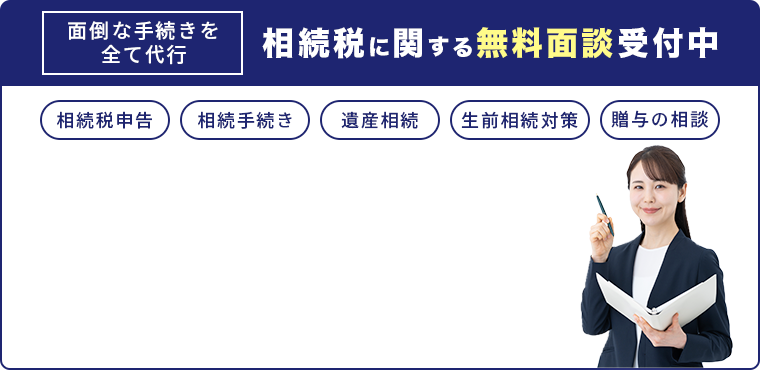
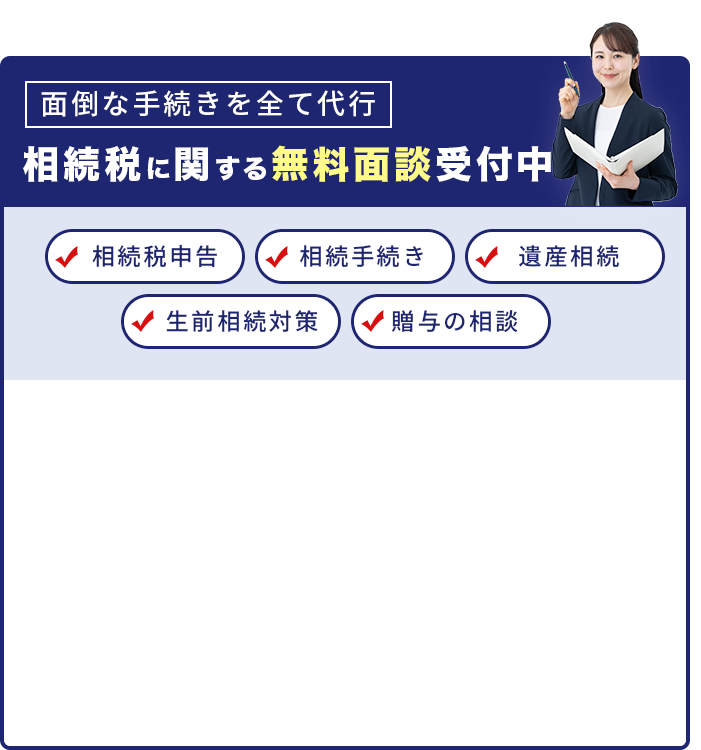
目次
1. 夫婦間贈与でも贈与税はかかる
夫婦間の贈与であっても、原則贈与税がかかります。
夫婦のなかには、一つの財布として家計管理を行なっている家庭もあるため、明確に「この財産は自分のもの」という認識を持っていない方も多いでしょう。
しかし夫婦間の贈与であっても、無償で財産を渡すことは贈与にあたるため贈与税がかかります。
当人たちの意思とは関係なく、客観的な証拠をもとに財産の贈与と税務署が判断した場合には、贈与税の対象となってしまうため注意しましょう。
しかし、通常の贈与と同様に、夫婦間の贈与にも非課税となるパターンがいくつか存在します。
以下では、夫婦間贈与が非課税になるパターンを解説します。
【関連記事】贈与税はいくらからかかる?非課税枠や計算方法をわかりやすく解説
2. 夫婦間贈与が非課税になるパターン
夫婦間贈与が非課税になるのは、下記3つのパターンのいずれかに当てはまるときです。
<非課税パターン>
|
それぞれのパターンについてくわしく解説します。
2-1. 年間110万円以下の贈与
贈与税には年間110万円の基礎控除が設けられているため、110万円以下の贈与であれば贈与税はかかりません。
これは夫婦間に限らず、すべての贈与に適用できる基礎控除です。
実は贈与には「暦年課税制度」と「相続時清算課税制度」の2種類があり、110万円の基礎控除が適用できるのは前者のみとなっています。
ただし、相続時清算課税制度は配偶者に対して利用することはできないため、夫婦間贈与を行う際には暦年課税制度が適用されます。
贈与税をかけずに贈与をしたい、年間で110万円以内でしか贈与を行わないという場合には、暦年課税の基礎控除をうまく活用しましょう。
2-2. 生活・教育費としての贈与
生活・教育費として贈与する場合には、その贈与が高額であっても贈与税はかかりません。
なぜなら国税庁によって、扶養義務者からの生活・教育に関わる贈与は、通常必要と認められるもので贈与税がかからないと規定されているためです。
そのため、配偶者に生活費として月に10万円を渡しているという場合でも、贈与税がかかることはありません。
また、学費や文房具などの教育関連の贈与に関しても同様です。
贈与税について毎年110万円という基礎控除を知っている方のなかには「110万円を超えると贈与税がかかってしまうかも」と不安を覚える方もいるでしょう。
これは誤りで、通常の生活に必要とされる費用については、贈与税が課されることはありません。
2-3. 配偶者控除の特例を利用した贈与
贈与税には、配偶者に対してのみ使用することができる控除が設けられています。
具体的には、配偶者に対して居住用不動産を贈与したときに特例が利用できます。
この特例は「おしどり贈与」とも呼ばれ、婚姻期間の長い夫婦のみが使える特例です。
以下では、おしどり贈与の要件や書類についてくわしく解説します。
3. おしどり贈与とは?20年以上の夫婦が使える特例を解説
おしどり贈与とは、贈与税における配偶者控除の特例のことを指します。
婚姻期間が20年以上の夫婦が利用できる特例で、最大2,000万円の非課税枠が利用できます。
ただし、贈与できる財産は居住用不動産に限られますので注意が必要です。
受贈者(財産を受け取る人)が住むための住居、たとえば現在住んでいる自宅を妻の所有に変更する際などに利用できます。
また、居住用不動産の取得を目的とする場合でも、金銭を贈与する際にこの特例が利用可能です。
おしどり贈与を利用するための要件や書類・条件などについてくわしく見ていきましょう。
3-1. おしどり贈与の特例で求められる要件
おしどり贈与の特例を適用するためには、下記の要件を満たさなければなりません。
<おしどり贈与要件>
|
おしどり贈与では、事実婚といった法律上の婚姻関係にない夫婦間では利用することができませんので注意しましょう。
また、贈与した不動産に翌年の3月15日までに受贈者が住んでいる必要があり、その後も住み続けなければなりません。
たとえば、居住用不動産の取得資金をおしどり贈与を利用して贈与したとします。
その資金で新築を建てるという場合でも、翌年の3月15日までに家が完成し、受贈者が住んでいなければなりません。
そのため節税対策を目的として、誰も住む予定がない不動産を建てる・贈与することはできませんので注意しましょう。
このようにおしどり贈与では「受贈者が住む」という点がとても大切なポイントになっています。
3-2. おしどり贈与の特例適用に必要な添付書類
おしどり贈与の特例を適用には、事前の申請は必要ありませんが、特例を利用したことを添付書類とともに申告しなければなりません。
特例の適用に必要な添付書類は下記のとおりです。
<添付書類>
|
おしどり贈与の利用要件である婚姻期間や、不動産の価額がわかる書類を添付する必要があります。
贈与税の申告時に、これらの書類を添付して申告します。
特例を利用すれば贈与税が0円になるという場合でも、申告は必要になるため注意しましょう。
3-3. 過去に離婚していた場合でもおしどり贈与が使える
おしどり贈与は、過去に離婚していた場合でも利用できます。
大切なのは婚姻期間が20年以上という部分で、過去に離婚をしている場合でも関係はありません。
そのため、特例の利用時に婚姻関係にある、その人との婚姻関係が通算で20年を超えていれば特例が利用できます。
一度離婚したからといって特例が使えなくなることはありません。
しかしおしどり贈与は、同じ人に対し生涯で1回しか使うことができない点には注意が必要です。
別の配偶者であれば可能ですが、同じ人には1回しかおしどり贈与の特例を適用することはできません。
4. 夫婦間贈与で贈与税がかかるパターン
夫婦間贈与であっても贈与税がかかりますが、贈与税がかかるパターンを具体例を用いて解説します。
<夫婦間贈与で贈与税がかかるパターン>
|
それぞれどのような場合に、贈与税がかかるのかみていきましょう。
4-1. 年間110万円を超えるプレゼントなど
夫婦間のプレゼントであっても、年間で110万円を超える場合には贈与税がかかってしまうので注意しましょう。
たとえば、高級な時計を配偶者にプレゼントした場合には贈与にあたるため、110万円を超える部分に対して贈与税が発生します。
車については自分名義で購入して共同で使用する分には問題ありませんが、名義変更などで配偶者の所有物となった際には贈与税が発生します。
なお、婚約指輪など社会通念上必要とされているものについては、贈与税がかかることはありません。
贈与税がかかるか否かは、生活に必要なものであるのか、それとも嗜好品であるのかという観点で判断が行われます。
車に関する贈与税に関して詳しく知りたい方は、下記記事も併せてご覧ください。
関連記事:車を買ってもらうと贈与税がかかる?親子間での譲渡は?節税方法を解説
4-2. 生活・教育費として使わなかった場合
原則、扶養義務者からの生活・教育費については、贈与税がかかることはありません。
しかし例外として、生活・教育費として受け取った金銭を、生活・教育とは別の目的で使用した場合には贈与税が発生します。
たとえば、夫から生活費としてもらっているお金で、株や経済的な価値がある資産を購入した場合には贈与税がかかります。
元々贈与税が非課税であった金銭に対して、贈与税がかかってしまうことになるため注意しましょう。
4-3. 自分が負担していない保険金を受け取る
自分が保険料を負担していない保険金を受け取った場合には、その保険金に対して贈与税が発生します。
たとえば、下記のような場合には妻に対して贈与税が発生します。
<例>
|
なお、妻が自分で保険料を負担して、自分が受け取るという場合には、贈与税は発生しません。
また、生命保険金には贈与税ではなく、相続税がかかる場合があります。
<例>
|
このような場合には、父の死をきっかけに妻が保険金を受け取ることになりますが、その保険金は贈与とはみなされず、相続財産として扱うことになります。
なお、死亡保険金には個別に基礎控除が設けられているため、相続税を抑えられる可能性があります。
4-4. 高額な金銭を配偶者の口座に移動する
夫婦で口座を分けている場合には、配偶者の口座にお金を移すということも日常的に起こり得るでしょう。
生活・教育費と判断される金銭の移動は何も問題ありませんが、数百万円単位の移動になると利用用途について税務署から指摘される可能性が高まります。
そこで、非課税となる使用用途以外にお金を使っていた場合には、贈与税の対象となってしまいます。
知らない間に、無申告になっている場合が多く、その場合にはペナルティの対象になってしまうため注意しましょう。
なお、配偶者が亡くなるまでその金銭を口座内にとどめておいた場合には、相続財産として扱われる可能性があります。
4-5. 不動産の持分割合と出資額に差額がある
夫婦で不動産を共有名義で購入する際などには、その持分割合と出資額に差額があると贈与税がかかってしまう可能性があります。
たとえば、夫の財産で不動産を購入したにも関わらず、持分は半々という場合には、妻に対して贈与税が発生してしまいます。
不動産を購入する際には、出資者の名義にするか、持分割合と出資額を合わせるようにしましょう。
5. へそくりに贈与税がかかることはある?
へそくりとは、家計管理とは別に、誰にも内緒で貯金しているお金のことを指します。
へそくり自体には何も問題ありませんが、へそくりのお金がどこから出ているかによっては贈与税の対象になってしまう可能性があります。
具体的にへそくりに贈与税がかかってしまう場合についてみていきましょう。
5-1. 高額な買い物をすると贈与税がかかる
へそくりで高額な買い物をしてしまった場合には、贈与税がかかる可能性があります。
たとえば、毎月配偶者から生活費として20万円をもらっているうち、5万円をへそくりとして貯めていたとします。
このへそくりで、自分へのご褒美として高級な鞄や時計などを買った場合、その総額が年間110万円を超えていると贈与税が発生します。
なぜなら、生活費としてもらっているお金を嗜好品の購入費用として使っているからです。
一度自分の懐に入ったお金だとしても、元を辿れば配偶者からもらっているお金になります。
自分で稼いでるお金であれば問題ありませんが、出所が配偶者である場合には贈与税の対象になってしまうため注意しましょう。
5-2. 名義預金とみなされ相続税の対象になる
へそくりとして配偶者からもらったお金を貯めている場合には、名義預金とみなされ相続税の対象になる可能性があります。
たとえば、毎月の生活費から5万円をずっと貯金しており、2,000万円貯まっていたとします。
この場合、一見自分の財産のように思えますがお金の出所は配偶者のため、名義預金とみなされ相続税の対象になってしまう可能性が高いです。
口座の名義人とお金の出資者が異なる場合には、へそくりなどでも相続税の対象になってしまうため注意しましょう。
6. 夫婦間贈与は贈与税無申告でもばれない?
贈与税の無申告は、夫婦間で行われた贈与であってもばれてしまう可能性が高いです。
税務署は銀行口座の取引履歴や登記情報などから、贈与税の無申告を疑いさまざまな調査を行います。
無申告が疑われた場合には直接調査が入ることもあり、その段階で無申告がばれてしまうとペナルティの対象になってしまうため注意が必要です。
とくに、意図的に無申告の状態を続けている場合には重加算税の対象となってしまいます。
本来払うはずだった贈与税にくわえ多額の追徴課税金を支払うことになるため、贈与税は正しく申告・納税しましょう。
7. 夫婦間贈与をうまく利用することで相続税対策が可能
夫婦間贈与を活用することで、財産を移動し相続税に備えることが可能です。
夫婦間贈与では110万円の基礎控除にくわえ、20年以上の夫婦であれば最大2,000万円の非課税枠が使えます。
相続できる財産は居住用不動産またはその取得資金に限られますが、うまく活用することで相続税対策が可能です。
たとえば、おしどり贈与を利用して父名義の自宅を妻に贈与するなど。
ただし、使い方を間違えてしまうとかえって相続税が高くなってしまう、相続人同士のトラブルを生んでしまう可能性があるため注意しましょう。
なお、おしどり贈与を利用して相続税対策を行う場合には、取得資金として2,000万円を贈与することがおすすめです。
8. 夫婦間贈与に関するよくある質問(Q&A)
夫婦間贈与についてご相談を受けていると、次のようなご質問をよくいただきます。代表的な疑問をQ&A形式で整理しました。
Q1. 生活費として渡しているお金にも贈与税はかかりますか?
一般的な生活費や教育費として必要な範囲であれば、夫婦間であっても贈与税はかかりません。
例えば、家賃・食費・光熱費・日用品、子どもの学費や塾代など「通常の生活を維持するために必要な支出」は、税法上「扶養義務者からの生活・教育費」として非課税扱いです。
一方、生活費として受け取ったお金を貯めて、高級な時計・バッグ・宝飾品・不動産などの資産に充てると「生活費ではない」と判断され、贈与税がかかるケースがあります。
生活費であることを明確にするため、
・生活費用の口座と貯蓄用の口座を分ける
・高額な買い物の際は資金の出どころを明確にする
といった点を意識しておくと安心です。
Q2. ボーナスや退職金を配偶者の口座に移すと贈与税がかかりますか?
まとまった金額を、対価なく配偶者名義の口座へ移した場合、その金額が年間110万円を超えると贈与税の対象となる可能性があります。
また、移した資金がそのまま使われずに残っている場合、将来の相続時に「名義預金」として相続財産とみなされるリスクもあります。
・生活費として使う分
・将来の共有の目的に使う分(住宅購入、教育費など)
を区別して記録に残しておくことが大切です。
多額の資金移動を検討している場合は、贈与税だけでなく相続税も踏まえて専門家へ相談するのがおすすめです。
Q3. おしどり贈与(配偶者控除)はどんなときに使うのがよいですか?
おしどり贈与は、婚姻期間20年以上の夫婦が「居住用不動産またはその取得資金」を贈与する場合に使える特例で、最大2,000万円が非課税になります。
次のようなケースでよく利用されます。
・夫名義の自宅を、将来の安心のため妻名義にしたい
・老後も住み続ける自宅について、配偶者名義を確保したい
ただし、
・同じ配偶者に対する適用は一生に一度だけ
・居住用不動産にしか使えない
・相続全体のバランスによっては、かえって相続トラブルの原因になることも
などの注意点があります。
夫婦間贈与を相続税対策として活用する場合は、贈与税と相続税の両面から最適な方法を検討する必要があります。
9. 夫婦間でも贈与税はかかる!非課税枠を活用しよう
ここまで夫婦間贈与について、特例や非課税枠などを解説してきました。
たとえ夫婦間の贈与であっても、基礎控除を超える部分に関しては贈与税が発生します。
そのため、高級な時計などの嗜好品をプレゼントするといった場合には注意しましょう。
どのような場合に贈与税がかかるのか、贈与税の申告方法がわからない方は税理士に相談することがおすすめです。

監修
中村亨
日本クレアス税理士法人 代表
税理士
公認会計士
2002年8月に会計事務所として創業、2005年には税理士事務所を開業し、法人や個人のお客様の会計・税務の支援をする中で、「人事労務の問題を相談をしたい」「事業承継を検討している」といったお客様のニーズに応える形でサービスを拡大し続け、現在では社会保険労務士法人など複数の法人からなるグループ企業に成長してきました。お客様に必要なサービスをワンストップで提供できることが当社の強みです。