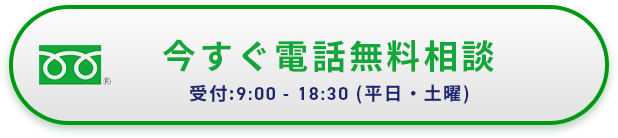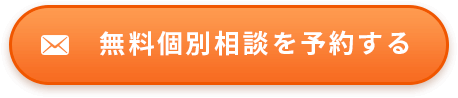不動産の相続税評価額とは?土地・建物別の計算方法と最新税制を税理士が解説

監修
中村亨
日本クレアス税理士法人 代表 税理士 公認会計士
相続税の計算で最も多くの方が悩むのが、「不動産の評価額をいくらで計算するのか」という点です。
実際、相続財産の中で不動産の占める割合は約半分以上に及び、評価方法を誤ると相続税額が数百万円単位で変わることもあります。
国税庁は「不動産の評価は路線価・倍率方式などを基準に行う」と定めていますが、一般の方にとっては複雑に感じられる部分も多いでしょう。
この記事では、税理士監修のもと、
-
不動産の相続税評価額の基本
-
土地・建物別の算出方法
-
評価額を下げる主な特例・減額要件
-
最新税制と実務上の注意点
をわかりやすく整理します。2025年の税制改正動向にも触れながら、相続税の基礎理解を深めましょう。
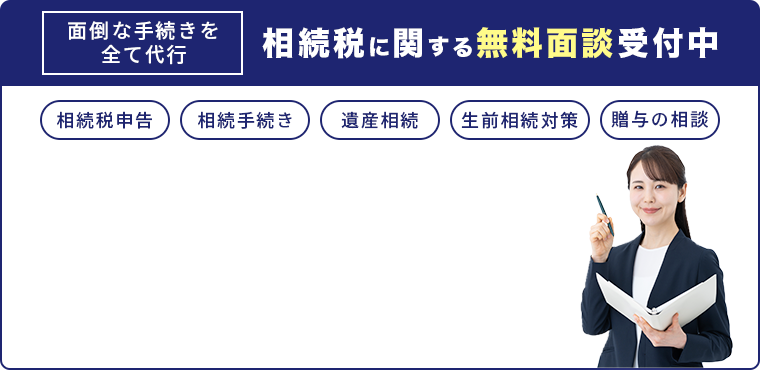
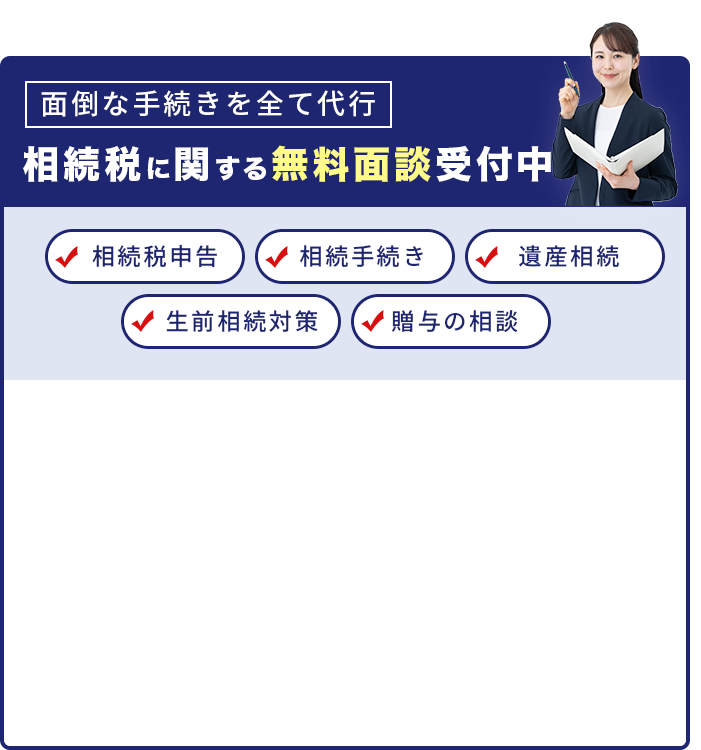
目次
1. 不動産の相続税評価額とは?
1-1. 相続税評価額の基本的な考え方
相続税の計算では、相続財産を「時価」ではなく「評価額」で算出します。
ただし、この「評価額」は売買価格(実勢価格)とは異なり、国税庁が定めた基準に基づいて計算されます。
国税庁によれば、
相続税評価額とは、財産評価基本通達に定められた方法で算定した価額をいいます。
(出典:国税庁 財産評価基本通達)
つまり、不動産を実際に売ったときの価格(時価)ではなく、一定のルールに従って算出された“税務上の評価額”を用いて相続税を計算するのです。
1-2. 実勢価格との違い
一般的に、相続税評価額は実勢価格の70〜80%程度が目安とされています。
これは、相続税評価が「市場価格よりも安く算定される仕組み」になっているためです。
ただし、立地・用途・形状・接道状況によっては実勢価格との差が大きくなることもあり、税務上の評価額が高く出る土地も存在します。
そのため、正確な評価を行うには、路線価・倍率・補正率などの要素を丁寧に確認する必要があります。
2. 土地の相続税評価額の計算方法
土地の評価方法は、国税庁が定める「財産評価基本通達」に基づき、次の2通りに分かれます。
2-1. 路線価方式
路線価方式とは、国税庁が毎年発表する「路線価」をもとに計算する方法です。
路線価は、道路に面する土地1㎡あたりの価値を示すもので、全国の主要道路ごとに1㎡単価が設定されています。
路線価は国税庁ホームページの「路線価図」で確認できます(出典:国税庁 路線価図)。
【計算式】
土地の評価額 = 路線価 × 地積(㎡) × 各種補正率
補正率には、奥行きが長い・間口が狭い・不整形地などの形状に応じた係数が適用されます。
また、角地や二方路などの場合は「加算率」が加わるケースもあります。
2-2. 倍率方式
路線価が設定されていない地域では「倍率方式」で評価します。
倍率方式とは、固定資産税評価額に国税庁が定める「評価倍率」を掛けて求める方法です。
【計算式】
土地の評価額 = 固定資産税評価額 × 評価倍率
評価倍率は、地域ごとに異なり、国税庁の「評価倍率表」で確認できます。
市街地や地方など地域性により倍率が大きく変動するため、所在地の区分を正確に確認することが重要です。
2-3. 宅地の評価を下げる特例
土地の評価を下げることができる制度として、代表的なのが「小規模宅地等の特例」です。
被相続人の自宅や事業用地を相続した場合、最大で評価額の80%が減額されることがあります。
【主な特例の例】
-
居住用宅地(330㎡まで):80%減額
-
事業用宅地(400㎡まで):80%減額
-
貸付事業用宅地:50%減額
これらは相続人の居住・事業継続の有無や面積条件により適用可否が異なります。
特例の適用には申告書への添付書類が必要で、申告後の適用は原則できないため注意が必要です。
3. 建物の相続税評価額の計算方法
建物(家屋)の評価は、土地とは異なり固定資産税評価額をそのまま用います。
【計算式】
建物の評価額 = 固定資産税評価額
固定資産税評価額は、市区町村が3年ごとに見直しており、通常は実勢価格の50〜70%程度です。
評価額は毎年送付される「固定資産税納税通知書」に記載されています。
3-1. 建物評価の注意点
-
木造・鉄筋コンクリート造など構造によって耐用年数が異なるため、築年数によって評価額は下がります。
-
建物が老朽化していても、固定資産税評価が更新されていない場合、実勢より高く評価されることがあります。
-
登記簿上の延床面積と現況が異なると、評価額の見直しを求められる場合があります。
3-2. 賃貸物件の評価減効果
賃貸アパートや賃貸マンションなど、被相続人が貸していた物件は、借家権割合や貸家割合を考慮して評価額を減額できます。
【計算例】
貸家の評価額 = 自用家屋評価額 ×(1-借家権割合 × 賃貸割合)
通常、借家権割合は30%とされているため、賃貸面積が大きいほど相続税評価額が下がる傾向にあります。
4. 評価額を下げるための主な減額制度
相続税対策の中でも、不動産の評価を正しく下げることは非常に効果的です。
以下の特例や減額要件を活用することで、評価額を大きく圧縮できます。
4-1. 小規模宅地等の特例(再掲)
自宅・事業用地の評価額を最大80%減額できる最も有効な制度です。
ただし、次の要件を満たす必要があります。
-
相続人が被相続人と同居していた、または相続開始後も居住を継続している
-
相続税の申告期限までに居住継続している
-
被相続人の居住用・事業用であることが証明できる
申告期限までに自宅を売却してしまうと適用外になる場合があるため、申告前に税理士へ相談しましょう。
4-2. 不整形地・奥行長大地・がけ地などの形状補正
土地の形がいびつな場合は「形状補正率」を使って評価額を減額できます。
具体的には、間口が狭い土地、三角形やL字型の土地、奥行が極端に長い土地などです。
補正率は国税庁が定める算式により0.9〜0.6程度まで下がるケースがあります。
4-3. セットバック・私道負担
建築基準法上の道路に満たない場合、道路拡幅(セットバック)や私道部分が評価減の対象になります。
私道持分を所有している場合、その土地は自用地に比べて20〜30%程度評価額が下がります。
4-4. 借地権・借家権の影響
借地権付き土地の場合、土地所有権者(貸主)は借地権割合分を控除して評価します。
逆に借地権を持つ側(借主)は、土地の権利部分を評価対象として算入します。
これらの割合は地域ごとに異なり、国税庁の「借地権割合表」で確認可能です。
5. 最新税制と実務上の注意点
5-1. 相続税の課税対象拡大傾向
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」とされています。
都市部では不動産の評価額が上昇傾向にあり、**「課税対象になった一般家庭」**も増えています。
国税庁の統計でも、相続税の課税割合は10年前の約4%から、近年は8〜9%へと倍増しています。
5-2. 路線価と実勢価格の乖離
2020年代以降、地価上昇が続く都市部では「路線価より実勢価格が高い」傾向が続いています。
評価額は上昇ペースが緩やかでも、実勢価格との差が広がるため、売却時の譲渡所得税との整合性も考慮した資産管理が必要です。
5-3. 評価の誤りが税務調査対象になるリスク
不動産評価は税務調査で最も指摘されやすい項目です。
国税庁の調査統計では、相続税の申告漏れのうち「不動産評価の誤り」が全体の約3割を占めています。
評価を安易に自己判断で行うと、後日追徴課税を受けるリスクがあります。
6. 税理士に依頼するメリット
相続税の評価において、税理士の専門知識は非常に重要です。
評価方法を正確に適用することで、合法的に税額を抑えることが可能になります。
税理士に依頼することで次のようなメリットがあります。
-
路線価・倍率表・補正率を正確に判定できる
-
小規模宅地等の特例や評価減要素を漏れなく反映できる
-
税務調査時の説明資料を整備できる
-
将来の売却・贈与・二次相続まで見据えた評価提案が可能
特に複数の土地を所有している場合や、共有名義・借地権付き物件がある場合は、専門的な評価手続きが必須です。
7. まとめ|不動産評価は「正確さ」と「証拠」が重要
不動産の相続税評価額は、税額を大きく左右する最重要ポイントです。
土地は路線価または倍率方式で、建物は固定資産税評価額で算出します。
また、形状・利用状況・所有権の種類などにより大きく変動するため、正しい評価方法を理解しておくことが大切です。
さらに、評価額を下げる制度(小規模宅地の特例・不整形地補正・借地権控除など)を適切に活用すれば、節税効果は大きくなります。
ただし、これらの特例は申告期限内での適用が原則であり、後から修正することは困難です。
不動産評価は「高すぎても損、低すぎてもリスク」。
法令に基づいた適正な評価を行い、専門家のサポートを受けながら、安心できる相続対策を進めましょう。

監修
中村亨
日本クレアス税理士法人 代表
税理士
公認会計士
2002年8月に会計事務所として創業、2005年には税理士事務所を開業し、法人や個人のお客様の会計・税務の支援をする中で、「人事労務の問題を相談をしたい」「事業承継を検討している」といったお客様のニーズに応える形でサービスを拡大し続け、現在では社会保険労務士法人など複数の法人からなるグループ企業に成長してきました。お客様に必要なサービスをワンストップで提供できることが当社の強みです。