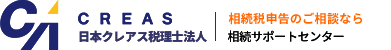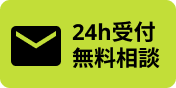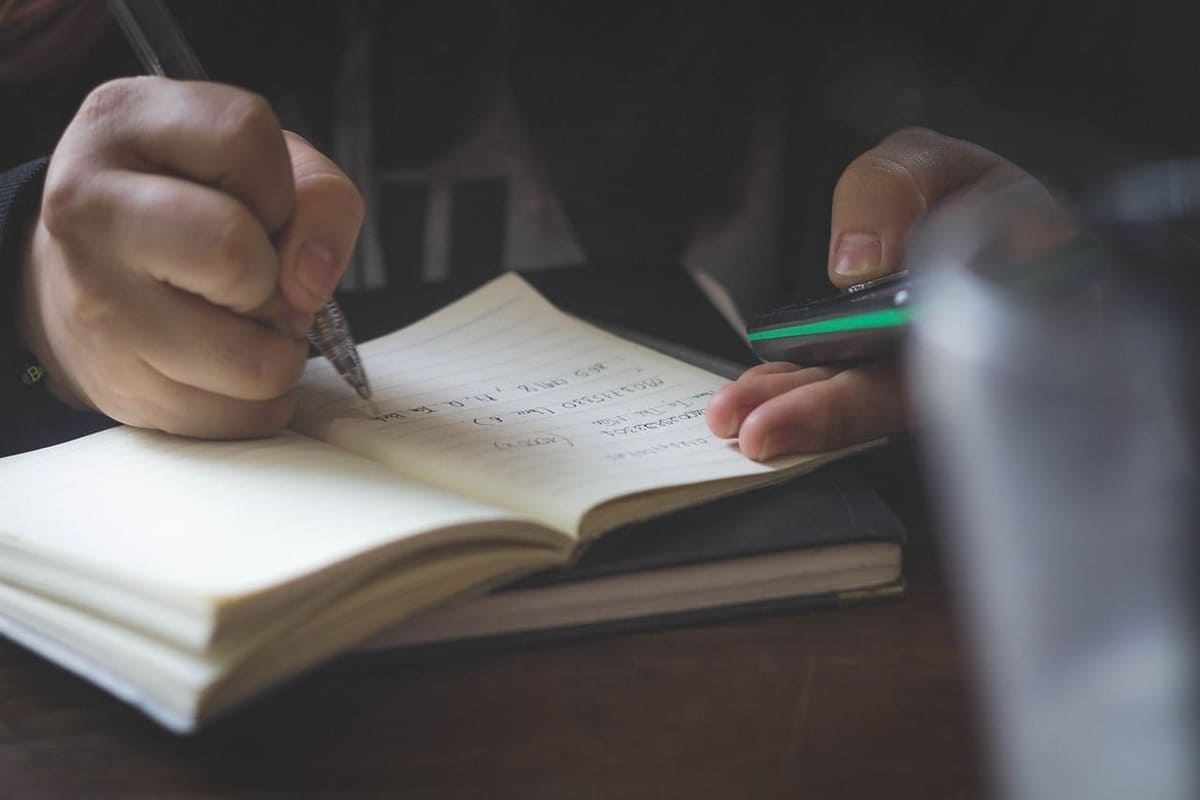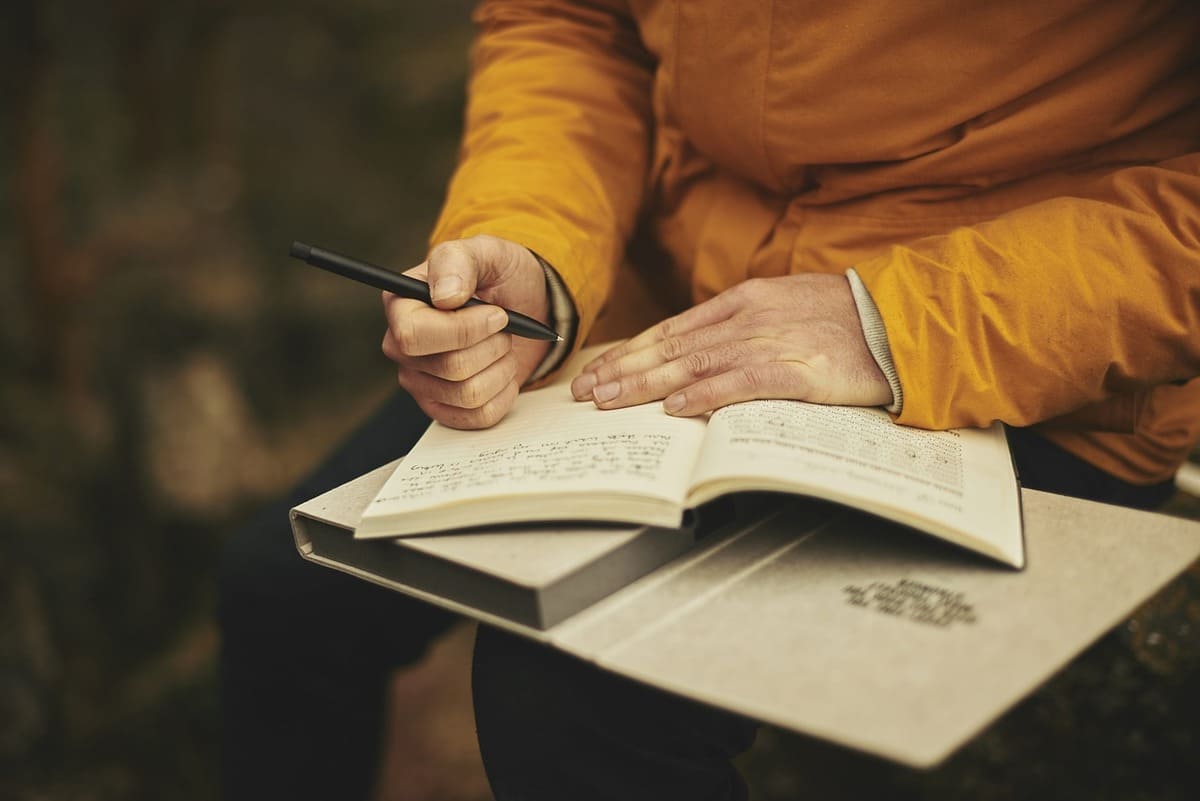相続税の申告をしたあとで、あとから間違えて申告してしまったことに気がついたときには、どうしたらよいのでしょうか。
相続税の申告は複雑で、財産評価のミスや特例の適用ミスなどがあり、あとから間違いに気がつくこともあります。相続税の申告は被相続人が亡くなってから行われるので、どれだけ財産があったかを本人に確認することができないことも大きな理由です。
申告したあとに間違いに気づいたときには、修正申告や更正の請求を行うことになります。今回は、この「更正の請求」について詳しく見ていきたいと思います。
1.相続税の「更正の請求(こうせいのせいきゅう)」とは?

「更正の請求」は、申告によって納付した税金が多すぎた場合に、税務署に税金の還付を請求する手続きです。
相続税を多く払いすぎたからといって、税務署が気づいて還付をしてくれることはありません。納付した税金が多すぎたと気づいたときには、税金を還付してもらうために、納税者が更正の請求をしなければならないのです。
これとは反対に納付した税金が少なすぎた場合には、「修正申告」をすることになります。 納付した税金が少なすぎて追加で税金を払わないといけないときに気づいたときには、税務署から指摘を受ける前に早めに自主的に修正申告をしないと、加算税がかかってしまいますので、気をつけましょう。
修正申告をしてあとから追加で納付する税金については、利息にあたる延滞税かかりますが、2か月以内であれば大幅に軽減されます。
2.更正の請求を行うことのできる期間
相続税の更正の請求をして納付しすぎた税金を還付してもらおうと思ったとしても、いつでも更正の請求ができるわけではありません。
更正の請求を行うことのできる期間は決まっていて、期間内に更正の請求をしなければなりません。期間には、通常の場合と特別な事情がある場合の2つの期間があります。
(1)通常の場合
相続税の更正の請求を行うことのできる期間の原則は、相続税の申告期限から5年以内です。
相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内ですが、通常、被相続人が亡くなった日が相続の開始を知った日となるので、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内と考えます。
つまり、更正の請求は10か月プラス5年で、被相続人が亡くなった日の翌日から5年10か月以内に行わなければならないのです。
※平成23年度の税制改正により、「更正の請求」ができる期間が延長されています。平成23年12月1日以前に申告期限のくる申告については、申告期限から1年以内となります。詳細は後述の「参考:平成23年度税制改正で期間の延長」をご参考ください。
(2)特別な場合
相続税の更正の請求は後発的理由など特別な理由が発生した場合には、その特別な理由を知った日の翌日から2か月または4か月以内となります。
2か月か4か月かは、特別な理由の内容によって変わってきます。 (1)の5年10か月の期間をすぎていても、特別な場合にはその理由を知った日の翌日から2か月または4か月まで、更正の請求を行うことのできる期間が延長します。
特別な理由の代表的なものとして、相続税の申告期限までに相続財産の分割の話し合いがまとまらなかった場合が考えられます。
この場合には、仮で申告をすることになるので、遺産分割の話し合いがまとまってから更正の請求をすることになります。
5年10か月がすぎている場合には、遺産分割がまとまった日の翌日から4か月以内が更正の請求を行うことのできる期間になります。
その他にも、あとから遺言書が発見された場合、遺留分侵害額(減殺)請求による返還があった場合などがあげられます。
3.更正の請求の対象者
相続税の更正の請求ができる人は、すでに行った相続税の申告について、納付税額が多すぎた人です。
4.手続きの流れと必要書類
相続税の更正の請求を行うには、まず、すでに行った相続税の申告について確認します。
更正前と更正後の税額、請求の理由、事情の詳細等を記載した「更正の請求書」を税務署に提出することで、更正の請求を行うことができます。
※参考: 国税庁HP __税の更正の請求書
この「更正の請求書」には、「事実を証明する書類」を添付する必要があります。
「事実を証明する書類」とは、たとえば、遺産分割がまとまったために更正の請求を行う場合には遺産分割協議書などの書類のことをいいます。事実を証明する書類は、後日、税務署から追加の資料を提出してくださいと言われることもあります。
更正の請求を提出すると、後日、払いすぎた相続税が税務署から還付されます。
5.スムーズな相続手続きをするには
(1)当初からきちんとした申告をする
遺産分割協議がまとまらないなどの理由がある場合をのぞいて、当初の申告がきちんとなされていれば、面倒な更正の請求という方法をとる必要がなくなります。
しかし相続税の申告は、財産評価や誰が相続人なのかなど考慮すべきことがたくさんあり必要書類も多いので、ミスをしがちな申告です。
相続税の申告書を提出する必要がある場合には、相続税に詳しい税理士に依頼することをおすすめします。
(2)生前の相続対策をしっかりとする
相続税の申告は、被相続人がどこにどれだけの財産を持っていたかの調査に時間がかかるケースも多く、あとから相続人が知らなかった財産が発見されたり、遺言書が発見されることもあります。
申告をしてしまったあとに財産や遺言書が発見され、修正申告や更正の請求が必要になると、せっかく一段落した相続の手続きを、またやり直さなければならなくなってしまいます。
できれば生前から相続対策をし、どれだけの財産があり、誰にどれだけ相続させたいかを専門家のアドバイスのもとで検討し、遺言書を作成し保管場所も明確にしておくとよいでしょう。
(3)セカンドオピニオンを依頼する
相続税は、1人の税理士のみに依頼して申告をした場合、その税理士がなるべくリスクの少ない申告をしようと思って申告をすると、相続財産を高めに評価し相続税額が大きくなってしまう場合があります。
特に、土地や建物などの不動産が多い場合には、評価額の考え方により評価する人によって評価額が異なる場合があります。
すでに相続税の申告をしてしまった場合でも、相続税が高すぎるのではないかと感じた場合には、セカンドオピニオンとして相続の専門家である税理士に相談してみると、更正の請求をすることができ相続税が還付されるというケースも多いのです。
相続税の申告を依頼している税理士に不安がある場合、不動産の評価についての部分だけ他の税理士の意見が聞きたい場合、相続税の申告をしてしまった後だが相続税の額に納得がいかない場合など、セカンドオピニオンとして相続の専門家である信頼できる税理士に相談することをおすすめします。
6.参考:平成23年度税制改正で期間の延長
2011年度の税制改正により、「更正の請求」ができる期間が延長されました。 それまでは、法定申告期限から1年以内に行なわなければならなかったのが、2011年12月2日以後に申告期限が到来する相続税については、申告期限から5年以内まで行えるように改正されました。
| A | 2011年12月1日以前の対象者 | 手続きの種類 |
| (1) | 申告期限から1年以内の方 | 「更正の請求」 |
| (2) | 申告期限から1年を過ぎて3年以内の方 | 「更正の申出」 ※「更正の申出書」を提出することにより、税務署長に税金の還付をお願いすること |
| (3) | 申告期限から3年を過ぎて5年以内の方 | 「還付嘆願」 ※税務署長に税金の還付をお願いすること ※ただし嘆願は、更正の請求と違って納税者の権利ではありません。税務署に無視されても、審査請求等の争いを起こせません |
| B | 2011年12月2日以後の対象者 | 手続きの種類 |
| (1) | 申告期限から5年以内の方 | 「更正の請求」 |
【お役立ちコンテンツ】
相続相談はどこにするべき?専門家(税理士、司法書士、弁護士)の強み
【クレアスの相続税サービス】
関連リンク
| 相続税の申告が正しく行われないとどうなるのか? |
| 申告した相続税額が誤っていたらどうすればいいのか? |
| 相続税の申告が正しく行われないとどうなるのか? |
| 相続税を納付しすぎた時の対応、更正の請求について |
| 相続税の申告の金額を間違えた時の修正申告に関わる税率 |
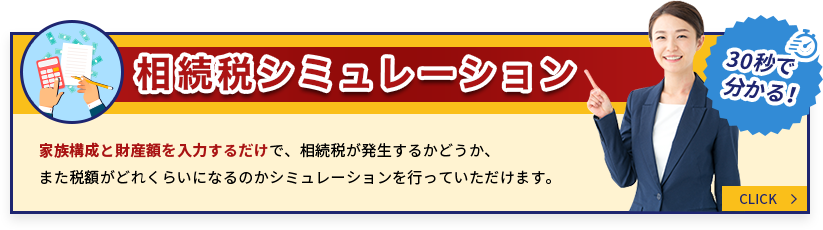
このコラムは「日本クレアス税理士法人」が公開しております。
東京本社
〒100-6033東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング33階
電話:03-3593-3243(個別相談予約窓口)
FAX:03-3593-3246
※コラムの情報は公開時のものです。最新の情報は個別相談でお問合せください