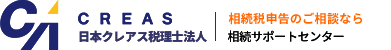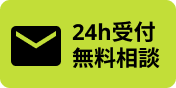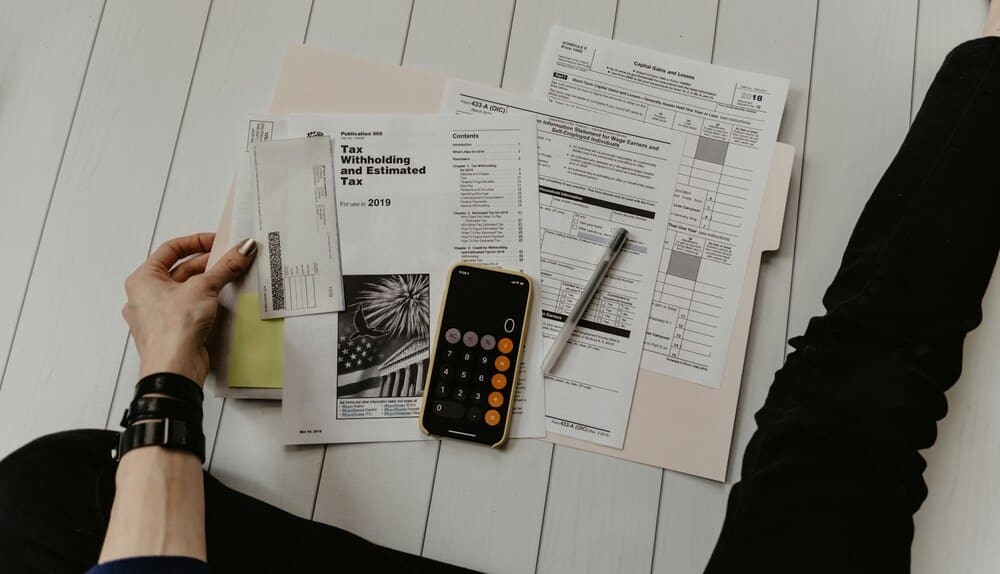サラリーマンの方は自分で確定申告をする機会があまりないので、税金に関する手続きは「良く分からない」、「面倒そうだ」というイメージが強いと思います。
それでも、もしあなたの親族が亡くなりあなたが相続人となった場合、ケースによっては亡くなった人に代わって確定申告を行う「準確定申告」が必要です。
1.そもそも「確定申告」とは?
確定申告とは、その年の1月1日~12月31日までの収入額をまとめ、これを税務署に申告し、必要であれば納税を行うものです。色々な理由で多少のずれが生じる税額を確定させて申告するので「確定申告」というわけですね。
人によっては確定申告によって納め過ぎた税金を取り戻すこともできます。
サラリーマンの方は会社が代わって事前に仮の納税を行っているので、後から自分で医療費控除などの控除施策を使って計算上の収入額を小さくし、計算上浮いた金額を還付してもらうこともできます。
2.「準確定申告」とは?
準確定申告とは、亡くなった方(被相続人)に代わって相続人が行う確定申告のことです。相続人が1月1日から死亡した日までに確定した所得金額と税額を計算して申告と納税をしなければなりません。
確定申告はその年の1月1日~12月31日までの収入をまとめて税金を確定させるわけですが、人の死亡は大抵年の途中に発生します。例えばAさんが6月15日に死亡した場合、生前の収入に対して納税の義務はありますので、Aさんはその年の6月15日までの収入をまとめて税務署に申告し、必要であれば税金を納めなければいけません。
準確定申告が必要な人とは?
準確定申告の対象者は、生きていたら通常の確定申告をしなければならなかった人です。
例えば、個人で事業を経営していた人、給与収入が2,000万円を超える人、給与所得・退職所得を除く各種所得金額の合計額が20万円を超える人、同族会社の役員・その親族等で給与の他に貸付金の利子・賃貸料等の支払を受けていた人等が該当します。
また、確定申告により還付を受けるはずだった人も、準確定申告をすることで還付を受けることができます。
3.準確定申告の留意点
では準確定申告の留意点を通常の確定申告と対比する形で確認してみましょう。
3-1.申告時期について
通常の確定申告はその年の翌年の2月16日~3月15日までに行いますが、準確定申告は相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から4か月以内に行う必要があります。
3-2.相続人全員で行うこと
通常の確定申告は自分自身が手続きの義務者ですが、準確定申告は故人の代わりにその相続人が手続きの義務を負います。
相続人が二人以上いる時は全員で行う必要があり、実務では各人が署名する連署の形で準確定申告を行います。あるいは各人が別々に申告書を提出することもできますが、その場合は他の相続人の名前を各自が付記し、さらに他の相続人に申告の内容を通知しなければならないので、手間がかかります。
3-3.医療費の取り扱い
故人が生前に負担した医療費は、その故人の準確定申告で医療費控除の対象になります。
もし故人の医療費について、故人と生計を同一にする相続人が負担していた場合は、それが故人の生前であっても死亡後に支払ったものであっても、相続人自身の確定申告で医療費控除の対象となります。
さらに相続人の相続税の計算においては、相続開始後に相続人が支払った医療費は債務控除の対象にもなります。
相続開始前に支払ったものについては、親族の扶養義務の範疇のものは債務控除の対象にならないため、後日清算する予定であったものだけが債務控除の対象になります。
3-4.所得控除や保険料(生命、地震等)の計算
生計同一要件や所得要件のクリアが必要になる配偶者控除や扶養控除などの人的控除については、故人の死亡時の現況でその要件がクリアされていれば準確定申告で利用可能です。
生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済掛金控除などは、1月1日から故人が死亡した日までに支払ったものが控除の対象になります。
保険料や掛け金の支払い証明書は通常年末まで郵送されてきませんから、こちらから早めに連絡し、準確定申告で必要なので支払証明書が必要な旨を伝えてください。
4.準確定申告の手続の流れ
4-1.必要書類
税務署が用意する確定申告の様式はAとBがありますが、基本的には例年故人が使用していた様式を利用することになります。
様式Aは給与所得、雑所得、配当所得、一時所得だけの方(会社員やアルバイト・パートの方)が使います。様式Bは 所得の種類に関わらず誰でも利用が可能です。個人事業主の方は様式Bを使います。
様式は国税庁のWebサイトでダウンロードできますが、どちらの様式の場合も上部にある様式名の「確定申告」の前に「準」の字を挿入して、これが準確定申告だと分かるようにします。
これとは別に、相続人が複数になる場合は各相続人の氏名や相続分割合などを記入した付表が必要になります。
※「死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」(国税庁Webサイト)
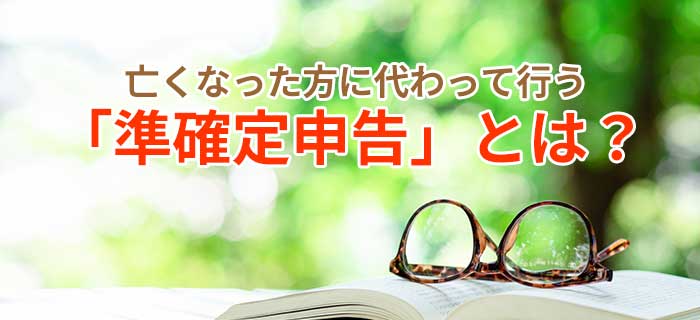
他には通常の確定申告と同じく、申告の内容を証明するため必要に応じて各種保険料などの支払い証明書や源泉徴収票、事業者であれば青色申告決算書や収支内訳書などを添付します。源泉徴収票は被相続人がお勤めだった事業所に発行をお願いしてください。
また、亡くなった方(被相続人)が年金を受け取っていた場合、準確定申告用の年金の源泉徴収票が必要となります。これは年金の受給停止手続きを行うと、自動的に死亡届を提出した方宛に送付されますが、送付まで数か月を要することもあります。なるべく早めに対処するようにするとよいでしょう。
4-2.申告書の提出先
通常の確定申告の提出先は基本的にその人の住所地を管轄する税務署ですが、準確定申告の場合は故人の死亡時の住所地を管轄する税務署に提出します。
4-3.e-Taxでの申告が可能
確定申告の電子システムであるe-Taxで準確定申告の申請が可能です。令和2年分以降の準確定申告(死亡の場合)において、青色申告特別控除の適用が受けられるよう、また利便性向上のためe-Taxでの電子申告に対応しました。e-Taxで申請するためには以下の書類が必要です。
- 所得税及び復興特別所得税の準確定申告書
- 死亡した者の令和_年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表
- 準確定申告の確認書
- 委任状
5.各種控除や消費税、還付等のポイント
- 医療費控除、社会保険料控除等は、死亡の日までに被相続人が支払ったものだけが対象となります。死亡後に、相続人が支払ったものは準確定申告の対象にはなりません
- 配偶者控除・扶養控除は死亡の日の現況により判定します
- 被相続人が消費税の納税義務者であった場合には、準確定申告をする際に、消費税の申告及び納税も行う必要があります
- 被相続人が受け取っていた収入の中で、源泉徴収されているものがあった場合、準確定申告により所得税の還付を受けることができる場合があります
6.準確定申告のまとめ
今回は被相続人に代わって行う準確定申告について見てきました。
手続き義務者は相続人であり故人の死亡から4か月以内という手続き期限もあるため、葬儀や各種の手続きに追われて心が休まらない時期とは思いますが不備の無いようにしたいものです。
一部、故人の収入が少ない場合などケースによっては準確定申告が不要なケースもありますが、要不要の判断も一般の方では難しいこともありますから必要に応じて税理士等に確認すると安心です。
手続きが必要な場合は源泉徴収票や保険料の支払い証明書などの必要書類の収集にも時間がかかりますから、これらの発行手続きも早めに進めておくことが望まれます。
【お役立ちコンテンツ】
相続相談はどこにするべき?専門家(税理士、司法書士、弁護士)の強み
【クレアスの相続税サービス】
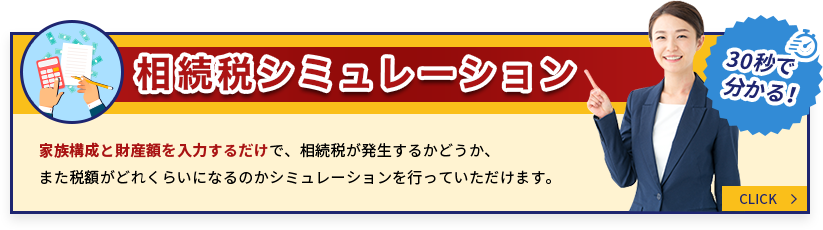
このコラムは「日本クレアス税理士法人」が公開しております。
東京本社
〒100-6033東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング33階
電話:03-3593-3243(個別相談予約窓口)
FAX:03-3593-3246
※コラムの情報は公開時のものです。最新の情報は個別相談でお問合せください