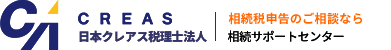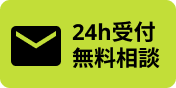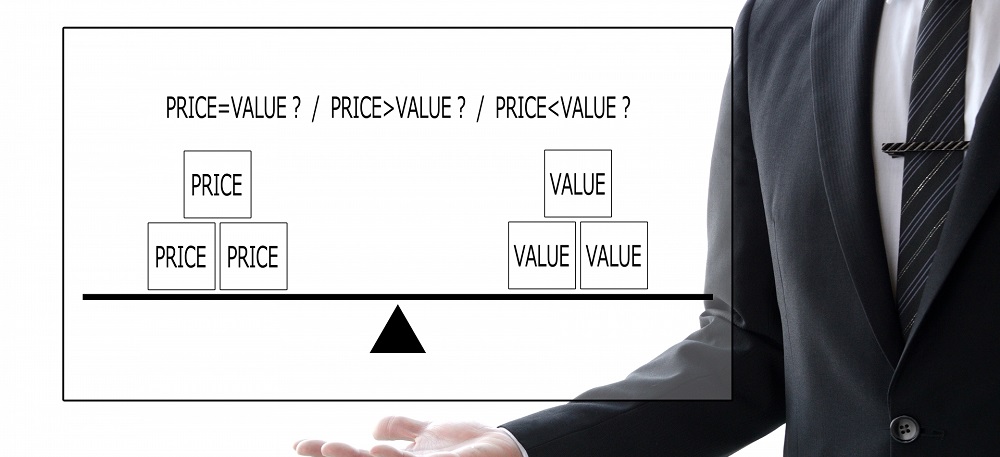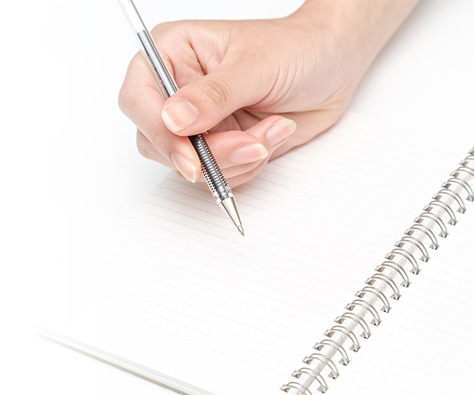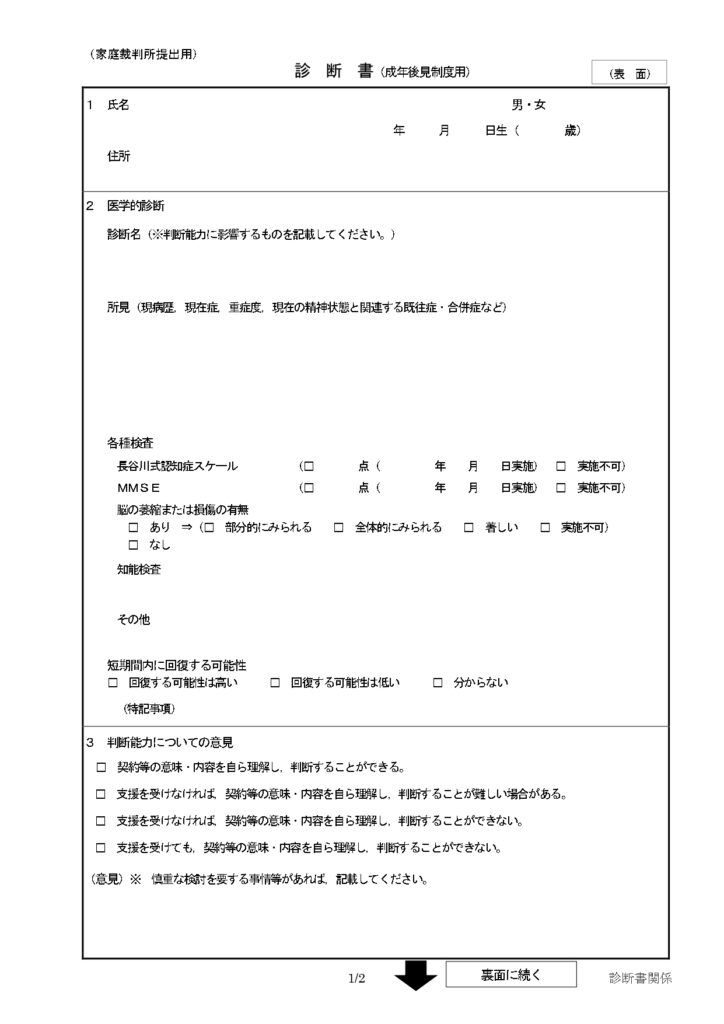相続税の計算においては、全ての相続財産の価値を数値化して評価する必要があります。
現金や預金などはそのままの額で評価することができますが、土地や建物など不動産の評価は国が定めた一定のルールに基づいて行うことになります。
1.土地の評価単位について
土地については、その評価単位は原則として地目別の評価となります。 地目とは例えば宅地、農地、山林などのことです。
宅地については、登記簿上の一筆の土地ではなく、利用の単位となっている一区画ごとの評価になります。例えば自宅用地と駐車場用地がある場合は利用の単位を別々としてそれぞれ評価を行うことになります。
2.相続時の土地は基本的には「路線価方式」
土地についての評価法は「路線価方式」と「倍率方式」があり、それぞれ評価法が異なります。
原則は「路線価方式」を利用した計算となりますが、これは国税庁が市街地などの主要な土地について1㎡あたり千円単位で基本の単価を設定したものです。この路線価に土地の地積をかけることでその土地の相続税評価額の大体の数値が計算されます。
実際にはそこから補正として様々な計算上の修正が入ることになりますが、この計算は税理士でなければ難しいでしょう。
例えば奥行価格補正といって、面している道路からどれくらいの奥行きとなっているかによって使い勝手が変わるので、これを補正するための計算が入ります。この補正はその土地がどの区分に該当するか(住宅地か工業地区かなど)によっても異なります。
また二つの道路に面している場合には側方路線影響加算率や二方路線影響加算率などの補正もありますし、他にも不整形地補正率、間口狭小補正率、奥行長大補正率など多くの補正が入ります。(参考コラム:土地の減額評価を使いこなして実現する相続税の節税対策)
税理士の中でも特に相続の経験が高い税理士は、これらを正確に計算することを得意としており、そのような専門家を頼った方が正しい申告と納税ができるでしょう。
2-1.路線価が無い場合は倍率方式で計算
路線価は主要な土地のみに設定されているので、それ以外の土地は「倍率方式」によって計算します。
こちらの計算は比較的に単純で、その土地の固定資産税評価額に国税局長が定める一定の倍率をかけて計算します。
2-2.路線価図や倍率の確認方法
路線価図の見方や倍率については国税庁のHPで説明を見ることができます。
他人に貸している土地(貸宅地)やアパートなどを建てて賃貸物件用の土地として利用している土地(貸家建付地)は、他人に貸す分、所有者自身による自由な利用が制限されるので、その分を減額して評価することができるようになっています。
貸宅地の場合、計算式としては「自用地評価額×(1-借地権割合)」となります。
自用地評価額というのは、貸地などとしてではなく通常通り自分で利用する土地として評価した価額のことです。
借地権割合は路線価図で確認することができ、アルファベットのA~Gの記号によって表記されています。
- A=90%
- B=80%
- C=70%
- D=60%
- E=50%
- F=40%
- G=30%
以上のような借地権割合を表しています。
貸家建付地の場合、借地権割合に加えて借家権割合や賃貸割合といった考慮項目が出てきます。 計算式にすると、「自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」となります。
借家権割合は一律0.3ですが、賃貸割合はその家屋の各独立部分の床面積の合計に占める、課税時期において賃貸されている各独立部分の床面積の合計となります。満室であれば1.0ということになります。
なお、土地については住居用の土地であったり一定の事業に利用する土地について特別に減額評価できる特例(小規模宅地等の特例)が利用できることもあります。
3.土地に関する5つの価格
土地の価格は路線価以外にも複数あり、同じ土地でも複数の目線で評価されることから「一物四価(いちぶつよんか)」「一物五価」などと表現されます。それぞれの算出方法をご紹介します。
①時価(実勢価格)
時価はその土地の現在の市場価格のことで、簡単に言うと売りに出した時にどれくらいで売れるかという目線で見る評価の仕方です。一般の方にとっては一番分かりやすい価値と言えるでしょう。
ただし時価は売り手と買い手との関係やそれぞれの事情、交渉上のパワーバランスなどで大きく変化しますから、安定した価格とは言えません。
②公示価格(公示地価)
公示価格は国土交通省が所管するもので、一般の土地取引の指標になる他、公共事業用の土地の取得価格の基準にもなるものです。
毎年1月1日時点での評価となり、毎年3月頃に発表されます。
③相続税路線価
前述している通りですが、国税庁が所管するもので、相続税の計算の為の土地評価法がこの路線価です。評価時点は毎年1月1日時点で、7月頃に発表されます。概ね公示地価の80%程度の評価額となります。
④固定資産税評価額
地元の市区町村が管理するのが固定資産税評価額です。
この評価は固定資産税の算定や登録免許税などの計算の為に利用されます。 評価時点は1月1日時点、毎年3月か4月頃に発表されます。概ね公示価格の7割程度の評価額になります。また固定資産税評価額は三年に一度の評価替えがあります。
⑤基準地価(都道府県基準地標準価格)
国土利用計画法に基づいて毎年都道府県知事が公表する価格で、公示地価でおさえられない場所を補完する目的で使われます。毎年7月1日を基準日とし、9月に発表されます。
4.古い相続税路線価で申告してしまったらどうなる?
相続税路線価は相続が起きた年のものを使用しなければなりません。
もし間違って古い相続税路線価を使用して相続税評価をしてしまった場合、申告納税をやり直す必要がでてきます。
もし本来納めるべき税額よりも少なく申告、納付してしまった場合は「修正申告」が必要です。 修正申告をすると追加で納めるべき税額について、納税が遅れた分のペナルティとして「延滞税」がかかります。一般的な借金の返済が遅れた際の延滞利息のようなものです。
また税務調査の事前通知を受ける前に自主的に修正申告した場合を除いて、「過少申告加算税」というペナルティもあります。本来よりも少なく申告、納税を行ったことそのものに対する懲罰的な意味合いがあるものです。
4-1.路線価の発表前に相続が起きたら・・・?
この相続税路線価は毎年7月頃発表されるものですが、相続というのはいつ起きるか分からないものです。発表前に相続が起きた場合には、その年の路線価が発表される7月頃まで申告手続きを待たなければなりません。
その間落ち着かないと思いますが、前年分の路線価を使うのではなく、相続が起きた年分の路線価を使わなければならないことは覚えておきましょう。
5.家屋の評価方法
家屋の相続税評価は土地に比べると単純で、基本的にはその不動産の固定資産税評価額に1.0の倍率をかけた値になります。
貸家については土地の場合と同じように、自由な利用が制限される分を減額して評価することができます。 計算式としては「自用家屋評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」となります。
借家権割合は一律0.3、賃貸割合は満室ならば1.0となります。
5-1.建築中の家屋の評価はどうする?
家屋については建築中のものである場合、まだ固定資産税評価額がつけられていないので利用することができません。
この場合、費用原価の70%を相続税評価額として利用します。
費用原価というのは、その建物の建築費用の価額を課税時期の価額に引き直したものをいいます。
6.まとめ
今回は土地や家屋などの不動産について、相続税評価の仕方の基本を見てきました。
家屋についてはそれほどではありませんが、土地については実際の計算は各種の補正が入るため素人の方では正確な計算は難しくなります。
また特例を上手に利用することで相続税の負担を減らすことができますが、これも適用のルールが細かく決まっているので分かりづらくなっています。必要に応じて相続税に詳しい税理士に相談し、上手な相続税対策を講じるようにしましょう。
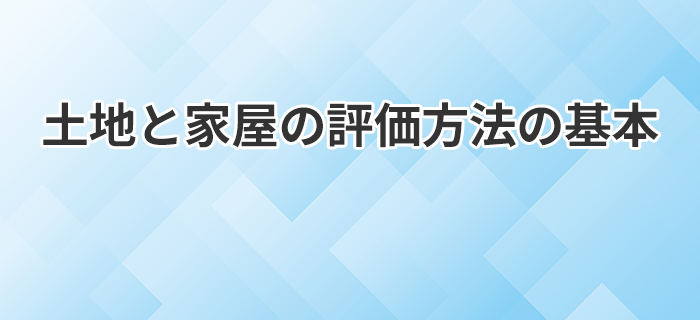
【お役立ちコンテンツ】
相続相談はどこにするべき?専門家(税理士、司法書士、弁護士)の強み
【クレアスの相続税サービス】
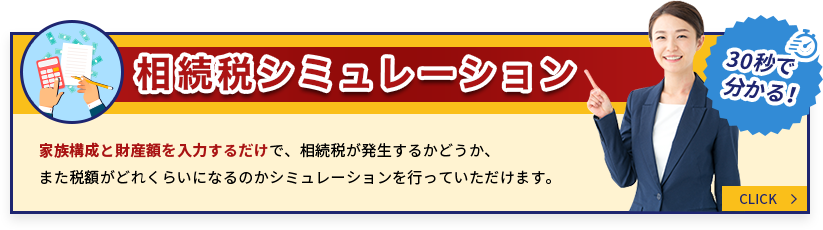
このコラムは「日本クレアス税理士法人」が公開しております。
東京本社
〒100-6033東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング33階
電話:03-3593-3243(個別相談予約窓口)
FAX:03-3593-3246
※コラムの情報は公開時のものです。最新の情報は個別相談でお問合せください