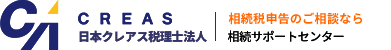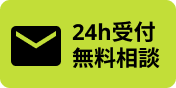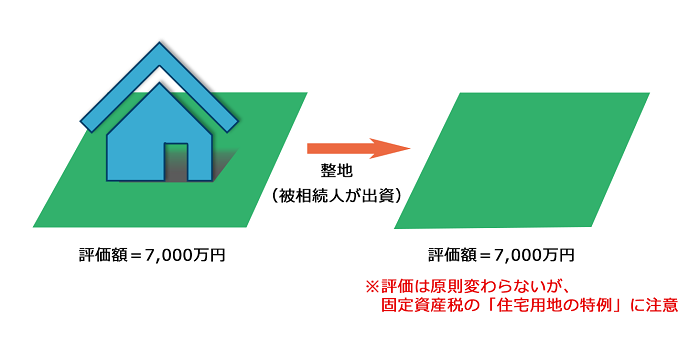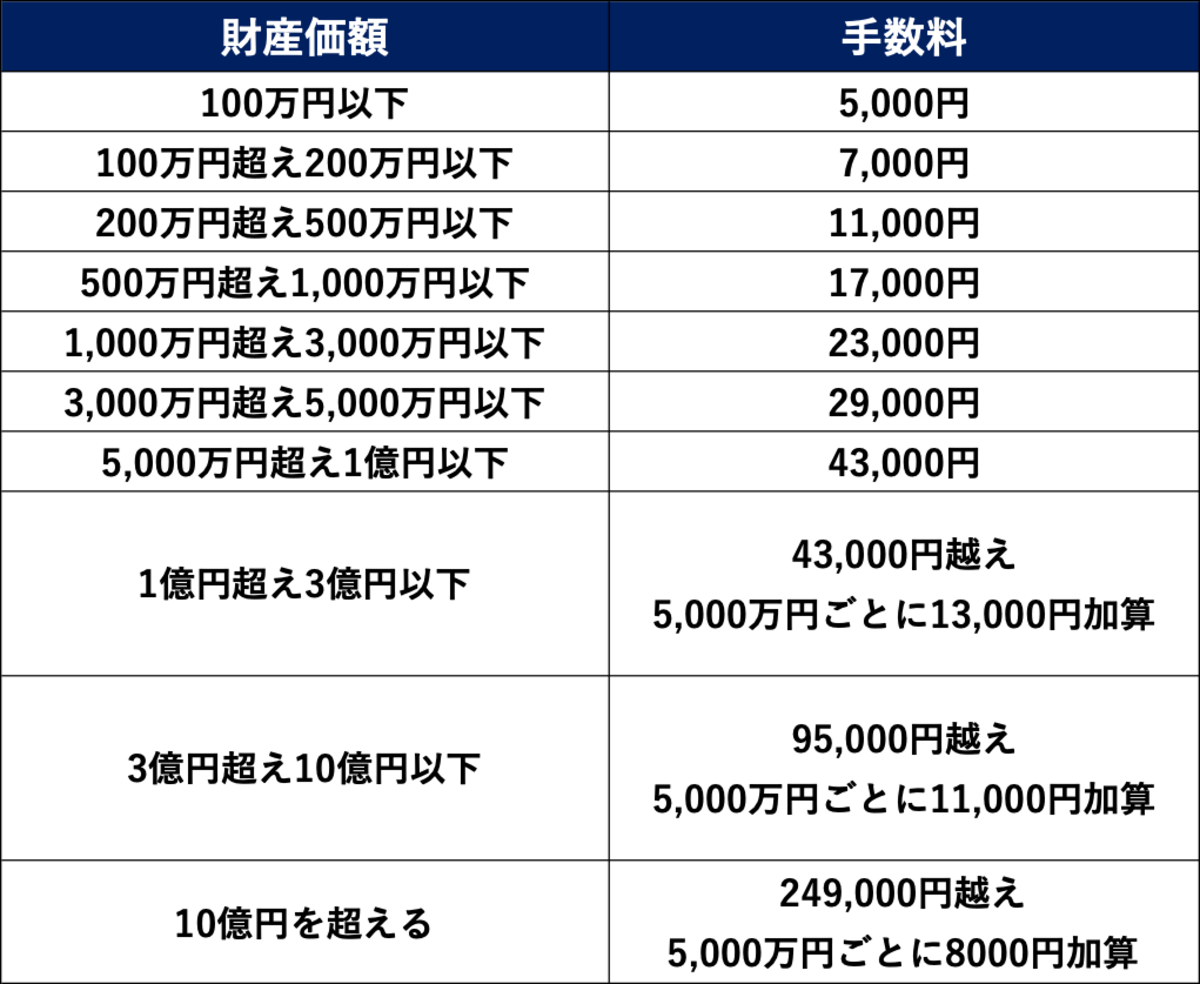「相続の生前対策」のコラム一覧
-
 自筆証書遺言vs公正証書遺言 どちらに軍配?-自筆証書遺言保管制度2022.7.2
自筆証書遺言vs公正証書遺言 どちらに軍配?-自筆証書遺言保管制度2022.7.2平成31年1月13日、自筆証書遺言の書き方に関する法律改正が、令和2年7月10日に自筆証書遺言の保管等に関する法律が施行され、 作成方式の緩和や安全性の向上などにより、自筆証書遺言の作成が身近なものになりました。ですが、 […]
-
 資産管理会社設立とは?仕組みと活用のメリットについて2022.6.28
資産管理会社設立とは?仕組みと活用のメリットについて2022.6.28高額化する所得税・相続税への対策として、設立した「資産管理会社」に個人所有の資産を移転させる方法があります。不動産投資の効率化・遺産分割時のトラブル防止策としても有効で、後世代のために着実に財を築きたい人に注目されていま […]
-
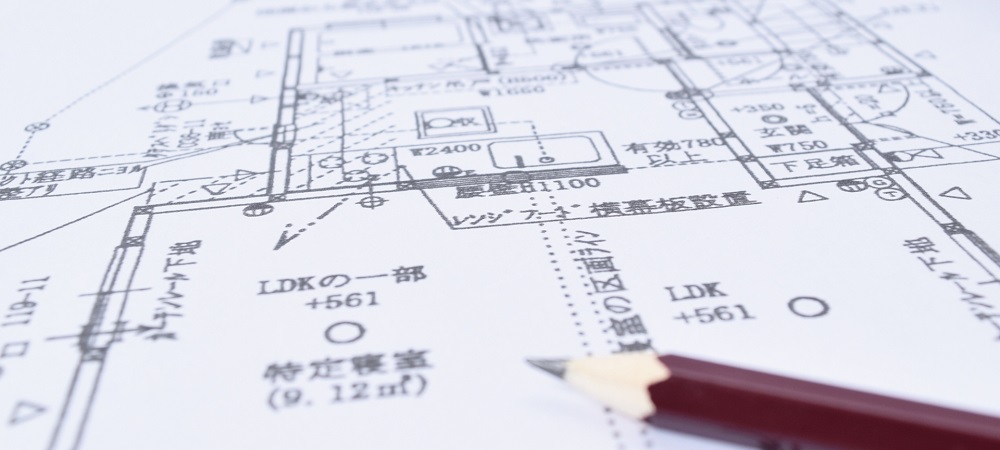 親の土地に家を建てる際に知っておきたい税金のこと、トラブル対策についても解説!2022.6.5
親の土地に家を建てる際に知っておきたい税金のこと、トラブル対策についても解説!2022.6.5住宅購入を検討している人にとって、親の持つ土地は“渡りに船”かもしれません。身内のよしみで持ち家を建設させてもらえれば、土地購入コストの削減のみならず、両親の生活を側で見守れる安心感も一挙に得られるでしょう。 ここで注意 […]
-
 成年後見人に資格は不要、なれる人、なれない人の条件を解説!2022.6.28
成年後見人に資格は不要、なれる人、なれない人の条件を解説!2022.6.28判断能力の低下がみられる家族には、後見人による財産管理のサポートが必要です。その後見人を誰が務められるのか(近親者orそれ以外の親類or弁護士や司法書士などの有資格者)、多くの家庭で最低でも一度は議論されるのではないでし […]
-
 遺言代用信託の活用方法やメリット、お手続きの流れもまとめて解説!2022.7.2
遺言代用信託の活用方法やメリット、お手続きの流れもまとめて解説!2022.7.2高齢者の資産に含まれる預金は、万一のときに誰にも出金できない“凍結状態”に陥ることがあります。こうした不便を解消できるのが、死亡時もしくは認知症発症時にあらかじめ指定した金額を払い戻せる「遺言代用信託」です。 本信託制度 […]
-
 地積規模の大きな宅地の評価とは?2022.6.28
地積規模の大きな宅地の評価とは?2022.6.28「土地の価値は面積に比例する」と考えられがちですが、実はそうではありません。 むしろ、土地面積が広がるほど宅地利用の際にさまざまなムダが生じ、負担増により収益性が落ちてしまうという問題点を抱えています。 そこで、税額を減 […]
-
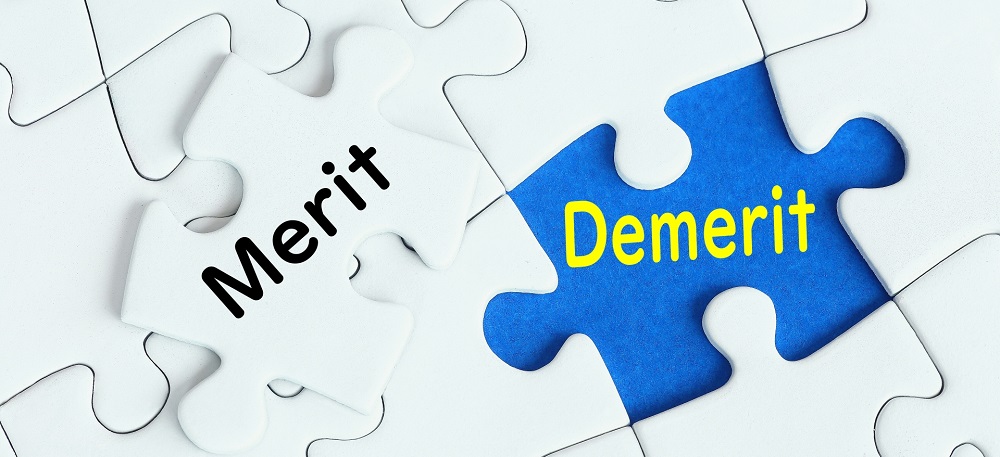 遺贈とは?相続との違い、メリット・デメリットを解説2022.7.2
遺贈とは?相続との違い、メリット・デメリットを解説2022.7.2遺贈では、法定相続人でない親族や第三者に対して、財産を取得する権利を与えることができます。遺贈の相手を、法人とすることも可能です。 孫やお世話になった友人など、法定相続人以外の人に財産を遺すことができ、被相続人の想いを実 […]
-
 成年後見人ってなに?手続き方法を徹底解説!2022.6.28
成年後見人ってなに?手続き方法を徹底解説!2022.6.28老齢や病で判断能力が落ちてきた人に必要なのは、日常生活のサポートだけではありません。その財産管理が適切に行えるよう「成年後見人」が必要です。 成年後見人に関するルールは法律で定められていますが、本人(=被後見人)の意思を […]
-
 自筆証書遺言書の正しい書き方を種類別、ケース別で解説2022.7.2
自筆証書遺言書の正しい書き方を種類別、ケース別で解説2022.7.2平成30年7月に行われた相続に関する法改正の内容が、2019年から順次施行されています。 ・財産目録の作成要件の緩和 ・法務局における遺言の保管制度の創設 大きく変わったこの二つの内容とともに、「自筆証書遺言」「公正証書 […]
-
 生前贈与とは?孫に贈与したい時の非課税について2022.6.28
生前贈与とは?孫に贈与したい時の非課税について2022.6.28生前贈与は、贈与税の対象ですが、贈与税には非課税になる基礎控除額があるので、数万円程度の贈与であれば贈与税を気にする必要はありません。 しかし、孫が住宅購入する際の資金援助や、土地を贈与する場合には贈与税の申告手続きが必 […]