相続税の申告が必要なのはどんな人?
相続税の申告が必要な人とは、相続財産の総額が相続税の「基礎控除」を超える方です。その他、特例を活用する場合にも申告が必要です。
目次
1.相続税の基礎控除以下なら申告不要
相続する財産の総額が「基礎控除」を超えなければ、相続税の申告は原則として不要です。
基礎控除は以下の計算式で算出します。
基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続財産の課税価格の算出には、
- 不動産なども含めて全ての相続財産を数字に換算する
- みなし相続財産を加える
- 非課税財産を控除する
- 債務控除を行う
- 相続開始前3年以内の贈与財産を加える
など、相続税法のルールに従い一定の計算処理が入り、その結果算出された相続財産の課税価格が、基礎控除の額に収まるようであれば相続税の申告手続きは原則不要です。
例えば、相続人が一人であれば基礎控除額は3,600万円、二人であれば4,200万円ですから、相続財産の課税価格がこれ以下であれば相続税の申告は原則必要ないということになります。
2.相続税の基礎控除額を下回っていても申告が必要なケース
相続税の基礎控除額と相続財産の課税価格を比べて基礎控除の枠内に収まっているようであれば原則として申告は不要と解説しましたが、一定の特例等を利用する場合には申告手続きが必要になるので注意を要します。
例えば以下のような特例を利用した結果、数字上は相続税の税額が0以下になったとしても、申告手続き自体は必要です。
①配偶者の税額軽減
配偶者は相続税においては特別に優遇されていて、大きな税額軽減の措置を受けることができます。
配偶者が負担すべき相続税額を計算して、算出された額から特別に1億6,000万円または法定相続分のどちらか大きい方の数字を差し引くことができます。差し引いた結果の数字が0以下になれば納税は不要ですが、申告手続きは行わなければなりません。
②小規模宅地の特例
これは一定の宅地について、宅地の種類に応じた限度面積までを減額して評価し、相続税の負担を軽減することができるものです。この特例を利用する場合も申告手続きが必要になります。
③農地等を相続した場合の納税猶予の特例
農業相続人が農地等を相続した場合に、相続税の納税が猶予される特例です。 この特例も利用するには相続税の申告手続きが必要になります。
3.もし相続税の申告漏れがあったら?
必要な相続税の申告漏れがあった場合はペナルティを課せられることがあるので、その概要だけは押さえておきましょう。
①無申告加算税
必要な相続税の申告をしなかったことによる懲罰的な意味合いのあるもので、必要な納税額に一定の加算割合をプラスされます。
②過少申告加算税
本来必要な税額よりも少なく申告した場合に適用があるもので、追加で納めるべき税額に一定の加算割合がプラスされます。
③重加算税
仮装や隠ぺいを行うなど、悪質性が高いと判断されるケースでは無申告加算税や過少申告加算税に代えて、加算割合が通常よりも重くなる重加算税が課税されます。
④延滞税
納めるべき税額について、法定納期限の翌日から実際に納付がなされる日までの日数に応じて、一定の割合で延滞税がかかります。 一般の借金でいうところの遅延利息のような性質を持ちます。
4.まとめ
今回はどんな場合に相続税の申告が必要になるか見てきました。
相続税の基礎控除額と相続財産の課税価格を比べて、前者の方が大きいようであれば相続税の申告は原則不要です。 ただし、申告手続きを取ることが条件となる特例等もあるので注意を要します。
実際の相続税の計算は素人の方には複雑で難しいため、相続が発生して計算が必要になった場合は税理士に相談するのが安全です。
税務署から「お尋ね」の文書が届いたら・・・?
税務署は被相続人の資産に関するいろいろな情報を有していることがあり、死亡の事実も市区町村の役場を通じて知ることができます。
被相続人の資産状況から、相続発生によって相続税の申告納税が必要とはっきり分かる場合は直接申告書を送ってくることもありますが、「必要かもしれない」という程度の場合は俗にいう「お尋ね」が送られてくることもあります。
この中身は実は相続税の簡易チェックシートになっていて、相続人が自分で簡易的なチェックができるようになっています。 これは正式な申告書とは違いますので、必要な場合は別途正式な書面様式を使って手続きを踏まなければなりません。
「お尋ね(チェックシート)」には、中身を記入して正式な申告書と一緒に提出するようにと書かれていますが、提出しなくても罰則のようなものはありません。
ただ、税務署としては情報収集として行っている面もあるので、下手に勘繰られないためにも提出した方が無難でしょう。
それでも、いきなりお尋ねのシートに書きこむのではなく、コピーを取ってコピー側に自分なりのチェックを入れてみて、それを基に一度税理士にアドバイスを受けることを強くお薦めします。相続税についてできるだけ有利に動くためには味方となる税理士のアドバイスを受けるのが得策です。
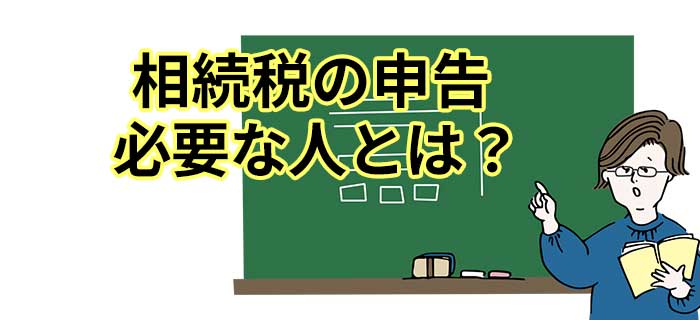
【お役立ちコンテンツ】
相続相談はどこにするべき?専門家(税理士、司法書士、弁護士)の強み
相続税はいくらからかかるのか?節税対策の必要性と金額の計算方法
代襲相続人とは?代襲相続と再代襲相続のケース別具体例
みなし贈与とは?贈与税が発生するケース
相続人になれないことがある?~相続欠格・相続廃除について
相続人の範囲と法定相続分について
基礎控除や配偶者控除、法定相続分を考慮した相続税の計算方法
限定承認とは?手続き内容と、メリット・デメリット
相続手続きは「相続関係説明図」から始まる
相続を「したことにされる」!?~法定単純承認とは
複数の相続資格があるとき、相続分はどうなる?
家族信託と信託銀行について
もめないために事前にできる相続・節税の対策は?
相続人に未成年者がいる方は必見。「未成年者控除」のポイント
配偶者控除の基本
「家族信託」の基本と家族信託が使われる具体的なケース
相続税額早見表【保存版】課税額・家族構成別
法定相続人とは?法定相続人の範囲・順位・相続分を解説
要点をチェック!遺産相続の基本~「相続分」について
我が家はいくら?早見表ですぐわかる 相続税額早見表【保存版】
節税対策として効果的?養子縁組について
【クレアスの相続税サービス】
